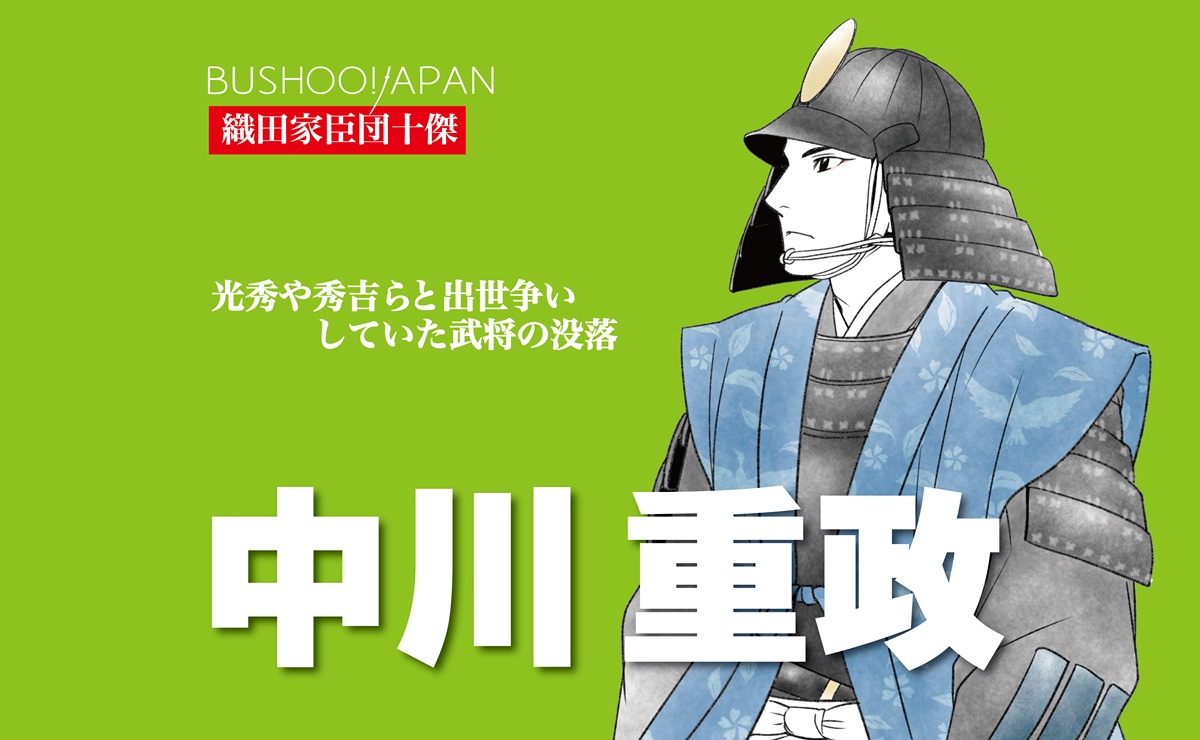戦国時代でダントツの人気を誇る織田信長。
その一門出身で、内政手腕もあって、織田家臣団トップテンに名を連ねた武将がいる――と聞けば、ものすごい武将だと思いますよね?
『信長の野望』シリーズでも、きっとカッコいい顔グラフィックで、パラメータも高いんだろうなぁ……と。
しかし、そんな立ち位置から悲しくもフェードアウトしてしまった武将がいます。
中川重政――。
一時は光秀や秀吉らとも出世争いをしていたほどの武将は、なぜ没落してしまったのか?
その歴史を追ってみましょう。
お好きな項目に飛べる目次
中川重政は織田一門なれど出自の詳細は不明
中川重政は、織田信長と血縁関係があります。
しかし、一門とはされておりません。
なぜか?
ざっと系図を記しますと
織田信次(信長の叔父)
│
織田刑部大輔
│
中川重政
※『織田系図』など
となり、信長から見ると従兄弟の子供に当たるんですね。
ただし、この系図には、重政と信長の関係にムリがありまして。重政には「永禄年間(1558年~1570年)」から活躍の記録があり、信長の子供世代ではなくそれより上の世代ではないか?と目されています。
もしかしたら父親の『織田刑部大輔が存在しないのでは?』とも危ぶまれていますが、ともかく他の史料から重政が織田一門であることは確定的だとされています。
重政は、信長の馬廻衆である「黒母衣衆」をつとめていました。
黒母衣衆には後に大名となる佐々成政、赤母衣衆には前田利家などが在籍。
-

信長の側近から戦国大名になった佐々成政~秀吉に潰された生涯53年
続きを見る
-

前田利家~槍の又左62年の生涯~信長に追放されてもド派手に復活!
続きを見る
大将自ら先陣へ立つ織田信長を支えていた強力な直臣軍団であり、その中に名を連ねていた重政も、当然、相応の武力を兼ね備えていたと考えられます。
しかも重政には、内政担当者としての能力も有しておりました。
織田家臣団十傑の一人
永禄11年(1568年)、足利義昭を将軍にするため信長が上洛を果たしました。
その際、先頭で働いたのが次のメンバー。
柴田勝家
蜂屋頼隆
森可成
坂井政尚
いずれもこの時期の織田家重臣たちであり、この四人組からやや遅れて佐久間盛信が加わります。
彼等は京都と近畿の内政を担当することとなり、禁制の発布や税金徴収など、来たる織田の天下に向けて、地固めを進めるのでした。
翌永禄12年(1569年)になると、さらに次の四名が加えられます。
丹羽長秀
木下秀吉
明智光秀
中川重政
織田家臣団でも錚々たる面々――この中に重政が名を連ねるのですから、相当な実力があったのでしょう。
信長には、他にも多くの親類がおりましたが、織田一門で、この政治・外交のトップ集団にいたのは中川重政だけです。
ちなみに、こうした状況から考えられる当時の織田家トップ10武将は次の通りになります。
柴田勝家
蜂屋頼隆
森可成
坂井政尚
佐久間信盛
丹羽長秀
木下秀吉
明智光秀
中川重政
滝川一益
主に京都と近畿地方を担当していた九人に加え、伊勢方面で活躍していた滝川一益を加えた面々です。
とはいえ、この時点での中川重政は馬廻に過ぎません。
内政手腕はあっても、やっぱり欲しいのが武功。
信長に、そうした配慮があったのでしょうか。
元亀2年(1570年)、六角氏残党にとどめを刺すべく、琵琶湖南岸に将兵が配置されることになり、重政も一角を任せられました。
配備先は安土。織田家でも睨みを利かせる位置にいた重政。
そんな彼に、加増のビッグチャンスが迫ります。
比叡山の攻略です。
なぜ比叡山を攻撃したのか
元亀二年(1571年)9月、信長は比叡山焼き討ちを実行しました。
明智光秀らが中心となって進めたとされ、その中には中川重政もおりました。
延暦寺焼き討ちの被害規模については、昨今の遺構調査などから「膨大な数の被害者のわりに遺骨が出てこないし、焼かれたという建造物の跡も出てこない」とあり、さまざまな疑問符が付いています。
-

比叡山焼き討ちを強行した信長~数千人の虐殺大炎上は誇張なのか?
続きを見る
-

史実の明智光秀は本当にドラマのような生涯を駆け抜けたのか?
続きを見る
ここで考えたいのは、洋の東西を問わずに起きる、権力者と宗教の対立です。
両者はしばしば衝突しますが、それはなぜか――。
宗教の教えが気に入らないから?
確かに信長と比叡山の場合、信長の性格に結びつけられがちではあります。
「比叡山は口先ばかりで堕落していたからだ!」
「合理的な信長は迷信のようなものを嫌う!」
そういうこともないとは言い切れませんが、個人的な趣味でいちいち寺と対立するほど信長も暇ではないはず。
-

史実の織田信長はどんな人物?麒麟がくる・どうする家康との違いは?
続きを見る
結論を先の延べますと「金」です。
「きん」ではなく「カネ」ですね。
それが中川重政と関係あるの?と結論を急がず、しばし類似事例をご覧ください。
※続きは【次のページへ】をclick!