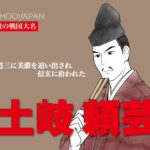戦国大名には、後に大きく飛躍するためのキッカケとなる敵対勢力がいるものですが、あの【美濃のマムシ】として恐れられた斎藤道三にも「噛ませ犬」的なキーマンがおりました。
それが土岐頼純です。
普段はほとんど注目されないこの武将。
2020年大河ドラマ『麒麟がくる』でも一瞬の登場ながら、道三(本木雅弘さん)の前で【毒殺される】という非常に重要なシーンを担っておりました。
出番は少ないながら当時の政局に一石を投じた土岐頼純は天文16年(1547年)11月17日が命日――その生涯を振り返ってみましょう。

土岐頼純/wikipediaより引用
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
土岐頼純の父とおじが対立する美濃国に生誕
土岐頼純は大永4年(1524年)、美濃国守護の家系である土岐頼武の長男として生まれました。
叔父には美濃守護の土岐頼芸(よりあき/よりのり・頼武の弟)。
そんな名族の生まれでしたが、当時の美濃国は土岐氏の勢力が衰退しており、家臣であったはずの長井氏や斎藤氏が主家をしのぐ勢いで台頭していました。
さらに周辺諸国の六角氏や朝倉氏の介入もみられ、非常に不安定な政情にあったのです。
こうした諸勢力の対立は、「頼武・頼芸兄弟」の父である土岐政房を巻き込み、一族内での権力争いに繋がりました。
政房は、長男だった頼武を軽んじて、頼芸を後継者に据えようとしたのです。
しかし、斎藤氏の有力者であった斎藤利良が、政房の意向に反して頼武を担ぎ出したところから、両者は骨肉の争いに明け暮れることに……。
わかりやすく図式化すると以下の通りですね。
土岐頼芸(弟)&土岐政房(父)
vs
土岐頼武(兄)&斎藤利良(家臣)
そして永正15年(1517年)、両者の間で初の衝突!
緒戦は一進一退の攻防を繰り広げました。
最終的には、政房&頼芸親子の勝利で幕を閉じ、利良は頼武を引き連れ、彼らに友好的であった越前朝倉氏のもとへ落ち延びてゆきます。
※以下は朝倉義景の生涯まとめ記事となります
-

朝倉義景は二度も信長を包囲しながらなぜ逆に滅ぼされてしまったのか
続きを見る
政争を制した頼芸は無事に美濃国主の座に就く……と思われましたが、ここで不運不幸なことが。
最大の支持者であり、父でもある政房が亡くなってしまうのです。
頼武が朝倉氏の力を背景に家督を継承
「チャンス到来!」とばかりに息巻いたのが斎藤利良でした。
利良は、頼武を連れて帰国すると、現在の岐阜県山県市にあった大桑城を本拠とし、もともと頼武が嫡男であるという正当性や、朝倉氏の力を背景にして家督の継承に成功します。
以後、美濃国にはひとときの平和が訪れました。
頼武は守護として治世を行っていた形跡が確認でき、利良も彼の右腕として活躍していたのでしょう。
しかし、美濃国主の座を諦めなかったのが土岐頼芸です。
-

道三に追われ信玄に拾われた土岐頼芸~美濃の戦国大名83年の生涯
続きを見る
頼芸は、当時朝倉・六角氏と対立していた浅井氏の支持を得て、大永5年(1525年)に挙兵。
利良を戦死させ、兄の頼武を歴史上から消し去りました。
明確に死亡したという記録はありませんが、消息が絶たれたことからこのとき頼武は死亡したと考えてもよいでしょう。
以上ここまで、頼純の父である土岐頼武と、おじである頼芸による政争の経過を記してきました。
土岐頼純に何の関係が?
と思われたかもしれませんが、大いにあるのです。
実は、頼武・頼純親子には「同一人物説」もあり、その場合「頼武の生涯」とされている部分も「頼純の生涯」と考えられるのです。
※続きは【次のページへ】をclick!