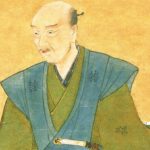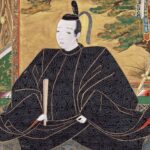慶長五年(1600年)8月1日は【伏見城の戦い】と呼ばれる激戦があった日です。
いわば関ヶ原の戦いの前哨戦とも言えるこの合戦。
その結果や、後の展開に与えた影響を振り返ってみましょう。
三成を隠居に追い込んだ家康
まずは当時の状況をざっくり見てみますと。
【文禄・慶長の役】やそれ以前のアレコレで福島正則や加藤清正などから恨みを買いまくっていた石田三成。
※以下は石田三成の生涯まとめ記事となります
-

石田三成・日本史随一の嫌われ者を再評価~豊臣を支えた41年の生涯
続きを見る
自ら火に油を注ぐような言動をしていたため、ますます関係がこじれていました。
豊臣秀吉や前田利家の存命中は何とか火種がくすぶる程度で済んでいたのですが、二人が亡くなると一気に着火し、三成が福島正則らに襲撃され(かけ)るという事件が起きてしまいます。
これを口実に家康が「石田殿はちょっと引っ込んでいたほうがよかろう^^」(超訳)といって、三成を居城・佐和山(現・滋賀県彦根市)へ半ば隠居させてしまいました。
伏見城に元忠を置いて会津へ
同時に家康は、神指城を整備するなど戦の準備にとりかかるような上杉家へプレッシャーをかけます。
と、同家の重臣・直江兼続から一通のお手紙が届きました。
「武家が武装を整えるのは当然ですし、その他も領民の至便を思ってやっていることですので、ウチの殿様はちっとも悪くありません^^ アタマおかしいのはそっちじゃないですか」
このナメくさった手紙は、いわゆる【直江状】と呼ばれ、関ヶ原のキッカケとして知られますね。
文面の詳細等は以下の記事をご覧ください。
-

家康激怒の『直江状』には何が書かれていた?関ヶ原の戦いを引き起こした手紙
続きを見る
-

戦国武将・直江兼続の真価は「義と愛」に非ず~史実に見る60年の生涯
続きを見る
ともかく上杉家から喧嘩を売られたも同然の徳川家康は軍勢を引き連れ、上杉家の領地・会津へ向かいます。
いわゆる【上杉征伐】ですね。
むろん全軍を東北に派遣させるワケにもいきません。
特に近畿は、豊臣派が多く、政情不安定なエリアでもありますから、防御の楔を打ち込んでおかねばならない。
そこで、秀吉が隠居所にしていた伏見城へ配しておいたのが信頼できる家臣・鳥居元忠でした。
「1,800vs40,000」の絶望的な籠城戦
この、鳥居元忠が守る伏見城へ、挙兵した石田三成が襲いかかります。
【伏見城の戦い】と呼ばれ、戦いの概要は以下の通り。
元忠の率いる伏見城の防御は兵1,800。
対する西軍は、宇喜多秀家・小早川秀秋など、西軍の主要どころがおり、約40,000にも達しておりました。
-

宇喜多秀家は27歳で豊臣五大老に抜擢され~意外と長寿な84年の生涯
続きを見る
-

関ヶ原の裏切り者・小早川秀秋はなぜ東軍に?儚い21年の生涯まとめ
続きを見る
単純計算20倍。
もはや計算するのさえ無意味なほど圧倒的兵力の差です。
「関ヶ原の戦いは、老練な家康が、キレる三成を手玉にとって起こさせた合戦」
フィクションでは時にそんな描かれ方をされますが、家康にだってそんな余裕はなかったでしょう。
なんせ福島正則や黒田長政などの豊臣系武将がいつ西軍に戻るかわかりません。三成が挙兵してもすぐに上方へは向かわず江戸城でしばし様子を見ていたほどです。
それだけに伏見城へ楔を差し込んでおいた家康の判断は間違ってはなかったのでしょう。
目と鼻の先にこんな重要な位置かつ小勢の城があれば、三成でなくても「落城させて仲間の士気をあげるにはちょうどよい」と考えるでしょう。
しかし……。
※続きは【次のページへ】をclick!