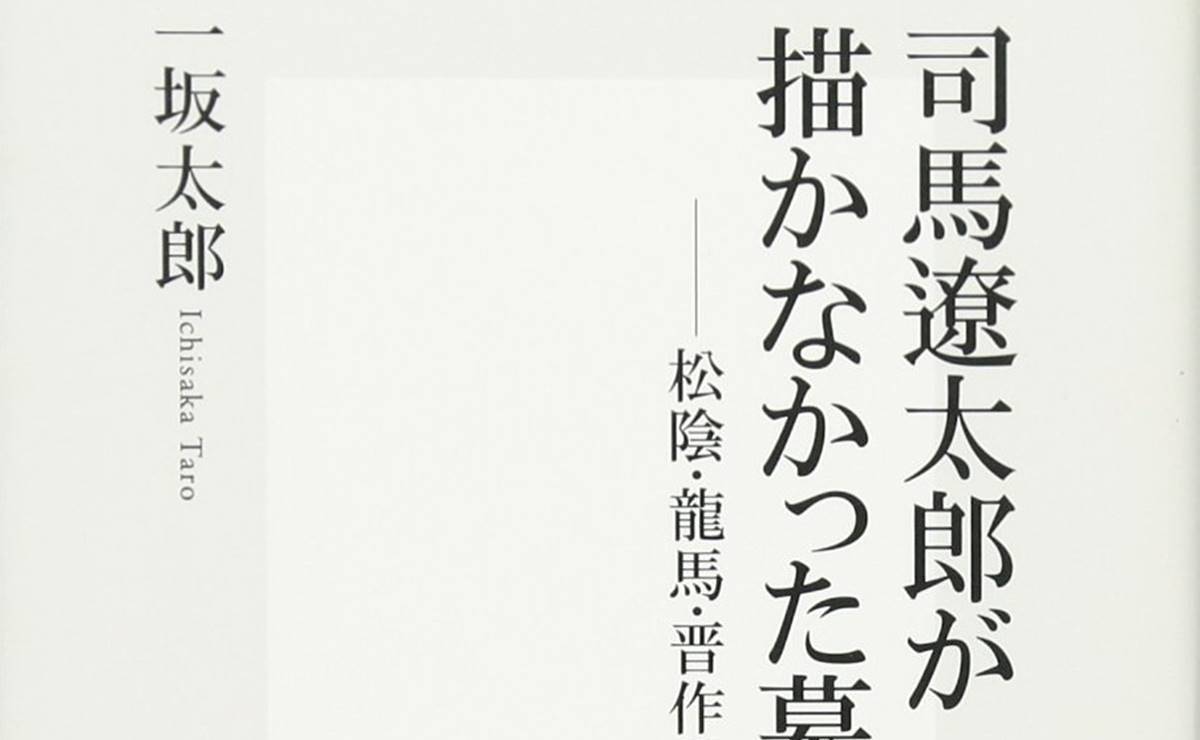司馬遼太郎(敬称略)という作家は、現在でも絶大な人気を誇っています。
坂本龍馬をスターに押し上げた『竜馬がゆく』(→amazon)。
西郷隆盛と大久保利通を描き、大河にもなった『翔ぶが如く』(→amazon)。
そして現在放送中の大河『麒麟がくる』でも注目の斎藤道三と言えば、今なお『国盗り物語』(→amazon)をイメージされる方も少なくないでしょう。
私も彼の作品は愛読していました。
寝る間も惜しんでむさぼるように読みたくなる、圧倒的なおもしろさがありました。
ところが、です。
現在になって彼の著作を読み返してみると、何か違和感をおぼえてしまう。
引っかかってよくよく調べてみると、彼の著作に書かれている「史実」はまったくの創作だったとわかるわけです。
私はあの歴史上の人物の実像ではなく、創作された姿を読んで面白がっていただけなのかと、ガッカリするような、虚しいような。
今回、注目する『司馬遼太郎が描かなかった幕末』(→amazon)の内容は、まさにこの「虚しさ」そのものです。
お好きな項目に飛べる目次
「高杉の武勇伝三点セット」が史実ではないなんて!
本書で取り上げられている人物は、吉田松陰、坂本龍馬、高杉晋作です。
正直に書きますと、私は本書を読んでいる間、何とも言えない辛さも感じていました。
夢中になってページをめくった、彼らが主人公の小説。あの夢中になっていた時間を否定されたようで、虚しさが押し寄せてきたのです。
本書には、かつての自分と同じような思いを抱く男子大学生が出てきます。
この「武勇伝三点セット」が大好きだと語る相手に、筆者が「それはすべて創作ですよ」と指摘したところ、相手は「ならば、高杉晋作って他に何が評価できるんですか?」と問うてきた、とのこと。
彼の気持ちはわかります。
いや、それだけが功績ではないのですけれども、かつての自分もこの部分を繰り返し読み、晋作に憧れていたのです。
彼にとってはきっとこの「武勇伝三点セット」に、晋作のカッコよさが凝縮されていたんだろうなあ、わかるよ~、と肩を叩きたくなります。
痛快エピソードが歴史を揺るがしたように魅せる
司馬作品が厄介なところは、このような痛快なエピソードが、やがて歴史を揺るがしたかのような繋げ方をしているところだ、と筆者は解説します。
「将軍野次事件」がきっかけで政局が複雑化し、なんやかんやで幕長戦争が起こる、という流れにしている。
こういう書き方をされると、ひとつひとつの武勇伝がものすごく重要な意味を持っている気がしてしまう、と指摘するのです。
ここで私の意見を付け加えると、自分や大学生も含めて読者が「武勇伝」を重視する理由は、キャラクター性が崩れるという問題点もあると思います。
「武勇伝三点セット」がある晋作と、ない晋作とでは、どうしても性格が異なるように思えてしまいます。
好きだった相手の性格が、思っていたのと違った――そんなガッカリ感がわいてくるのです。
司馬遼太郎の創作テクがあぶり出されます
本書はこのように、幕末のヒーローたちの虚像と実像の差を丁寧に埋めてゆくのですが、その過程で司馬遼太郎の読者を引き込むテクニックがあぶりだされます。
言い方は悪いけれども「騙しのテクニック」とも呼べるかもしれません。
・都合の悪い話は書かない
・作者の強調したい表現を何度も繰り返す
・経緯を省いて大きく歴史が動いたように見せる
手元を隠していきなり空中にハトを出現させるマジックショーのような、そんなテクニックが見えて来ます。
本書は幕末のみを扱っていますが、同じトリックを使っているのであれば、他の著作も気をつけて読まねばならないでしょう。
※続きは【次のページへ】をclick!