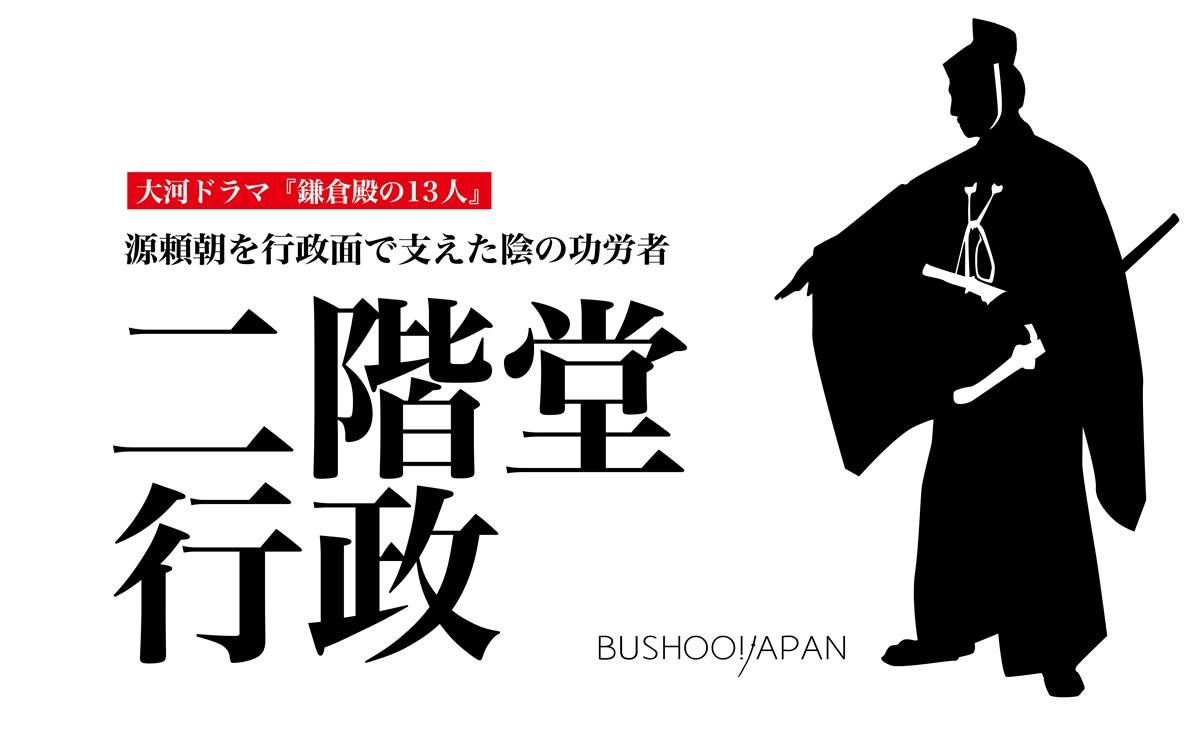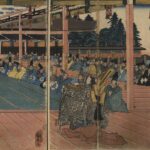大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で、ほとんど存在感のない人物だったのに、終盤、急激に悪目立ちされた方がいます。
二階堂行政(ゆきまさ)です。
史実では、鎌倉幕府の文官であり、いかにも真面目な役人タイプなのですが、ドラマでは孫の伊賀の方が北条義時の後妻となったことから、しきりに「政権に喰い込もう!」という姿勢がクローズアップ。
『さすが鎌倉幕府、あんな悪いオッサンもいたのか……』
と思われた視聴者も多いかもしれません。
しかし実際の二階堂行政の事績を見ると「名は体を表す」という言葉通り、「行政(ぎょうせい)をそつなくこなしたお方」という印象が浮かび上がってきます。
実際、彼は官吏になるため生まれてきたかのような血筋で、藤原南家・乙麻呂流工藤氏の子孫だといわれています。
血の流れを簡単に示しますと、
藤原不比等
|
武智麻呂(むちまろ)
|
乙麻呂
|
(略)
|
工藤行遠
|
行政
となり、父の工藤姓から「二階堂」に変わったのは、邸宅の近所にあった寺院に由来します(詳しくは後述)。
厳密にいえば、二階堂氏を名乗り始めたのは子孫からで、行政本人に関する記述はおおむね”藤原行政”なのですが、そのまま進めていきましょう。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
二階堂行政は頼朝と親類関係
まずは二階堂行政の両親に注目してみますと、父母の出会いは、なかなか衝撃的だったようです。
父の行遠が遠江の国司を殺害して尾張に流され、そこで熱田大宮司の娘だった行政の母と知り合い、その間に生まれたと伝わります。
熱田神宮に縁があると言えば源頼朝。
※以下は源頼朝の生涯まとめ記事となります
-

源頼朝が伊豆に流され鎌倉幕府を立ち上げるまでの生涯53年とは?
続きを見る
頼朝の母も大宮司家の娘で、行政とは親類になります(両者の母がいとこ関係)。
行政の青少年時代については、詳しい記録がありません。
治承四年(1180年)1月に主計少允(しゅけいしょうじょう)へ任じられているため、少なくともこの前後は朝廷の役人だったことがわかります。
主計寮(しゅけいりょう・かずえのつかさ)は民部省下の役所の一つ。
“計”とつく通り、税の量を計算したり、実際に収められた税を計ったり、帳簿と照合することが主な仕事でした。
少允(しょうじょう)は上から四番目の役職で、官位では従七位上に相当します。
身分はあまり高くないものの、由緒正しいお役人……というイメージでしょうか。
鎌倉幕府の内政業務で重用され
そこからまたしばらく記録が飛び、次に登場するのは『吾妻鏡』の元暦元年(1184年)8月24日。
-

鎌倉幕府の公式歴史書『吾妻鏡』が北条に甘く源氏に厳しいのはなぜか
続きを見る
この日、二階堂行政は公文所(くもんじょ・鎌倉幕府の政庁)の上棟式の奉行を三善康信(みよしやすのぶ)と共に務めた、と記されています。
三善康信は同年4月14日に鎌倉で頼朝と対面しているので、この前後に行政も到着していたのかもしれません。
また、約半年後の10月6日に行われた公文所の「吉書始(きっしょはじめ)」では、寄人(よりゅうど・職員)として列席しています。
この時点で行政は、頼朝にとって「内政の要となる人物の一人」と認識されていたのでしょう。
同時期から、
・主要な寺社に関わる工事の指揮
・物品や書面の手配
などにたびたび関わるようになります。
いくつか例を挙げてみますと。
◆元暦二年(1185年)5月8日
大江広元・三善康信とともに治承・寿永の乱の際に破損した宇佐八幡の修理や今後の待遇、西国のことについて書面を作った
◆文治元年(1185年)9月5日
小山有高と威光寺の領地に関するトラブルについて聴取があり、広元らとともに書面を作った
◆同年9月29日
南御堂勝長寿院の工事が捗っていたので、大工たちへの褒美として長絹を手配した
◆同年10月21日
南御堂勝長寿院の本尊・阿弥陀仏運搬の指揮を善信らとともに担当
先ほど「行政」という名が体を表す――と申しましたように、内政に携わる場面で重用されているのがわかりますね。
もちろん頼朝からの信頼も上々だったようで、文治二年(1186年)3月1日には、鎌倉に護送されてきた静御前(源義経の愛妾)とその母・磯禅師の宿所を行政が指定しています。
-

「静御前・郷御前・蕨姫」義経を愛した女たち その非情な命運とは?
続きを見る
-

史実の源義経はどんな生涯を送り最期を迎えた?鎌倉殿の13人菅田将暉
続きを見る
頼朝vs奥州藤原氏の静かな戦い
行政の特徴としては、大江広元や三善善信のように具体的な発言が記録されていないこともあげられます。
元の身分が彼らほど高くないこともあるのでしょうか。実直謹厳に仕事をこなすタイプだったのかもしれません。
-

朝廷から幕府へ 大江広元は頼朝や義時のブレインをどう務めたか?
続きを見る
文治二年(1186年)5月29日には、東海道地域の寺社を復興するための資料作りに参画。
そのおよそ半月後には、上総の荘園に関するトラブルについて書類作成を命じられており、なかなかのハードワークぶりです。
また、文治二年と文治五年(1189年)には、馬に関する話題が一回ずつ出てきます。
どちらも行政が実務を担当しており、まずは文治二年10月3日の話題から。
この日、奥州藤原氏から朝廷へ献上する馬と黄金を鎌倉に送ってきました。
なぜわざわざ鎌倉を経由したのかというと、頼朝が奥州藤原氏に
「朝廷に献上する馬や金は、私が仲介しよう」
と申し出た(恫喝した)からです。
これまで直接京都へ届けていたのに、この言い草はどう見ても傲慢ですが、藤原秀衡(ふじわらのひでひら)は逆らわずに受け入れました。
-

義経を二度も匿った藤原秀衡~奥州藤原氏の名君はどんな武士だった?
続きを見る
すでに平家討伐を終わらせて勢力を拡充させる頼朝と、真っ向から戦うことを避けたのです。
弱腰にも見えてしまいますが、秀衡は非常に老獪な政治家で、代々築き上げてきた奥州一体の自治を保つために努力を重ねてきています。
例えば、
・平家が奥州藤原氏に高官を与え、源氏討伐をほのめかしてもスルーしたり
・平家に焼かれた東大寺の再建費用を、頼朝の五倍も出したり
状況がどの方向に転んでも、どこかの勢力と手を結んで生き延びられる立場を保ち続けていました。
対して、鎌倉で新政権を作りたい頼朝としては、秀衡は目の上のたんこぶ。
奥州藤原氏が健在である限り、東北に鎌倉の支配力が及ばないからです。
たとえ秀衡に反抗的な態度がないとはいえ、直接支配できないのは実に歯がゆい。頼朝としては秀衡を怒らせて武力行使に持ち込み、それを口実に武力でねじ伏せてしまいたいわけです。
秀衡はそれを読み切っていますから、ときには下手に出てでも奥州の自治を守ろうとしているんですね。
頼朝も武将というよりは政治家タイプですが、この辺は「亀の甲より年の功」という感があります。
※続きは【次のページへ】をclick!