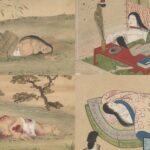暦応四年(1342年)12月23日は、天龍寺船の計画が立てられた日です。
天龍寺船とは、何となくイケてる字面ですよね。
ただ、この計画の始まりはあんまりカッコよくありません。
お好きな項目に飛べる目次
怨霊に悩まされるようになり……
当時は室町時代の始め。
足利尊氏とその弟・足利直義、そしてブレーン役の僧侶・夢窓疎石は、新しい政権の基盤を整えるため、アレコレと忙しい日々を送っていました。
※以下は足利尊氏の生涯まとめ記事となります
-

足利尊氏は情緒不安定なカリスマ将軍?生誕から室町幕府までの生涯
続きを見る
そんな中で、切っても切れない縁の後醍醐天皇が亡くなった――そんな知らせが届きます。
足利サイドにとっては政権をスムーズに運営できるようになったのでは?
と思うかもしれませんが、現実はさにあらず。
尊氏は、後醍醐天皇の怨霊に悩まされるようになってしまうのです。
-

後醍醐天皇の何がどう悪かった?そしてドタバタの南北朝動乱始まる
続きを見る
怨霊が実在するかどうかはさておき、尊氏は好きで後醍醐天皇と対立したわけではなかったので、亡くなるまで正式に和解できなかったことを悔やんでいたのでしょう。
もともと日本史上でも屈指の“か弱い”メンタルを持つ尊氏が、何とかして後醍醐天皇に許しを請いたいと考えるのも当然の流れ。
おそらく、直義も疎石も「またか」と思いつつ、ドン底モードになってしまった尊氏の精神を回復させるため、いろいろな手を講じたと思われます。
そして「新しく寺を造り、後醍醐天皇の霊を慰めれば、尊氏の気分も良くなるだろう」という結論が出ました。
中国に送った貿易船で寺社の造営費を捻出
お寺を建てる場所は、亀山殿という皇室の離宮だった場所に決まります。
ここはかつて檀林皇后が開いた「檀林寺」というお寺がありました。
-

「私の遺体は道端に放置し鳥や獣に与えよ」檀林皇后の凄まじき終活
続きを見る
檀林寺が廃寺同然になってしまった後、第88代の天皇である後嵯峨天皇とその息子である亀山天皇が「亀山殿」という離宮を作った場所でもあります。
西に小倉山を臨む、とても景色の良い場所ですので、怨霊を慰めるには良い場所だと考えられたのかもしれません。
しかし、離宮をお寺にするには、それなりの工事が必要です。
当時の幕府には、とてもその余裕がありませんでした。南北朝の争いは未だ終結したとはいい難く、戦費に押されてカツカツだったのです。
となると、どこかでお金を稼がなければ、せっかく立てた計画もおじゃんになってしまいます。
そこで、直義たちが思いついたのが「寺社造営料唐船」でした。
「中国に貿易船を派遣し、その儲けで寺社を作る」という計画で、鎌倉時代にも建長寺(鎌倉市)創建のため派遣した前例があり、直近でも、元弘ニ年(1332年)に住吉社造営料唐船が中国へ行っていました。
前例のあることなら、朝廷からの許可も得やすいですしね。
しかし、当時の中国は倭寇(大陸沿岸で暴れまわっていた海賊)にかなり悩まされていた時期。
「話はわかったけど、事前に連絡をもらうにしても、海賊船と見分けがつかないよ(´・ω・`)」(※イメージです)となかなか好意的になってもらえなかったとか。
※続きは【次のページへ】をclick!