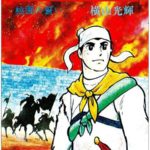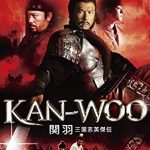2020年代は文化面におけるアジアの存在感が世界でより意識されることになるのでしょう。
中国製のアプリも増えています。
そして2022年6月16日には、中国で大ヒットして社会現象にもなったアプリの日本版『水都百景録』がリリースされました。
このアプリの事前登録特典は……
・中国史上唯一の女帝・武則天
・潘安
武則天は世界史で習うしドラマもあるけれど、潘安って誰?
なんと中国史上最高のイケメンです。「潘又安」(潘安の再来)というイケメンを指す言葉もあったほど。
こうしたアプリは、映像作品のファンも狙っています。
映像作品では『愛の不時着』や『梨泰院クラス』が人気を博し、ビルボード1位を獲得したBTSに至っては世界クラスで大ブレイク!
日本でもこうした第3次韓流ブームが歓迎される最中、ジワジワと勢力を伸ばしているのが華流ドラマ(中国語圏ドラマ)です。
『陳情令』がAmazonランキングの海外ドラマでトップを獲得しました。
秋にはNHK BSプレミアムで『コウラン伝 始皇帝の母』が放送され始めました。
さらには日本発の中国史邦画『キングダム』や『新解釈三国志』などがあり、なんとなーく気になっている方もおられるでしょう。
「『陳情令』は好評よの」
「ククッ、二番煎じの目敏さに定評のある中国では、もはやBLドラマが群雄割拠よ……」
「なんと!」
「共産党が禁止令を出したとかなんとか言う者もおるが、かの国の禁令はいたちごっこが基本。ますます伸びる」
「つまりは華流BLがブームの予感とな?」
「左様」
「しかし、美男美女でキラキラしているウェブ記事や関連書籍で、歴史的なBLについては語っておらんようだが」
「そう、そこが問題よ」
と、突然、妙な会話をぶっこんでしまい申し訳ありませんが、今、彼の国では華流BL・イケメンブームとも言える動きがキテいます。
いや、正確に申しますと、そんな一過性のものでもなく、中国史を紐解けば、BL・ブロマンスが頻繁に取り扱われてきたものなのです。
一体こいつは何を言ってるんだ?と思われることは百も承知で考察してみたい。
本当に中国史でBLはアリなのか?
真面目に進めていきましょう。
【TOP画像】
『三国志 Secret of Three Kingdoms』(→amazonプライムビデオで無料)
お好きな項目に飛べる目次
『陳情令』もBLかもしれないが『三国志』にもあった
華流が燃え始めた2020年秋。
そんな中でも注目のドラマが『三国志 Secret of Three Kingdoms』です。
-

マニアも唸る『三国志 Secret of Three Kingdoms』23の疑問に回答
続きを見る
美男美女まみれで『三国志』の話なのに、劉備も孫権も出てこないばかりか、主役はなんと献帝の双子の弟!
本国放送からほどなくしての配信で、日本で今最も熱い『三国志』です。
しかも、これは『陳情令』を先取りするBLではないかと思われる作品です。
献帝と入れ替わった劉平と、そんな劉平を弟のように思う司馬懿。そんな二人の関係性で、漢、魏、そして晋への王朝交代を描く――こうまとめると無茶苦茶としか思えないのですが、極めてレベルが高いのですから恐ろしい。
もう、曹操が劉備に向けて語った、
「天下の英雄は、君と余だ!」
という言葉すら愛があるように思えてしまい……作り手もそのあたりは理解しているのでしょう。
劇中で常に郭嘉を推してくる満寵が「郭❤︎嘉」ハチマキをつけるコマーシャルまで作られるほど――といったファントークは横に置き、本稿では歴史的な考察に取り組んでみたいと思います。
中国史でBLはありなのか?
ジャーンジャーンジャーン!
中国史でBL。しかも『三国志』ものといえば、日本でもそういう扱いの作品はあります。
代表的なものとしては
等ですね。
そもそも、古典的な名作である吉川英治の『三国志』ですら「恋の曹操」(※関羽に恋をして引き留めようとする場面、3巻収録)という章題を使う始末。
横光版も、いろいろな意味で熱いものでした。
-

不朽の名作『横光三国志』はいわば日本の町中華? その成立を考察してみた
続きを見る
関羽に恋焦がれる曹操は、本場の映画でもそういう描かれ方ですので、もう仕方ありません。
いわば公式が最大手です。
-

これが21世紀理想の関羽像だ!『KAN-WOO 関羽 三国志英傑伝』感想レビュー
続きを見る
ある意味手遅れのような気もしますが、あえて歴史と文学史として、この点を考えてみましょう。
「断袖分桃」――それは禁断の愛
同性愛とは、国と地域、文化、宗教によってかなり扱いが異なります。
キリスト教圏、イスラム教圏等では重罰の対象。
一方、儒教圏としてまとめられる東アジア(日本・中国大陸・朝鮮半島)はどうでしょうか。
絶対禁止ではないものの、奨励されるかどうかは異なります。
日本だけとってみても、江戸時代は藩によってかなり異なりました。古代ギリシャ並に盛んだとされる薩摩藩もあれば、禁止令があった藩もあるのです。
-

日本が男色・衆道に寛容だった説は本当か?平安~江戸時代を振り返る
続きを見る
まとめますと東アジア圏では一部をのぞき、同性愛は「トラブルを引き起こす困ったもの」扱いでした(女性の同性愛につきましては割愛)。
なまじ男を寵愛するとなると、政治権力を与えることにもなりかねない。
腕力が強いだけに、深刻なトラブルを引き起こす。
そもそも、子孫繁栄に繋がらないことにエネルギーを使うのはどうなのか?
そんなマイナス評価がくだされるんですね。
暗愚とされる人物には同性愛傾向があったという誇張もされたりします。日本での典型例は蘆名盛隆でしょう。
困ったもんなんですよ、主君が美少年に夢中になるとね……。
中国史における男性同性愛をあらわす言葉とて、ボヤキ混じりの有名なものがあります。
【断袖分桃】です。
◆断袖(=袖を切る)
前漢・哀帝は、寵愛する董賢と昼寝していて目を覚ましました。すると董賢が自分の袖の上で寝ているじゃありませんか。
「もぅ……でも起こせない❤︎」
そう思い、袖を切ったのです。典型的な、主人による寵愛ですね。
董賢は皇帝の覚えめでたく、どんどん出世。哀帝のあとは王莽が王朝を簒奪します。
こういう私情によるしょうもない政治の乱れを起こすこととして「BL、ダメゼッタイ!」というニュアンスがあります。
◆分桃(中国語・日本では「余桃」を使うことが多い)
衛の霊公は、弥子瑕(びしか)という美少年を寵愛していました。二人で果樹園を散歩していたとき、こんなやりとりが……。
「ねえダーリン、この桃おいしいよ。あげる」
「弥子瑕たん……ありがと〜!」
けれども、霊公の寵愛は薄れてしまいます。
そしてこうなった。
「弥子瑕、お前さあ、主君に食べかけの余った桃食わせるってどういうこと? 処罰するから」
この故事を引く『韓非子』では、主君の寵愛は薄れたら危険だという戒めとしても用いられます。
BLが悪いというよりも、君主や家臣としての心得を説いていると言えなくもありません。そこには戒めのニュアンスを感じます。
それにこのカップリングは果たして心の底から愛し合っていると言えるのかどうか?
利害関係ではないか?
そういう関係性はどうなのか?
もっとソウルフルな関係性はないのか?
そう思ったりしませんか。
そこで考えたいのが【ブロマンス】です。
ブロマンス(英語: Bromance)とは、2人もしくはそれ以上の人数の男性同士の近しい関係のこと。
性的な関わりはないものの、ホモソーシャルな親密さの一種とされる。
Wikipediaより
中国史はブロマンスに溢れている
歴史上でBLとなると、真面目な本でもカップリング扱いされている人物もいます。
ヨーロッパ史でのBLビッグカップルといえば、英仏王の二人でしょう。イギリスのリチャード1世と、フランスのフィリップ2世です。
映画やドラマ化もされた名作劇『冬のライオン』は、この二人がお付き合いをしていたという設定で話が進んでゆきます。
無根拠というわけでもありません。
この二人は同じベッドで眠り、一緒に食事をするほど仲が良かったという記録があります。
-

尊厳王フィリップ2世はフランス史上最強か ドロ沼の英仏関係が面白い
続きを見る
この二人の話に触れたことは、もちろん理由があります。
というのも「同じベッドで寝たらカップリングが成立する」となると、中国史はとてつもないことになってしまいます。
親愛の証として、同性が同じ寝台に眠り、語り合う――それは大いににアリでした。
劉備、関羽、張飛の桃園三兄弟が代表例ですね。
もうひとつ典型例をあげましょう。
※続きは【次のページへ】をclick!