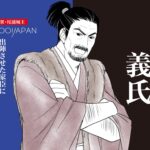山形県最上川西に広がる庄内平野は、日本有数の米どころとして知られています。
ところが、です。
今から四百年ほど前の庄内平野は、平地でありながら不毛の地でした。
それが現在のように生まれ変わったのは、すべて北楯利長(きただて としなが)という最上家の家臣が、困難極まる治水事業を成功させたからであります。
一般的にはほとんど知られることのない武将ながら、やり遂げた功績は決して戦国の名将にヒケをとらないもの。
400年前に一体なにがあったのか。
知られざる歴史を見て参りましょう。
豊臣政権での重税に苦しむ庄内地方
もともとこの地は、戦国時代末に大宝寺義氏が支配しておりました。
内政を軽視し、日々戦いに明け暮れた義氏。
その影響で地元の人々は生きていくだけで精一杯の苦境に苛まされます。
※以下は大宝寺義氏の生涯まとめ記事となります
-

悪屋方と呼ばれ嫌われた戦国武将・大宝寺義氏~家臣に城を包囲されどうなった?
続きを見る
大宝寺氏の滅亡後は、庄内の領有権をめぐって上杉家と最上家が死闘を繰り広げ、さらに豊臣政権の支配が広まると、今度は重税に苦しめられました。
最上領の場合、四公六民か五公五民だったのが、豊臣政権下では全国一律・二公一民とされたのです。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
寒冷地であり、荒れ果てた庄内地方は一毛作しかできず、ただでさえ収穫高の少ない土地でした。
とても生きてはいけない――。
そんな年貢率に苦しんだ領民は【庄内藤島一揆】を起こします。
一揆は上杉家によって鎮圧されましたが、その過程で多くの民が命を落としました。
荒れていた庄内地方はさらに荒み、多くの働き手をも失うことになったのです。
民に慈悲深き義光 目をかけられた利長は立ち上がる
庄内地方が安定したのは、関ヶ原の戦いのあと、最上義光が支配するようになってからでした。
内政手腕に長け、敵には容赦なくとも民には慈悲深い名君・義光。
庄内の民はやっと安寧を見いだすことができたのです。

最上義光像
庄内の狩川城主となったのは、最上家臣の北楯利長(きただて としなが)でした。
石高は三百石程度とも、あるいは三千石とも言われています。
それまでの彼の功績は、あまり伝わっていません。実に2,500名はいたという最上家臣の中で、大きく目立つのは大変であり、そこまでの武功がなかったのでしょう。
では、なぜ取り立てられたのか?
あるとき義光が狩川城に立ち寄った際のこと。
当主自ら武具を点検してみるや、実に手入れが行き届き、さらには銃弾等が多めに備えられていることに気づきました。
以来、義光は、利長に目を掛けるようになったと言います。
利長が庄内でとれた鮭や和リンゴを義光に贈呈し、そのことを感謝した義光からの礼状も残されたりしています。
そんなある日のこと。利長が領内を視察していて、痛ましい光景を見ました。
夏になると大地が干上がり、稲が枯れてしまうのです。
「水がないのはどうしたことか」
利長が尋ねると、民はこう答えました。
「水はどうしても引けないんで、雨や沢の水を使うしかないんです」
「川なら近くにあるようだが」
「それが川と地面の高低差があるんです。どうしても水を引けないんですよ」
そう、原因は地形にありました。
水源になる川はすべて土地より低いところにあって、水を引き込みようがないのです。
ここで普通の人ならば「そうか、仕方ない」と思うところでしょう。
ところが利長は違いました。
「つまり、ここに水を引くことさえできれば豊かな土地になるということか。そうすれば民の暮らしは潤い、殿もきっとお喜びになるだろう」
利長は庄内を豊かにするため、主君に忠誠を尽くすため、現地調査を始めます。
このとき利長は既に50歳過ぎ。
「人間五十年」とも謡われた時代に、新たな人生の可能性を広げ始めたのです。
執念の水源探し
利長は何かに取り憑かれたように、熱心に水源を探し始めました。
人に出会えば「どこかに水源はないか?」と尋ねる利長。
あまりのしつこさに呆れた住民たちが、利長のことを陰で「水馬鹿」と呼び始めたほどです。
しかし、調査すること数年。
熱意と調査の結果、利長はついに月山から流れ出る立矢沢川に目を付けます。
「この流れを変えて堰を作ればよいのだ!」
利長は思いつきました。
もちろん簡単な工事ではありません。利長とその家臣だけでは到底できない大規模な藩営事業になる見込みでした。
そこで利長は大工から技術を学び、完璧な工事請願書を作成。
慶長16年(1611)夏、主君の義光に提出することにしたのです。
義光はその計画書を見て驚き、利長の熱意を感じました。
しかしこの規模となると、藩主の一存で決定できることではありません。重臣たちを呼び集めて評定を開きました。
※続きは【次のページへ】をclick!