幼いころから聡明で美しかったとして知られる『三国志』の甄皇后(しんこうごう)。
コーエーテクモゲームスの『真・三国無双』シリーズでは、甄姫として2001年の『2』に初参戦。
セクシーな衣装と笛を使うキャラクターとして登場し、夫の曹丕(そうひ)と協力して戦います。
その後も多くのゲームに登場し、知名度も高い女性ですが……身分もある女性の死因がハッキリしないうえに、「夫の曹丕に殺されている」のですから恐ろしい話ではありませんか?
そもそも甄皇后は袁紹の子・袁煕(えんき)の妻でした。
しかし、袁紹が【官渡の戦い】で敗北したため危難が迫り、建安9年(204年)、彼女が潜む鄴(ぎょう)の地も、曹操の手に落ちました。
そこで彼女を見つけたのが曹操の嫡男である曹丕(そうひ)です。
甄皇后の美貌に惹かれた曹丕が妻とし、彼女は後の魏明帝・曹叡(そうえい)を産みました。
そして後に文昭皇后甄氏(ぶんしょうこうごうしんし)と呼ばれることに――。
結果だけ見れば皇帝の子を送り出し、シンデレラストーリーかのようにも思えるのですが、夫・曹丕に死を賜っているのは前述の通り。
いったい彼女はなぜ死なねばならなかったのか?
今なお謎多き三国志ミステリの一つを考えてみます。

文昭皇后甄氏/wikipediaより引用
甄皇后 謎の死
太子・曹叡の母である甄皇后。
幼い頃から聡明で、謙虚で、控えめで、美貌もあった。そんな彼女がなぜ死んだのか?
被害者も加害者も明らか。
加害者:曹丕
被害者:甄皇后
されど動機がわからないから三国志ファンを悩ませ、特に陳寿の記述がそっけないため、後世の人間は「異議あり!」とつきつけてきました。
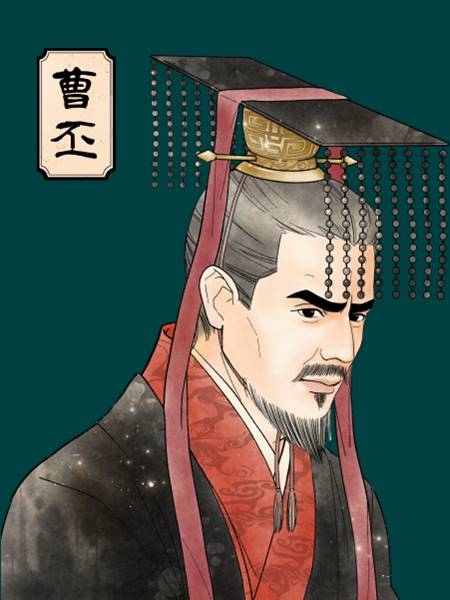
例えば裴松之はこう考えました。
裴松之
死去についての記述があまりにもそっけないのはなぜか?
陳寿が嘘をついているからです。
魏がこれを大罪であるとすれば、隠蔽することでしょう。些細なことだと思えば、美辞麗句で飾り立てて誤魔化す。
この場合は後者……この記述には嘘がある!
裴松之がこのように指摘すると、後世の人々がどんどんと話を膨らませてゆきます。
推理①
郭皇后による女のバトルです。
寵愛を争い、相手の悪口を吹き込んだ。信じ込んだ曹丕が惨殺したんですね。
よくある女の嫉妬ですよ。
推理②
嫉妬は嫉妬でも、この詩をご覧ください。
曹植の『洛神賦』……曹植は義理の姉に恋心を抱き、相手も心惹かれたんですね。
曹丕からすれば、これは許せないわけです。
推理③
口封じではありませんか?
曹叡の生年はハッキリしていません。つまり、甄皇后の前夫・袁煕との子かもしれない。
そのことを知る母である甄皇后は、死なねばならなかったのです……。
いずれも興味深いですね。
曹丕の殺害動機は外戚排除か
こうした先人の推察を読み解くうちに、私なりにひとつの説を推理しました。
こちらです。
筆者なりの推論
曹丕は後漢の外戚政治を問題視していました。
問題解決はカンタン。最初から排除しておけば起こりません。
つまり、太子の生母を殺せばいい。
そして皇后には、バックボーンの薄い(政治力の弱い)一族の者を選ぶ。
随分と殺伐とした推理と思われるかもしれません。
我ながら書いている時点で気分が悪くなってしまいましたが、もちろん当てずっぽうな妄想でもなく、根拠の一つとして注目したのが曹丕の詔です。
彼は以下のような【外戚政治根絶宣言】出しておりました。
曹丕の詔
家臣の皆さん、政治のことを太后に相談してはいけません。
皇后の一族を、政治的な要職につけてはいけません。
天下一丸となって、外戚政治を根絶しましょう!
外戚の影響力はどんな王朝にも見られること。ときに王の政治を圧する……にしても、さすがに殺すのはやりすぎではないか?
そんな指摘もわかりますが、中国史においての実例は少なくありません。
※続きは【次のページへ】をclick!
