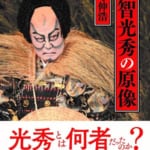【編集部より】
2020年大河ドラマ『麒麟がくる』の主役として、従来のイメージとは異なり、非常に誠実な人間像で描かれた明智光秀。
2023年の『どうする家康』では何とも残念な人物像だったので、2026年『豊臣兄弟』では一体どうなるか?
今から気になっているファンの方も少なくないでしょう。
三英傑(信長・秀吉・家康)と光秀と言えば、100%熱くなるのが、この話題。
「なぜ、光秀は本能寺の変を起こしたのか?」
もう何十何百回と盛り上がってきた話題ですね。
そして何回話し合ったところで答えは出ないものであり、もはや光秀ファンや研究者の間では永遠のテーマとも言えますが、今回、一風変わったアプローチで本能寺の変を考察されてる方がいらっしゃいますので紹介させていただきます。
本年8月に史論『異聞・光秀に成り損ねた男たち』(あさ出版)を発行した窪寺伸浩さんです。
窪寺さんは、戦国史最大のこの事件を一体どう見ているのか。
以下の本文よりご覧ください。

明智光秀/wikipediaより引用
【これより本文へ】
大名同士の権力闘争に非ず
天正10年(1582年)6月、織田信長は、明智光秀による謀反「本能寺の変」で討たれ、天下統一の夢が潰えます。
その後、羽柴秀吉と明智光秀による山崎の合戦を皮切りに繰り広げられたのは、信長亡きあとをめぐる苛烈な権力闘争でした。
山崎の合戦で明智は滅び、そのわずか4年後には、当時羽柴側についた、柴田勝家、滝川一益、織田信孝ら主要な大名たちは皆、すでにこの世を去りました。それだけ激しい争いが繰り広げられたわけです。
では、その発端となった「本能寺の変」も、大名同士の権力闘争の一つととらえるべきものなのでしょうか。
私は、この「本能寺の変」は、そうしたものとはまったく異質なものであり、それゆえに時代を超えて、私たちの心をひきつけると考えます。
光秀は「ブルータス」だったのか
光秀に関する歴史的な資料は、断片的な光秀評を除いて、ほぼ存在していません。
歴史は、勝者の側から語られるものであり、敗者である光秀の記録が残っていないのは、ある意味、当然と言えるでしょう。
ですから、「本能寺の変」を起こした光秀の真意はわかりません。
ですが、私が今回まとめた史論『異聞・光秀に成り損ねた男たち』で述べたように、そこには恨みだとか、ましてや天下を取りたいなどといった、私心はなかったと考えます。
光秀は、信長・信忠親子を討ち果たした理由として「天下の妨げとなる悪逆」だったからと書状に残しています。
私は、この言葉に、ローマ皇帝、ジュリアス・シーザーを暗殺したブルータスを重ね合わせてしまいます。
ブルータスは、シーザーを愛していました。ですが、それ以上にローマを愛しており、ローマの誇りである共和制が危機に瀕していたことから、シーザーを手にかけたと言われています。
光秀と信長の関係も決して悪いものではありませんでした。
なぜ、信長が無防備ともいえる、わずか数十人で本能寺に宿泊したか、それは光秀が京都にいる安心感からでした。
諸説あるものの、信長が謀反の知らせを聞いたとき、相手が光秀だと知ると「是非に及ばず(仕方がない)」と口にしたともされています。
光秀自身も信長に恩義を感じていることを、明智の家中軍法で述べています。
信長に出会ってからわずか10年で重臣になったことからも、お互いに通じ合うものがあったことがうかがえるでしょう。
矮小化された光秀の真意
にもかかわらず、光秀が信長を滅したのは、なぜか。
それは、ブルータス同様、信長を愛する以上に、日の本を愛し、この国の行く末に危機感を抱いていたからでではないでしょうか。
このままでは帝がいなくなり、皇統が途絶えてしまうかもしれない、南蛮の植民地になってしまうかもしれない――もし、光秀がもう少し長く生き、自分の考えを述べる機会があったならば、そのようなことを言ったかもしれません。
実際にそうしたことを書面として細川に伝えていたり、長曾我部や、徳川家康に話していたりしたかもしれません。
ですが、光秀はそのような記録が残るまで生き続けることはできませんでした。
勝者である羽柴、豊臣のプロパガンダにより、光秀の真意は矮小化され、歴史の彼方に葬られたわけです。
キリシタンの光秀評から見えてくるもの
宣教師であるルイス・フロイスに関する史料から、光秀の本心を想像することができます。
ルイス・フロイスは、信長、そしてある時期までは秀吉のことを高く評価していました。
それは、信長、秀吉がキリシタンとうまく付き合っていこうとしていたからです。
一方で光秀については、徹底的に嫌われており、「悪魔の崇拝者」「人を騙す術にたけている」とまで言われています。
では、キリシタンにとって「悪魔」とは何か、それは異教である仏教です。
「人を騙す術」とは、孫子の兵法であり、すなわち「兵は詭道なり」です。
つまり、光秀は、日本の伝統社会、伝統文化に精通してたからこそ、キリシタンにとっては、敵として見られていたわけです。
罪穢れを自ら引き受ける
ですから、光秀が信長を殺した動機とは、私怨でも、私欲でもなく、日本の国のあり方を守ることだったのではないでしょうか。
江戸時代、歌舞伎の中で、織田信長、豊臣秀吉が描かれることはほとんどありませんでした。
一方で、光秀は、蓑笠をかぶった姿でしばしば登場していたとされます。
蓑笠は罪人の象徴です。
一方で、民俗学者、国文学者の折口信夫が言うところの「蓑笠を着た巨人」すなわち罪穢れを背負い、共同体を追放され、旅をする「スサノオ」すなわち「神の姿」をそこに重ねることもできます。
日の本という共同体のために、絶対権力者である信長殺しの罪を引き受けたからこそ、少なからぬ日本人が心の底で光秀を認めている。
これが、この「本能寺の変」を戦国史上で特別なものにしている理由だと私は考えます。

『異聞・光秀に成り損ねた男たち』(→amazon)
あわせて読みたい関連記事
-

光秀の生涯を描いた唯一の書物『明智軍記』には何が書かれている?
続きを見る
-

明智光秀の生涯|ドラマのような生涯を駆け抜けたのか?謎多き一生を振り返る
続きを見る
-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは
続きを見る
-

光秀最期の11日間|本能寺の変を起こし秀吉に敗れるまで何をしていた?
続きを見る
参考文献
- 窪寺伸浩『異聞・光秀に成り損ねた男たち――本能寺の変 明智の三日天下の真実』(あさ出版, 2025年8月18日, ISBN-13: 978-4866677729)
出版社: あさ出版公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 商品ページ - 窪寺伸浩『明智光秀の原像~史論としての『明智軍記』』(あさ出版, 2019年11月11日, ISBN-13: 978-4866671871)
出版社: あさ出版公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 商品ページ