「ぜんぶ、言っちゃうね」
と、険しい顔をして、まるで『エヴァンゲリオン』碇ゲンドウのようなポーズでこちらを見つめるのは、歴史学者として世間にもよく知られた本郷和人先生の新刊『歴史学者という病』。
学者のくせにフザけた表紙だ――そう眉をひそめる方もいれば、「なにこのオッチャン、面白そう」と感じるエヴァ世代の方もいらっしゃるでしょうか。
本郷先生からしてみれば、いずれのリアクションもしてやったり。
とにかく歴史に関心を持ってもらいたい。日本の歴史学を発展させていきたい。そのためには自身が道化になっても構わない。
常日頃からそう言って憚らない当人が「歴史学者」について語ったものです。
そこには一体何が記されているのか?
東京大学の歴史研究って、どんなことになっているのか?
そんな興味をそそられる、本書をレビューしてみたいと思います。
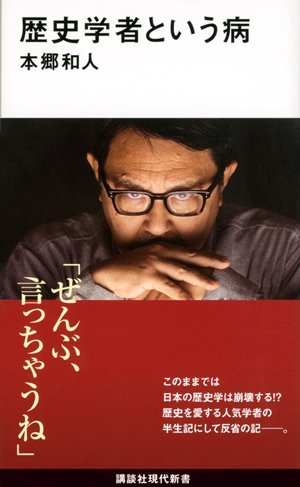
本郷和人著『歴史学者という病』(→amazon)
前半は本郷先生の「自分史」だ
本書は、本郷先生のエッセイ集のような体裁です。
「はじめに」からして、自席でクッキーを探し、コーヒーをすする本郷先生の姿が映し出され、読む者を歴史という学問の世界へ。
といっても、前半部の「歴史」とは、本郷先生の「自分史」です。
ぜんそく持ちで友人もなく、読書好きであった本郷少年。
教育熱心な母の期待を背負い、学校に通う――ここでのエピソード取捨選択が巧みで、歴史という学問は忘れてひきこまれてしまいます。
このあたりで、なぜ本郷先生が売れっ子なのか、わかってきます。
読ませる文章力が高いのです。
とある編集者から「先生の文章はほとんど修正が要らない。ヘタな作家より断然上手い」と聞いたことがありますが、それが単なる称賛でないことがよくわかる一冊で、その世界へ引き込まれてしまう。
一人の少年がいかにして歴史を学ぶようになるのか?
どのように接していくのか?
学校に通い、自我が出てくるとその素養は出てきます。
仏像や、中島敦の漢文、北村透谷に憧れるとなると、やはり何かがちがう。そう思わされます。
中二病だったのかもしれぬ……そう振り返るものの、そんな高尚な中二病にはなかなか罹患しませんて……。
それでも本郷先生が謙虚になっていて、コンプレックスの塊だったとしたら、それは綺羅星のごとき周りの人々のせいだろうと思えます。
様々な人々との対話を通して教養を育んでいくところまで読み進めると、ともかく羨ましいとしか言いようがありません。
才能という玉は、こうして磨かれてゆくのか――と、妙に納得させられます。
「こんなのオレの好きな歴史じゃない!」
そしていよいよ東大入学の話に。
更衣室で一人だけグンゼの白ブリーフだったという悪夢が語られ、笑っていいのかどうしたらいいのか、困惑することになります。
笑い話のようで、想像するとなかなかシャレになってません。
本郷先生も、歴史を学ぶ大学生にありがちな悩みに遭遇しておりました。
「こんなのオレの好きな歴史じゃない!」
大学でわざわざ歴史を専攻するような学生には、十中八九、好きな歴史ものがあります。
大河ドラマ、小説、『信長の野望』、『三国志』など。
我々が日頃から目にするような各種コンテンツですが、かりにも学問として歴史を学ぶのならばフィクションで育んできたものは捨てねばならない。
そこで大きな葛藤が湧いてくる。
一種の洗礼ですね。
そこをどう乗り越えるか? 出会った恩師とは?
歴史をこれから学ぶ若い方も、今一度学び直してみたいという御年配の方も、ぜひとも読んでいただきたいところです。
そしてこの先、本郷先生が実にわかりやすく日本史を学ぶ上での基礎的な考え方を解説してくれます。
楽しんで本郷青年の行く末を読んでいたと思ったら、気づけば歴史を学ぶ基礎がすっと入ってくる。
実に巧みです。
未来の伴侶、その理解力に脱帽
そうして日本史を学ぶうえでの考え方を読み進めていると、未来の伴侶こと小泉恵子さんとの出会いが出てきます。
ホモソーシャルな狭い世界を生きていた本郷先生が、その才能に感心してしまうのです。
まるで朝の連続テレビ小説のような甘ったるさ。しかし、「残念なことに」か、いや、「ご安心ください」か、脱線は終わってしまいます。
そして歴史を見る上で、「物語」と「歴史学」を切り替える考え方の実例が出てきます。
さらには恩師とのやりとり、失敗談、そして卒論の書き方まで出てくるのですから、確かにこれは全部語っていると思えるほど赤裸々です。
それにならい、本書を読む上での注意点でも。
本郷恵子先生が出てくる本書を読み、こんなことを思いませんでしたか?
「女性が日本史を学んでいる。東大には女性差別なんてない、女性が歴史を学べないなんて嘘だ!」
これは正解であり、不正解でもあります。
確かに東大は共学であり、女子学生も女性教員もいます。
ただし、その割合はどうなのか?
世界の他大学と比べてどうなのか?
そこが重要でしょう。
日本中世史には北条政子がいます。
政子が「尼将軍」と呼ばれるほど権威を振るっていたからといって、日本中世に女性差別がなかったのかというと、そんなことはありません。
少数でも目立つ存在がいると、「ほらみろ、差別なんてない」と誤解してしまう。よくある錯誤です。
歴史学には科学的なアプローチも必要であると、本書には記されています。
政子という歴史の物語にいる巨大なヒロインはひとまず忘れて、様々なデータを当たらねば中世の女性像は見えてきません。
本郷恵子先生という巨大な像に惑わされる、そこを慎重に考えたい。
学問における性差別を訴える側に、本書を掲げつつ、本郷恵子先生の名を挙げて封じるとすれば、読み取りが足りないということになりかねません。
歴史学者としての道を歩む
大学院を出て、ダイヤの指輪を買ってプロポーズをして、博士号をとり、研究者としても道を進む本郷先生。
脱線として合間に入る恵子先生とのやりとりも面白く、ここまで書いてよいものかと思えてきます。
この夫婦のやりとりを読んだらファンになってしまうような、そんな素敵な関係。
夫婦としてののろけではなく、研究者として敵わない実例もあげています。
妻ではなく研究者として褒め称える記述からは、とても公正な目線が見えてきます。
本郷先生には、感情はあります。当然です。何かを言われてカチンとくることもあるし、史料を読んでいて不快感を覚えることもある。
歴史教育そのものにも、不満がある。
とはいえ、なぜそうなのか、そこまで冷静に踏み込み、自分自身の感情すら俯瞰するように見つめてゆくのです。
本郷先生は偉大な人物、先学、恩師まで功罪を分析します。
批判と捉えられかねないかもしれない、そう前置きすることもあります。
それでも褒めるだけでなく、自分なりの考えをもってきちんと整理し、批判すべきところはします。
偏見もありません。女性に歴史がわからないという偏見は、恵子先生が一蹴しています。
そして、こうした考え方そのものが大事なのだと思えます。
健全でもある。
タイトルと帯に反して、むしろ本郷先生の根は健全に思えます。
本書にはチラホラと、本郷先生自身が浴びている批判への目配せを感じることもあります。
そうした意見に怒りや冷笑という感情をもって立ち向かうのではなく、自分なりのやり方で回答してゆく。そんな技巧を感じます。
最近はSNSの発達も著しく、歴史分野の批判や議論もそこで行われることがしばしば見受けられます。
しかし、本郷先生の本書読んでいるうちに、それはあやまちではないかと思えてきます。
どうしたってSNSは文字数制限もあるし、自分に届きやすい情報がフィルタリングされるし、投稿しているうちに感情が昂りますから。
確かに「ここまで言ってよいのか?」
読み終えて、特に「おわりに」がなかなか考えさせる内容であった本書。
そこには本郷先生なりの問題意識、歴史学継続へ向けた苦闘のあとがあります。
軽妙な文体や、衝撃的な帯、引き込まれるエピソードの数々。
そうした印象が強く、見誤りそうになるけれども、読後感を整理したいと思います。
本作は、確かにここまで言ってよいのか?と思えます。
それは彼自身の人生体験や失敗談ではなく、歴史学者としてのアプローチ手法、そして問題意識についてそう思えるのです。
彼が今の歴史学の課題をどう捉えているのか。
若手研究者の反発を受け止めつつ、どう向き合っているのか。
その持つ手札を明かしているわけで、定年退官が数年後に迫った今だからこそ書けたのかもしれない。
この本は一気に読めます。
引き込む文章力ゆえに、気がつけば読み終わっているような巧みな仕掛けがあります。
そして本を置いて、あの帯を再度見て、意味がわかった時、もう一度刺激される。そんな構図があります。
すでにAmazonでベストセラーにランクインしている本書に、こんなことを書くのはおこがましいとは思います。
それでも敢えてこう書きます。
本書は一冊でも多く売れて欲しい。
歴史が好きであるならば、ぜひとも読んでいただきたい。
特に歴史を学ぼうと考え始めた学生にこそ、手に取って欲しい。そう言える一冊です。
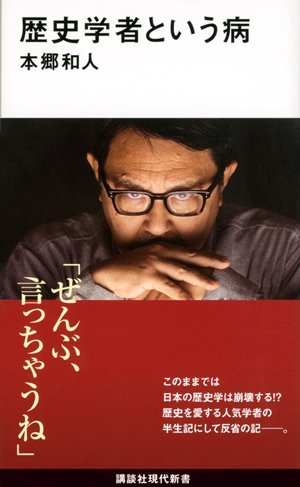
本郷和人著『歴史学者という病』(→amazon)
文:小檜山青
※著者の関連noteはこちらから!(→link)
