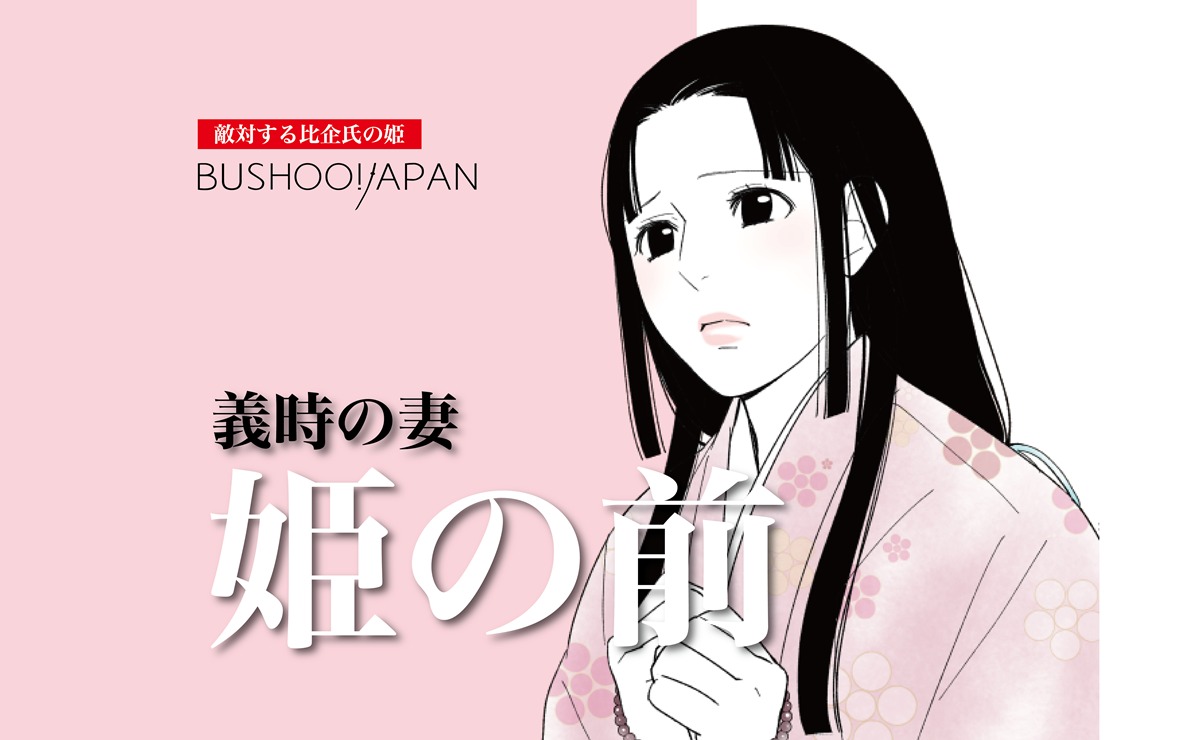「ロミオとジュリエット」と言うには、いささかロマンチック過ぎるけれど、二人の離別シーンには胸が締め付けられる思いだった。
それが大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の北条義時と、その妻・比奈(以下、姫の前で表記)でしょう。
劇中では、義時が八重と死別した後、比企一族から迎えた姫。
いったい史実ではどんな女性だったのか?
北条と比企を繋ぐ――そんな役割からして政略結婚にも思えますが、意外や北条義時からの猛烈アタックで結ばれたという記録が残されています。
では、二人が離別した後の彼女はどうなってしまったのか。
承元元年(1207年)3月29日に亡くなったとされる姫の前の生涯を振り返ってみましょう。
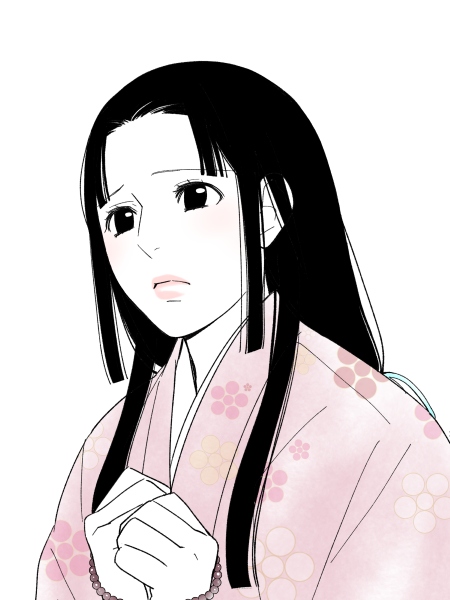
絵・小久ヒロ
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
義時一人目の妻は正体不明
大河ドラマの主人公にもなったのに、婚姻関係がとにかくわかりづらい北条義時。
彼の嫡男・北条泰時が寿永2年(1183年)の生まれですので、少なくともその前年には妻がいたと考えられます。
しかし、この泰時は「庶長子」とされています。
ゆえに、義時が妾を迎え産ませたようにも思えてきますが、ここで『鎌倉殿の13人』を思い出してみましょう。
劇中で義時は八重に向かい、「正式に結婚することを認めてもらう」と語っていました。
江間の領地をもらい、その屋敷に八重を住まわせていた義時。
あの状態では、周囲からも深い仲だと見なされていたことでしょう。
下衆の勘ぐりでもなく、それが当時の感覚であり、正式な夫婦関係であることを認めさせていたという状況がわかる場面です。
そもそも当時の義時は、本人の身分が盤石ではありません。
父・北条時政も跡取りとは決めておらず、江間を領有する「江間小四郎義時」とみなされていました。

江間小四郎義時こと北条義時/国立国会図書館蔵
鎌倉殿である源頼朝の義弟ではある。
しかし御家人としてはせいぜい江間の領主程度。
そんな身分だからこそ、義時の結婚に関する記録は曖昧であり、息子・泰時の誕生も重視されなかったため、母の身分も生まれた性格な日付も判明しておりません。
だからといって、その女性がぞんざいに扱われたことにはなりません。
確かに、義時一人目の妻であり泰時の母は「妾」と表記されることもあります。
これが現代人の考える「妾=愛人」という図式には当てはまらないのです。
当時は、結婚相手に身分差があると、正式な婚礼でも「妾」と記載されることがあり、例えば、義時の妹である阿波局(実衣)もそうでした。
彼女も
「源頼朝の異母弟・阿野全成の妾」
と記載されていることがあります。

頼朝の異母弟・阿野全成/wikipediaより引用
源氏の御曹司に嫁いだ地方小豪族・北条氏の娘という力関係からそうなってしまうんですね。
少し前提の話が長くなってしまいました。
それでは義時の正室・比奈(姫の前)を振り返ってみましょう。
高嶺の花だった姫の前
義時の長男・泰時が生まれ、彼が9歳になっていた建久2年(1191年)。
妻に先立たれて数年が経過していたと推察される義時に、新たな恋が芽生えました。
相手は鎌倉殿の大倉御所につとめる女官・比奈(姫の前)です。
『吾妻鏡』にはこうあります。
「比企の籐内朝宗が息女、当時権威無双の女房なり。殊に御意に相叶う。容顔太だ美麗なり」
「権威無双」とか、「美麗」といった言葉が目に飛び込んできますね。
比奈(姫の前)の特徴を文意からまとめてみましょう。
◆比奈(姫の前)とは?
経歴:比企尼の子である籐内朝宗(比企朝宗や比企藤内朝宗とも)の娘であり、つまりは比企尼の孫娘にあたる
見た目:美女
特徴:他に類を見ないほどパワーを振るっている!※ 源頼朝もお気に入り
こうした女性を表現する言葉はこれでしょう。
高嶺の花――。
凄まじい美人で素敵なだけでなく、ツンケンしていてなかなかデレない。
日本人にとってお馴染みの典型例は小野小町でしょう。
彼女は、深草少将という男性にアプローチされるも「百夜通ってきたら……」と条件を出し、その百日目に少将は大雪に遭って凍死してしまった――。
そんな創作話があり、史実ではありません。
しかしこうした話から、プライドの高い美女が魅力的だという日本人の感性が見えます。
史実の義時は、世間でも評判の美女・比奈(姫の前)に対し、なんと一年以上も恋文を送り続けました。
そして建久3年(1192年)9月、見かねた頼朝が姫の前に命じます。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用
「絶対離縁しないと起請文を書かせるから、あの男と結婚してやってくれ」
かくして義時と姫の前の結婚はまとまったのです。
※続きは【次のページへ】をclick!