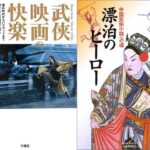もしも歴史上の人物が、後世のフィクション作品を鑑賞したら、どんな反応をするか?
ふと、そんな妄想を抱くことがあります。
例えば織田信長。
『織田信奈の野望』でも手に取ろうものなら、その本屋は瞬時に焼かれ、包囲された出版社は社長が切腹するまで許されないかもしれない。
では、それが『三国志』の登場人物だったら?
劉備が後のフィクション作品を見れば「いや、別にこんなに正義を振りかざしてないんですけど……」と困惑しそうですし、身に覚えのない殺人事件まで捏造された曹操は苦笑しそう。
関羽に至っては、見知らぬ息子や娘、家臣が増えていて、ワイドショーで弁明の機会でも与えたくなります。
そうした妄想を繰り返す中で「諸葛亮 被害者の会」を結成させてみたくなりました。
被害者とは以下の4人。
・周瑜
・司馬懿
・諸葛亮本人
・陳寿
いずれも伝説的軍師の影響により実像を捻じ曲げられた4名であり、今回は彼らの立場に寄り添い、後世の作品を見ていきたいと思います。
4名の史実と、後にフィクションで曲げられた苦悩の考察とでも言えばよいでしょうか。
少々お付き合いいただければ幸いです。

絵・小久ヒロ
entry1 周瑜「そんなに吐血してない……」
では、まず周瑜から。
史実での死因は病死なのに、どういうわけか諸葛亮のせいでストレスを溜め、吐血しまくって死ぬことにされた――典型的な被害者であります。
※『周瑜吐血』というタイトルまであるほど
孫策の盟友で水軍の名将?
うーん、それどころかイメージとしてはすっかり吐血の人ですもんね。
ではなぜそうなったのか?
考えてみましょう。
周瑜が諸葛亮の被害者にされた理由は?
天才軍師を描くには邪魔だったから。それだけのことです。周瑜の気の毒な点は、人格的にはむしろ優れていたところなのです。

曹操が司馬懿の人格に問題があることは、もう振り返る必要もない。それと比較して、あまりにひどいと思えます。
周瑜の罪とは?
「赤壁の戦い」大勝利です。
曹操の野望を阻んだ大勝利であり、実質的なMVPは周瑜。それが諸葛亮をさしおいて目立つな、お前の方が賢いと思われたら困るんだよ! となるわけです。
「やっぱりここで、蜀が曹操をボコボコにしないと盛り上がらないよなぁ。どれどれ……ん、風が吹いたことが勝利の一因って書いてある。よし、風を呼ぶことにしよう!」
無茶しやがって……そんな突っ込みどころ満載ではありますが。
「赤壁の戦い」は盛り上がる!
↓
なのに蜀の影が薄い……
↓
東南の風が勝利の一因
↓
ならば蜀の軍師かつ出てきたばかりの諸葛亮に風を呼ばせよう!
こういう流れです。
昔の作家が嘘つきというだけではなく、エンタメ誇張の王道でもありますので、このような手法もあると納得しておきましょう。
でも……ここで気になってきませんか?
「風を呼ぶにしたって、リアリティが欲しいよなぁ。頭がいいからって、風は呼べないし」
あなたならどうします?
答えはこうでした。
「道術を使えるということにしよう!」
道術とは、道教の秘術のこと。
道教とは、老子を提唱者とする中国の宗教ではありますが、この扱いがフィクションだと無茶苦茶なのです。
1980年代に『霊幻道士』という香港映画がブームになりまして。この「道士」は、道教の修行者のことでした。
霊幻道士はキョンシーを封じ、戦うわけですね。
キョンシー相手に戦うだけでなくて、フィクションの道士は大暴れします。仏僧も自由自在ですが、それ以上かもしれません。
彼らは剣術が得意。
しかもこの剣は武器を通り越して、ハリー・ポッターの杖レベルの使い方ができる。
剣の上に乗って空中浮遊すらあり。『ドラゴンボール』の桃白白が、柱で飛ぶ技の元ネタかと思うほどで、インスピレーションを与えた可能性も考えられます。
武侠小説や映像化作品でも大暴れしておりますので、ご興味があれば是非。
-

北斗の拳やドラゴンボールにも影響大!中国エンタメ「武侠」は日本と深い関係あり
続きを見る
さてここでは、他ならぬ諸葛亮も、こう突っ込みたくなるはずではあります。
「待って、私は別に道術を学んでいません!」
まぁ、学んでいた可能性がゼロだとは言い切れませんが、低いとは思います。
それでも諸葛亮と道術が接近してしまうのは、元代あたりからフィクションを盛りまくった結果。『三国志平話』、雑劇といった元代成立のエンタメにおいて、諸葛亮はこうなりました。
「諸葛亮、赤壁で東南の風を呼ぶ!」
講談師が考えて、定着して、史実に突っ込みたい誰かが何か言おうものなら、ファンからブーイングを浴びる――そういう状況で次第に定着していったのでしょう。
そして、あの伝説の作家もこう考えました。
「ここは、秘伝書も出してみよう!」
明代の羅貫中です。
彼は『三国志演義』をさらにブラッシュアップしようと一生懸命努力をしました。
人物像に深みを加え生合成を持たせ、教養を身につけられるようにする――羅貫中のしたことはあくまで『三国志』エンタメのブラッシュアップであり、ゴーストライターがいただのなんだのしょうもない話は無視してよいことなのです。
昔の文人とは、そういうもの。かの文豪シェイクスピアの作品には、だいたい元ネタが存在します。
それを選び、まとめ、名作としてリライトしたからには、十分功績となりましょう。
一からフィクションを組み立てなければパクリなんて言い出したら、文学史を学ぶ意義が崩壊しかねません。
羅貫中一人がまとめたのかどうか?
そこにも諸説がありますが、それは横にひとまず置きまして、羅貫中は考えました。
「今までのフィクションだと、どうにも道術設定が甘いんだよなあ……よし、ここは気合をいれて、風を呼ぶリアリティを増すか」
はい、突っ込みたくなりますね。
リアリティを増すのであれば、まず風を呼ぶところからなんとかしろ。そう思うのは、あなたが現代人だからです。
こうした作家のリライトにより、諸葛亮のスキルはパワーアップしてゆきました。
・『奇門遁甲天書』を伝授されているんですよ!
→「奇門遁甲」とは、中国の占いです。この占いは諸葛亮をやたらと持ち出してくるわけです。卵が先か、鶏が先か? そういう状況に突っ込みつつあります。
・服装もここでは道士のものにします、ポーズもね!
→コスプレではなくて、ちゃんと形から入っています。あの呼ぶポーズや動きも、道術由来なのです。
現代人からすれば、努力の方向性に疑念を感じるこうした現象も、当時の人にはそうではなかったのです。
そしてここに突っ込みどころも出てきます。
「でも、黄巾党の道術は妖しくて悪いんでしょう? 諸葛亮はいいの?」
はい、それはこの一言で終了。
【主人公補整】です!
道教を守っていた、深く傾倒していたという点では、黄巾党の方が上でしょう。
彼らと思想的になんらかの同意に達した曹操だって、わかっていたかもしれない。彼自身は占いを信じないので、使おうとはしなさそうではありますが。
そういう整合性について『三国志演義』の時点では、大半の読者側も特に疑念を感じなかったのでしょう。
※続きは【次のページへ】をclick!