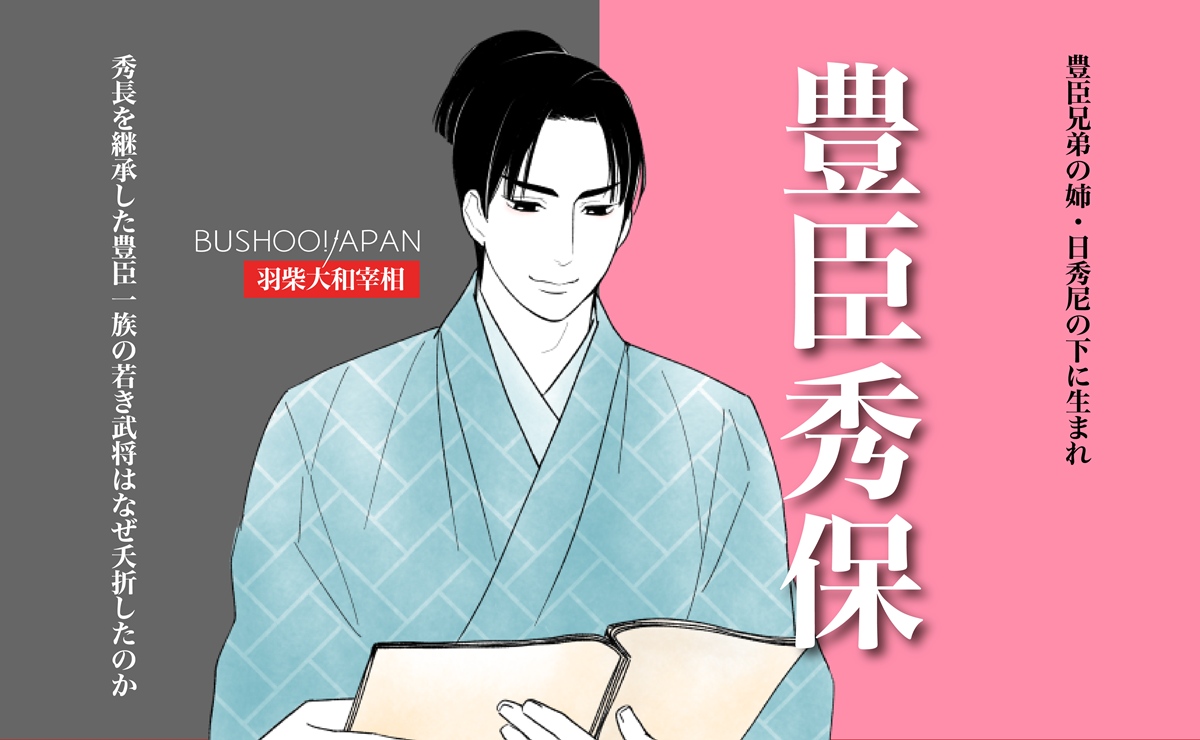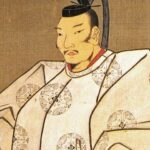2026年大河ドラマ『豊臣兄弟』の主役である秀吉と秀長にとって最大の不幸は、子供や譜代の家臣に恵まれなかったことでしょう。
全く生まれなかったわけじゃない。
配下の者たちだって積極的にスカウトしてきた。
しかし、子沢山で三河武士を抱えていた家康と比べて、そのラインナップはあまりに脆弱であり、しかも数少ない血縁者にしてもなぜだか早逝したり不幸な最期を迎えてしまうのです。
今回はその一人・豊臣秀保(羽柴秀保)の生涯に注目。
豊臣秀長の跡継ぎでもあり、重要なポジションに置かれた次代の武将は、どのような人物だったのか。振り返ってみましょう。
※本記事では「豊臣秀保」表記で統一します
羽柴秀長の養子となった甥
豊臣秀保は天正七年(1579年)、三好吉房と妻・日秀尼(とも)の三男として生まれました。
日秀尼と書くと、なんだか名門武家の女性という感じもしますが、“とも”と記せば豊臣秀吉と豊臣秀長の姉であるとスンナリ入ってくるでしょうか。
彼女が秀保を産んだ当時はすでに46歳だったため「実子ではなく養子なのでは?」とも言われます。
現代でも、なかなかの高齢出産ですしね。もちろん物理的に絶対不可能というわけでもないでしょう。
おそらくそのまま両親の手で育てられていた秀保に運命の転機が訪れたのは天正十六年(1588年)のこと。
叔父であり秀吉の補佐役だった羽柴秀長の養子となりました。

豊臣秀長/wikipediaより引用
もともと秀長にも一男二女がいたのですが、男子が夭折してしまったため、甥を養子に迎えたのです。
同じく天正十六年(1588年)4月の後陽成天皇による聚楽第行幸の時点で「御虎侍従」と呼ばれている人物が秀保と思われます。
年齢的にはまだ幼名だったと考えられますので「御虎」がそうなのでしょう。勇ましい名前ですね。
天正十九年(1591年)1月、秀保は、秀長の娘・通称おみやと結婚し、婿養子となりました。
おみやは当時4~5歳ですので、物心ついたかどうかといった頃合い。
なぜ、そんな段階で結婚に至ったのか?というと、秀長が病みついていたためと思われます。
事実、この結婚の直後に秀長が亡くなり、その領地だった大和・紀伊は秀保へ与えられました。
宗教勢力や在郷国衆たちの影響力が特に強いとされる地域を秀長以外の者に任せて大丈夫なのか……と不安は感じてしまいますね。
羽柴大和宰相
天正十九年(1591年)4月、豊臣秀保は正四位下の位を受けました。
そして9月には参議の官職を得て、ある呼び名を付けられます。
参議の異称である「宰相」をつけ「羽柴大和宰相」です。いささか大仰な雰囲気もありますが、足軽から天下人となった秀吉を支えるためという意味もありますね。
秀吉も、そんな秀保をきちんとバックアップしようと考えていたのでしょう。
秀保の文書に朱印を捺すなどして、弟の跡継ぎとして秀保を庇護しました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
なんせ秀保はこの時点でまだ12歳ですので、実際の統治能力は期待できません。
清華家(公家のランク・摂関家の次にエラいとされた家柄)として認められていた秀長の跡を継いだため、一族内でも秀保は実兄の羽柴秀勝よりも格上とされていました。
ちなみに、豊臣家内での序列では羽柴秀次と徳川家康が同格で二番目であり、その次に秀保が続いています。
秀次も秀吉の甥であり、家康は秀吉の妹婿という扱いのためです。
身内の二番目が秀次、大名の筆頭が家康という見方の方が自然ですね。
豊臣政権の次世代として
豊臣秀保はそのまま順調に出世を重ね、文禄元年(1592年)1月には従三位・権中納言に昇格。
秀長と同じく「大和中納言」と呼ばれるようになります。
文禄の役では一万人を率いて肥前名護屋に在陣し、普請役を担いました。

ドローンで空撮した名護屋城の本丸と遊撃丸
とはいえ、この時点でもまだ13歳なので渡海はしていませんし、本人が能力を発揮できることはそう多くなかったでしょう。
代理として渡海したのは、秀長の頃から仕えていた藤堂高虎でした。
翌文禄二年(1593年)8月になると、お拾(後の豊臣秀頼)が誕生しますが、秀保にはそこまで大きな影響はなかったと思われます。

豊臣秀頼/wikipediaより引用
秀吉の養子となっていた兄の秀次が、豊臣秀頼の存在について気が気でなかったのに対し、秀保は秀長の養子=親族衆という位置ですので、直接的な不安は抱かなかったはず。
むしろ秀吉も、本家だけで豊臣が存続できると考えていなければ、弟・秀長の家だって重要になってきます。
そもそも身内や家臣団が少ないわけですから、秀頼を脅かすようなことさえなければ、秀保も大事な甥だったわけですね。
早すぎる病死
羽柴大納言家も並行して存続していれば、豊臣本家がいざというとき、親族で政権の後継者を輩出できる。
そんな目論みは、文禄四年(1595年)春、突如崩れ去ります。
この年の3月、秀吉が高野山に参詣した際、同行した秀次が大和郡山城に豊臣秀保を見舞っています。
不幸にも疱瘡にかかったようです。
こうなると当時の医療では為す術なく、後は本人の体力次第――すると4月10日頃から容態が悪化し、同月16日に病死してしまいました。
享年17。
あまりに早すぎる死です。
だからでしょうか、次のような話が残されています。
「秀保は小姓に川へ飛び込めと命じ、その小姓の巻き添えとなって十津川で水死した」
「殺生禁止の川で魚を取って食べたので神の怒りに触れたためだ」
こちらの描写は、秀保の死後180年近く経った江戸時代中期に書かれた創作であろうと思われ、原文では名前が”秀俊”となっています。
江戸時代の創作物には「名前を少しもじってフィクションということにする(でも実際はわかるよね?)」というパターンがよくありますので、おそらく秀保を指す目的でしょう。
「”殺生関白”こと豊臣秀次の実弟ならば、これぐらいのことはやったのだろう。早死したのがその証拠だ」
そんな風に考えた人が創作したのかもしれません。
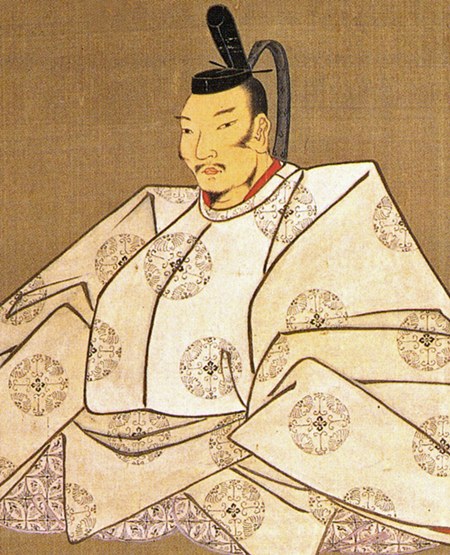
殺生関白と呼ばれる豊臣秀次/wikipediaより引用
江戸時代は徳川家に関する著作がタブーであり、そのぶん「豊臣家やその家臣に対してはどんなに悪く書いてもいい」みたいな風潮もあり、その辺りを差し引いて考えなければなりませんね。
なんせ享年17での死でしたので、秀保には子供もおらず、大和大納言家は無嗣断絶となりました。
秀長も草葉の陰でさぞ悲しんだことでしょう。
もっとも、現実的に影響が一番大きかったのは、配下にいた藤堂高虎ですね。
秀長に続き秀保が亡くなり高虎は出家
七度主君を変えたことで知られる藤堂高虎は、もともと豊臣秀長に長く仕えていました。
そして相次ぐ主君の死を悼み、一時は高野山で出家しています。
秀吉に呼び戻されて還俗しておりますが、何度も主君が変わったのは単純に高虎の性格が気難しいとか薄情だからではないでしょう。

藤堂高虎/wikipediaより引用
それよりも次々に亡くなっていった秀吉の血縁者のほうが気になりませんか?
本記事の豊臣秀保だけでなく、秀吉の養子だった御次秀勝(羽柴秀勝)も18歳で病死し、豊臣秀次も結局は切腹している。
秀次の死などは、たしかに猜疑心の強い秀吉の性格が影響しているとは思います。
しかし、後継者候補である血縁者が連続して途絶えてしまう惨状を見ていると、何者かが超長期計画で豊臣家の系譜を根絶していたのでは?と勘ぐりたくなるほどです。
まぁ、結果から見た妄想ですね、すみません。
結局、一代で足軽(農民)から成り上がった者に長期政権の継続は難しい、そんな非情な現実があるのでしょう。
★
冒頭で触れた通り、豊臣秀保については「ともの実子なのか、養子なのか」と言った点も含めてまだ謎が多い状態です。
大河ドラマに取り上げられると注目が集まり、新史料が発見されやすくなりますので、今後の新発見を期待したいですね。
早逝するため地味な扱いにされがちですが、2026年のドラマ用に名前を覚えておくと面白そうです。
あわせて読みたい関連記事
-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】
続きを見る
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
-

藤堂高虎の生涯|豊臣兄弟の秀長や家康にも厚く信頼された戦国の転職王
続きを見る
-

豊臣秀次の生涯|殺生関白と呼ばれた秀吉の甥はなぜ自害に追い込まれたか
続きを見る
参考文献
- 黒田基樹『羽柴を名乗った人々 (角川選書 578)』(KADOKAWA, 2016年11月, ISBN-13: 978-4047035997)
出版社: KADOKAWA 公式書籍情報 |
Amazon: 商品ページ - 菊地浩之『豊臣家臣団の系図 (角川新書 K-290)』(KADOKAWA, 2019年11月, ISBN-13: 978-4040823256)
出版社: KADOKAWA 公式書籍情報(増補新版案内) |
Amazon: 商品ページ - 国史大辞典(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979–1997年刊)
出版社: 吉川弘文館(ジャパンナレッジ紹介)