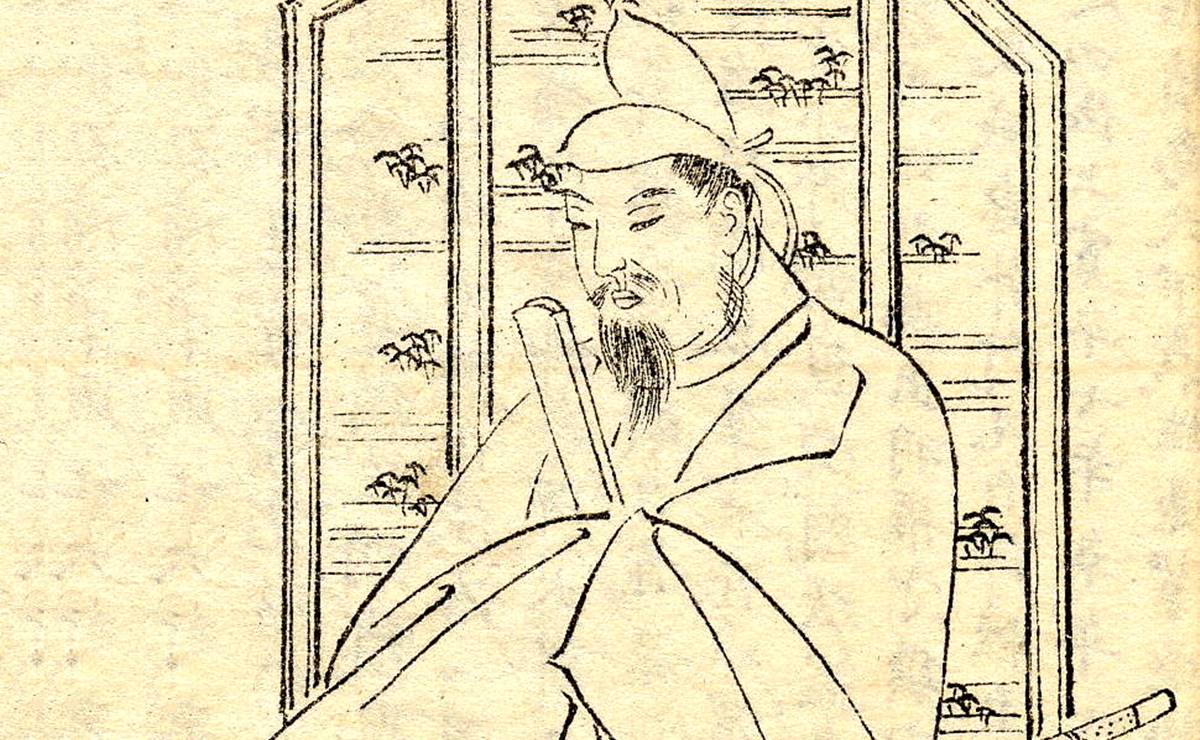延喜三年(903年)2月25日は、菅原道真が亡くなった日です。
天才として今なお全国に名を知られる平安時代の学者であり政治家の道真公。
彼がなぜ学問の神様と呼ばれるのか、ご存知でしょうか?
今回は道真の命日にちなみ、彼が「文章博士」となって出世のキッカケを得て、そこから讒言→太宰府への左遷を経て、人物神となるまでの経緯を確認してみましょう。
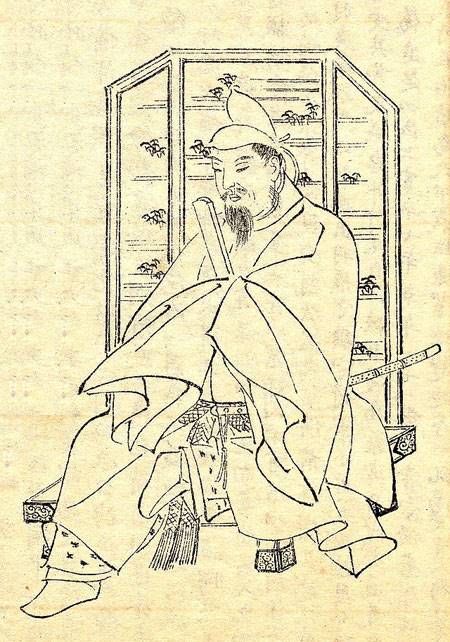
菅原道真像(菊池容斎)/wikipediaより引用
菅原道真は大学教授で文筆家&天皇の先生
文章博士の読みは「ぶんしょうはくせ」ではなく「もんじょうはかせ」です。
仕事内容は、大学の教授と文筆家のみならず、天皇の先生を兼任するというスペシャルハードなものでした。
もっとも、これには日本人の気質が大きく関係していて、単に全部押し付けられたとかそういうわけではありません。
日本の学校制度は中国の歴代王朝を基本にしており、中国人と日本人で好む学問の分野が違ったため、こういう収まり方になったのです。
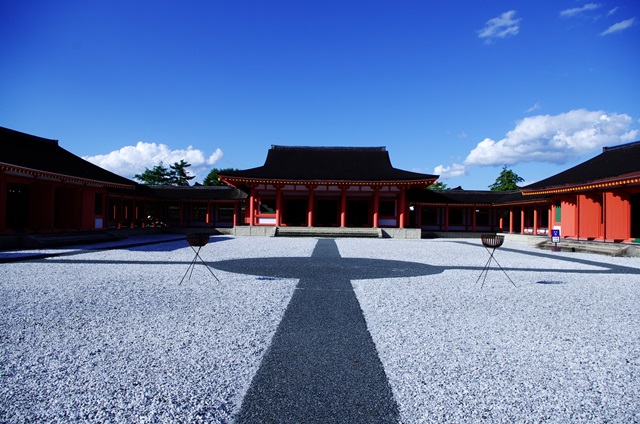
具体的に申しますと、中国では儒学が好まれました。
一方、日本では文学や史学に関心を持つ人が多かったので、担当する文章博士の権威も大きくなり、そこから発展して天皇の先生をやったり、貴族からの依頼で漢詩や文章を書くようになっていったのです。
現代でも紙の本や電子書籍問わず「日本人は読書好きだ」って言われることがありますから、民族性なんですかね。
まぁ、全国民に対し統計取ってみたら、諸国と変わらん……なんてことかもしれませんが。
道真は生誕地も不明なほど身分が低かったが
やがて文章博士は身分も引き上げられます。
従五位下という貴族と同等の位を与えられるようになりました。
同格には少納言や少輔など、貴族や戦国武将の官位でよく耳にするものが並んでいます。 そのくらい重要視されるようになったということです。
時は藤原氏が隆盛を極めんとしていた頃。
下級貴族たちにとって、藤原氏のコネ以外で出世するには、文章博士になるのがもっとも手っ取り早く確実な手段といっても過言ではありませんでした。
そこで下級貴族たちは、息子をこぞって大学寮(国立の官僚候補学校)に通わせるようになります。

道真も同様に大学寮へ入っています。
ただし、道真の生誕地はわかっていません。そのくらい元の身分が低かったんですね。
小さい頃から詩歌の才があったといわれていますので、少なくとも読み書きなどの教育が受けられるギリギリの家だったという可能性が高いです。
無名の青年が頭脳を武器にわずか8年で大出世!
大学寮は中国の科挙と同じように、試験にさえ受かれば身分の低い者でも入学できました。
ごくごく僅かですが、名字を持たない身分の人が入学した記録もあります。
道真もこのシステムのおかげで頭角を現し、18歳で入学して23歳の時には文章得業生(もんじょうとくごうしょう・文章博士の候補者)に選ばれています。
さらに26歳のときには、文章博士の行う「方略試(ほうりゃくし)」という試験にも合格しました。
本当はここで位階が3つ上がるのですが、それでは文章博士を超えてしまうというので1つに留められたほどです。
無名の青年が頭脳を武器に、わずか8年で大出世!
なかなかドラマチックな展開ですよね。
そして元慶元年に文章博士になった後も讃岐守となって領地をもらったり、宇多天皇と藤原氏とのゴタゴタを片付けるなど活躍しました。

宇多天皇/wikipediaより引用
宇多天皇からも厚く信頼され、その息子・醍醐天皇の代には右大臣にまで上り詰めています。
隆盛振りは凄まじく、自分の娘を宇多天皇の息子・斉世親王(ときよしんのう)に嫁がせるほどでした。
しかし、これがやっかみを買う原因になってしまいます。その相手とは、もちろん……。
※続きは【次のページへ】をclick!