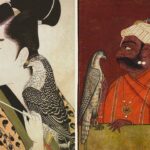今回で『信長公記』首巻が終わります。
前回までに斎藤龍興を美濃から追い出し、岐阜と改め【天下布武】を用い始めた織田信長。
上記のことは永禄十年(1567年)までの出来事であり、事実上、首巻の内容はそこで終わりです。
しかし、首巻の最後に「翌年のこと」として、「足利義昭を奉じての上洛」の件が記されています。
信長と義昭は永禄十一年(1568年)に上洛をしており、その詳細については、首巻に続く「巻一」に描かれているのですが、今回はとりあえず上洛のダイジェスト版として見ておきましょう。
義昭「信長を頼りたい」
永禄十一年(1568年)夏のこと。
それまで近江の六角義賢や、越前の朝倉義景を頼っていた足利義昭が「信長を頼りたい」という旨の要望を申し入れてきました。
取り持ったのが細川藤孝(細川幽斎)と和田惟政です。
信長はすぐに越前へ迎えの使者を送り、それから百日もしないうちに入京を果たします。
そのおかげで、義昭は正式な征夷大将軍になることができました…………と、これでおしまい。いわゆる「上洛戦」やその間の出来事はほぼすべて端折られています。
首巻の最後に付されたダイジェスト版なので、淡白なのでしょう。
しかし、これで終わりというのはあまりに消化不良ですので、後に内容が被ることは踏まえた上で、信長と義昭の上洛を少し詳しく見ておきましょう。
美濃攻略が済み実現可能に
実は義昭は、しばらく前から信長に書面での上洛協力を依頼してきていました。
しかし、その頃の信長はまだ美濃を攻略しきれておらず、余裕もないためハッキリした返事ができず、先延ばしになっていた……という経緯があります。
美濃攻略は、そういう意味でも必要不可欠だったわけですね。
上洛に関するひとつひとつのことについて詳しく書くと、あまりにも膨大な量になってしまうので、ここでは入京までの信長に関わる出来事のうち、今後にも大きく影響してくる部分を簡単にまとめておくにとどめましょう。
義昭を奉じての上洛から将軍就任までの流れ
◆永禄十年(1567年)9月~永禄十一年(1568年)3月ごろ
→お市の方が浅井長政へ輿入れ
◆永禄十一年(1568年)7月25日
→足利義昭が岐阜に到着し、信長と会見
◆永禄十一年(1568年)9月7日
→義昭を擁して上洛開始
◆永禄十一年(1568年)9月12日
→観音寺城の戦い(=箕作城の戦い)※vs近江六角氏
◆永禄十一年(1568年)9月26日
→信長軍が入京し東寺を宿所とする
◆永禄十一年(1568年)10月18日
→足利義昭に将軍宣下
美濃を制して、割とスグに妹のお市を浅井長政に嫁がせておりますね。
美濃~近江間の移動はクリアになったのですが、問題はその先、南近江の六角でした。
京都での乱暴狼藉を取り締まる
六角氏については、戦をせずに済むよう数日間かけて交渉したり、途中で妹婿・浅井長政と連携して事に当たるなど、今日あまり知られない一面も、この中でみられました。
おそらく京都市民の「武士が来る=町を焼かれる=一刻も早く逃げなくては!」といった連想からくる混乱を最低限にするため、道中でも手荒なことは控えようとしたのでしょう。
結局、六角氏が頑として応じなかったために、戦になってしまいました。
これが【観音寺城の戦い(=箕作城の戦い)】と呼ばれ、数万の織田軍が一気呵成に攻め込み、わずか一日で陥落させています。
そしていざ京都へ。
ときの帝である正親町天皇から「兵が京での乱暴狼藉を働かないよう、厳しく取り締まるように」という命令も届いており、信長はこれを忠実に守りました。
しかもこのときだけでなく、後々まで兵や京都市内の不届き者については、厳重に処罰しています。
信長が為政者としての視点と行動力を持っていた証左といえるでしょう。
「あいつはきっといい武将になる」と娘を嫁がせ
他に、このあたりの有名なエピソードとしては蒲生氏郷の話がありますね。
観音寺城の戦いの後、六角家臣だった蒲生氏から人質として信長へ差し出された蒲生氏郷(当時は元服前・鶴千代)。
「こいつの目つきはただ者ではない。俺の娘を嫁にやろう」
と言って、氏郷が元服と初陣を済ませた後、次女を嫁入りさせた。
そんな話があります。
氏郷も信長に懸命に仕えようとしていたらしく、岐阜城でよく行われていた深夜の軍談を毎回真剣に聞いていたとか。
人質という立場だから……という理由もあったでしょうが、目をかけた信長と、期待に応えようとする氏郷の微笑ましい光景が脳裏に浮かびますね。
稲葉一鉄なども、その光景を見て「あいつはきっといい武将になる」と褒めていたそうです。

蒲生氏郷/wikipediaより引用
当時、信長は既に34歳になっていました。
「人生五十年」の折り返しを過ぎて、残りは1/3といったところ。
信長公記では、信長の妻子のことがほとんど書かれていないので忘れがちですが、上の息子三人(織田信忠・織田信雄・織田信孝)があと2~3年で元服という頃合いでもありました。
氏郷は、ちょうどこの三人と同世代です。
信長はただ単に氏郷の目つきを気に入っただけではなく、「きっと息子の役に立つ」と見込んで、娘婿にまでしたのでしょう。
さほど知名度は高くありませんが、『信長公記』首巻の最後には、また別の逸話が添えられています。
いずれ天下を取ったときに頂戴します
以前、丹波長谷の城主・赤沢加賀守という人物が、関東へ自ら足を運び、良い鷹を二羽手に入れました。
その帰り、尾張へ立ち寄り、信長へ言いました。
「どちらかお好きな方を差し上げましょう」
信長は、こう答えます。
「お気持ちはありがたいが、いずれ天下を取ったときに頂戴します」
赤沢はこの話を京へ帰ってから人々に話し、皆で笑っていたとか。
「尾張の田舎者が天下を取るだなんて、できるわけがないだろwww」
しかし、それから十年もしないうちに、信長は本当に京へやってきたので、皆驚いた……という話です。
結局この話の鷹がどうなったのか書かれておりません。
もう少し後の時期になると、信長は多くの武将や大名から鷹を献上されていますので、その中に加賀守の鷹がいたかもしれませんね。
あわせて読みたい関連記事
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

信長も家康も世界も熱中した鷹狩の歴史~日本最古の記録は仁徳天皇時代だった
続きを見る
-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請
続きを見る
参考文献
- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)
書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)
出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)
書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)
出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)
出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ