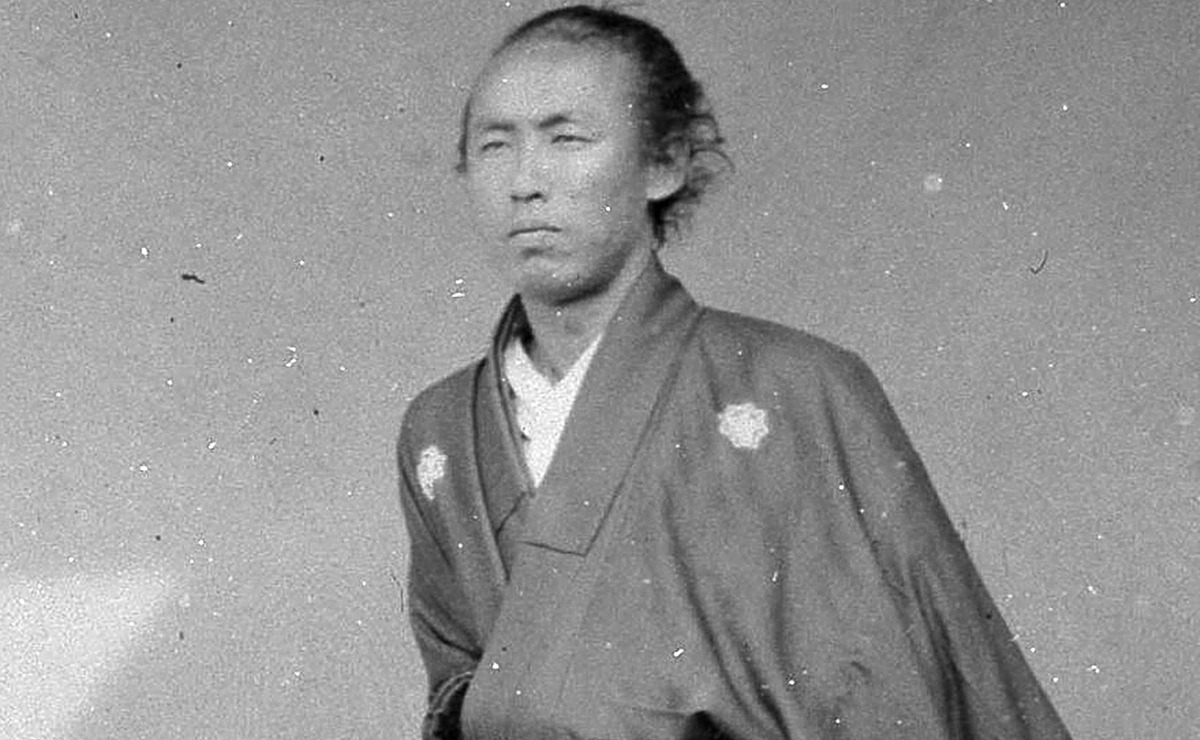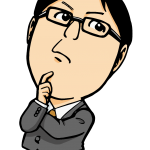日本中世史の本郷和人・東大史料編纂所教授が歴史ニュースに注目する「歴史ニュースキュレーション」。
今週のメインテーマは「坂本龍馬が暗殺された時に携えていた『陸奥守吉行(むつのかみよしゆき)』はどんな刀?」です!
「龍馬が暗殺時に携帯の刀」は本物だった
◆「龍馬が暗殺時に携帯の刀」は本物だった「『反り』がないのは、おかしい」の謎が解けた/j-cast 2016/5/11(→link)
姫「このニュース、いろいろなところで取り上げられているわね。坂本龍馬の人気はやはりすごいのね」
本郷「司馬遼太郎は倒幕側では坂本龍馬を、幕府側では土方歳三を描いて、それぞれ歴史上の大スターにした。その力量には頭が下がるけれども、龍馬は会社を経営しているおじさんなんかにまで人気があるから、全体としては龍馬>歳三、という感じなのかな」
姫「そうね。歳サマのファンは女子が中心かもね。そういうあなたはどうなの?」
本郷「そりゃあ、江戸っ子のぼくは佐幕だからね。土方ファンですよ。『萌えよ剣』じゃなくて、『燃えよ剣』は司馬作品の中でも一番の愛読書だった。その一方で、実は『竜馬がゆく』は読んでないんだ。最終巻だけは読んだけど」
姫「えーっ。じゃあ、土佐勤王党のあんなことやそんなこと、知らないの?」
本郷「いや、子母沢寛の『勝海舟』で岡田以蔵ほかの物語を知ったり、小山ゆう先生のマンガ『お~い!竜馬』でいろいろ知ったんだけれどね」
姫「ふーん。テレビとかで何か言うときは気をつけなさい。ニワカあつかいされるわよ」
本郷「はいはい。気をつけます。はい、それで今回は、竜馬が暗殺されたときに持っていたという陸奥守吉行が京都国立博物館にあったのだけれど、調べてみたら間違いなく本物だった、というお話だね」
姫「この刀、反りがないのよね。だからニセモノ説があったみたい。でも、なぜ反りがないかがきちんと説明できたので、良かった、良かった、というわけね。陸奥守吉行って、どんな刀工なの?」
本郷「生まれが1650年で1710年没。出身は陸奥国中村とも摂津国住吉ともいうらしい。本名は森下平助。山内家に召し抱えられて土佐に移住したことから土佐吉行とも呼ばれるようだよ。この刀を、高知の裕福な商家の息子である竜馬さんがもってたのは、まあ、納得のいく話だね」
姫「あのさあ、この刀工の刀って、いくらくらいするものか知ってる? お金の話をするのはちょっと下品なんだけれど、知りたくなるわよね」
本郷「ああ、平均的な値段なら、教えてくれるサイトがあるよ。ええとね、陸奥守吉行は630万円とあるよ。土方歳三の11代目兼定は600万円だから、良い勝負だね」
姫「へー。うーん。高いのか安いのかよく分からないけれど。あ、近藤局長の虎徹とかだとどうなるの? 虎徹はいってみれば新しい刀の中の大将格なんでしょ?」
本郷「うん。虎徹は高いだろうな……、っと3500万だ。すごいね。ケタが違う。」
姫「なるほどねー。でも、この吉行って、竜馬さんが脱藩するとき、お姉さんがこっそり持たせてくれたのよね」
本郷「お姉さんっていうと、あの大柄だった乙女さん?」
姫「そうじゃなくて、その上のお栄さんだったっけ。結婚に失敗して、実家に帰っていたのよ。それで、竜馬さんの理解者で、彼が脱藩するときに家の家宝のような刀を持たせるの。それで、そのあとに、責めを負って自害するのよ、たしか」
本郷「ああ、聞いたことがあるよ。坂本家のお墓を昭和40年代に改修したときに、地下深くから髪の毛と遺骨が発見された。これが自害して密葬された栄さんのものだということになったんだよね」
姫「そうそう。心をうつ、悲しいお話よね。『竜馬がゆく』にも出てくるわ」
本郷「『お~い!竜馬』にもね。でもそれ、間違いらしいよ」
姫「え? そうなの?」
本郷「うん。 昭和63年に栄のものと見られる別の墓石が、嫁ぎ先である柴田家の墓石と隣り合わせに発見されたんだ。墓石には『柴田作衛門 妻』『坂本八平 女』と2行で刻まれているので、まず間違いない。それによると、栄さんは柴田家に嫁いで程なく病死したらしい。だから竜馬に刀を渡すことはできないんだね」
姫「あら。じゃあ、だれが竜馬に吉行を渡したの?」
本郷「今は乙女さん、ということになっているようだね。それで、脱藩の時に持って行った刀は吉行ではない。肥前忠広なんだ。ちなみに忠広を銘とする刀工は何人もいるから、参考価格はよく分かりません」、
姫「それじゃあ、竜馬さんはいつ吉行を?」
本郷「後になってお兄さんの坂本権平さんに『吉行を下さい』って頼んだみたい。それでお兄さんはこの刀を西郷隆盛に託し、西郷から竜馬さんの手に渡ったようだよ」
姫「なるほどねー。数奇な運命をたどった刀なのねー」
<神皇正統記>只見で中世写本見つかる
◆<神皇正統記>只見で中世写本見つかる/河北新報 5月13日(→link)
姫「『神皇正統記』って、北畠親房が書いた歴史書よね。あなた、親房、好きなのよね。わりと詳しいんじゃない?」
本郷「親房の生涯についてはオリジナルな話ができる自信があるけれど、自分の生き死にのかかった、参考書とかが何もないところであれだけの書物を書いたんだから、すごい人だよね、ってくらいで止めておこう」
姫「親房が15年ぶりくらいに兵を率いて京都の地を踏んだとき、『京洛よ、私は帰ってきた』って言わせたでしょ。あれは笑ったわよ。ガトー少佐じゃないんだから」
本郷「親房って、ぼくの中ではガトーなんだよ。まあいいじゃないか……。それでね、『神皇正統記』だけど、原本はない。写しの中で一番古いのはどこにあるか知ってる?」
姫「たしか、白山神社じゃなかった? 「いま親房」たらんとした平泉澄先生が保管されていて、できすぎ、って思ったことがあるから」
本郷「そう、そのとおり。平泉澄については、ここで述べだすと長くなるので、調べてくださーい。東大の先生だったんだけど、太平洋戦争の敗戦によって公職を追放され、郷里の白山神社に帰ったんだ。しょげていたのか、というと全然そうではなくて、親房卿のことを思えば、何のこれしき、と意気軒昂だったそうだね」
姫「たしか白山神社の『神皇正統記』は重要文化財に指定されているのよね」
本郷「そうだね。あと古い写本で有名なのは、水戸市(かつては常澄村)の六地蔵寺のものかな。塙保己一が『群書類従』を編纂するときには、この六地蔵寺本を底本として採用したんだね」
姫「六地蔵寺、って、あまり聞かないけれど、大きなお寺なの?」
本郷「うん。大永年間くらいに作られた本堂があってね。ぼくは20代の頃、このお堂の修理を見学させていただいたんだ。そしたら、屋根裏や柱にいくつか「かたみ、かたみ」って書いてあって、なんだこれ? って思ったんだよ」
姫「それは、何だか、分かったの?」
本郷「最近知ったんだけれど、当時の人がお寺に書いた落書きらしいんだ。『書きおくも形見となれや筆の跡 われはいずくの土となるとも』という歌が有名でね、それでお寺や神社に参詣した人が、「かたみ、かたみ」と落書きした。あ、これはマネしちゃダメですよ。詳しくは三上喜孝くんの『落書きに歴史を読む』(吉川弘文館)を読んで下さい。とても良い本です」
姫「今回発見された写本は、六地蔵寺本のあとくらいに位置するわけね。とても貴重な発見ね。良いニュースが聞けてうれしいわ」