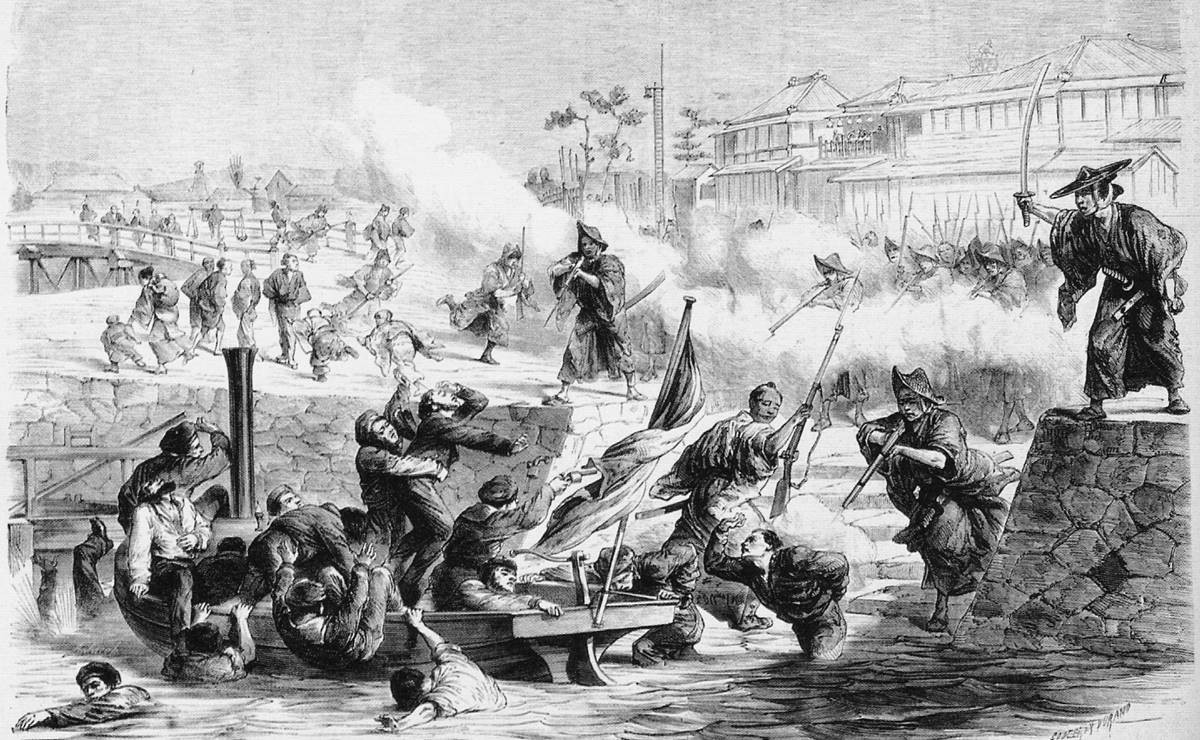慶応四年(1868年)2月15日は、堺事件が起きた日です。
堺で起きたから堺事件……とはあまりにシンプルすぎて概要が全く伝わりませんが、平たくいえば「生麦事件や神戸事件の堺版」みたいな感じです。
まだまだ西洋諸国と外交慣れしていない日本で起きた、国家間のトラブルということになりますね。
何となくイメージできたところで、詳しいことを見ていきましょう。
堺の港に停泊していたフランス海軍デュプレクス
慶応四年(1868年)2月15日、堺港にはフランス海軍の「デュプレクス」という船がやってきていました。
日本に駐在していたフランス副領事と、中国・日本方面担当の司令官を迎えるためです。
遡ることこれより2ヶ月ほど前、大坂ではとある事故が起きていました。
天保山沖にやってきていたアメリカ海軍のボートが転覆し、乗っていた提督(海軍のお偉いさん)を含む数名が溺死してしまったのです。
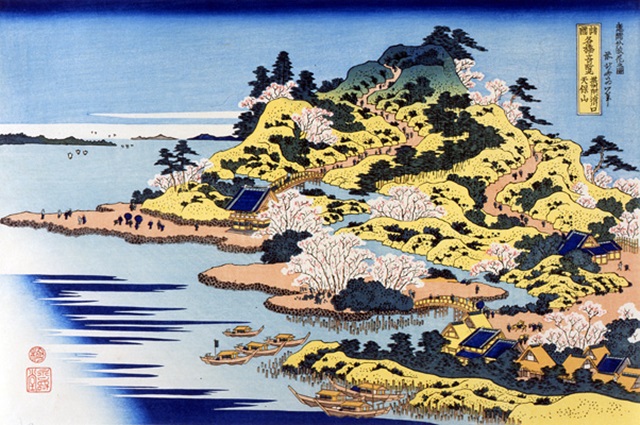
葛飾北斎の描いた天保山(川ざらえで出来た山)/wikipediaより引用
そのため、フランス海軍は「アメリカの二の舞いにならないよう、どこが深くてどこが浅いのか、波の様子はどうか、調べておこう」としました。
平たくいえば、港の測量です。
測量をするのに、一般の水兵の力はあまり要りません。
暇になってしまった彼らは、大坂の町に繰り出して遊ぶことにしました。
言葉も通じないのに、恐るべき行動力というか。かなりテンションが上ってしまっていたらしく、フランス水兵たちは日が暮れても船に帰ろうとしません。
ただでさえ外国人慣れしていない日本人が、警戒し始めるのも仕方のないことです。
住民たちは当時堺の警備を担当していた土佐藩士の警備隊に「偉人たちがうろついていて怖いので、何とかしてください」と訴えました。
仏国公使「何もしていないのにいきなり発砲された」
通報を受けた警備隊は、フランス水兵たちに接触し、船に帰るよう促します。
しかし、当然のことながら言葉が通じません。
仕方がないので捕縛して連れて行こうとしました。
事の経緯が飲み込めないフランス水兵は、これまた当然のごとく抵抗。
そこで土佐藩の隊旗を奪うという無礼に出てしまいました。
言葉が通じないとはいえ、軍や国の旗を奪うというのは、相当失礼な行為です。
しかもそれだけではなく、フランス水兵たちが逃げようとしたため、警備隊はやむなく発砲しました。
そして起こった銃撃戦の結果、フランス水兵に多数の死傷者が出てしまいます。
海に突き落とされて、溺死した者もいたようです。
イギリス公使が間に入って取りまとめようと
非はもちろんフランス水兵にもありました。
しかし、仏国公使レオン・ロッシュたちは「何もしていないのにいきなり発砲された」と受け取り、日本側へ下手人の処罰その他の処分を求めます。

レオン・ロッシュ/wikipediaより引用
フランス水兵の葬儀を神戸居留地で執り行った際、ロッシュは弔辞としてこんな風に言っておりました。
「私は諸君の死の報復をフランスと皇帝の名において誓う」
どうやら静かに怒りを燃やしていたようですね。
一方、日本側の当事者の上司である土佐藩主・山内容堂は、京でこの事件の知らせを受けました。
たまたま京の土佐藩邸には、イギリス公使館職員アルジャーノン・ミットフォードが滞在しており、「この件に関わった藩士はきちんと処罰する、とフランス公使に伝えてほしい」と頼んでいます。
ミットフォードはただちにロッシュに連絡を取り、日仏間で解決のために動き始めます。
そしてロッシュは在坂中の各国大使と話し合った上で、下手人斬刑・陳謝・賠償などを求める抗議書を提出しました。
※続きは【次のページへ】をclick!