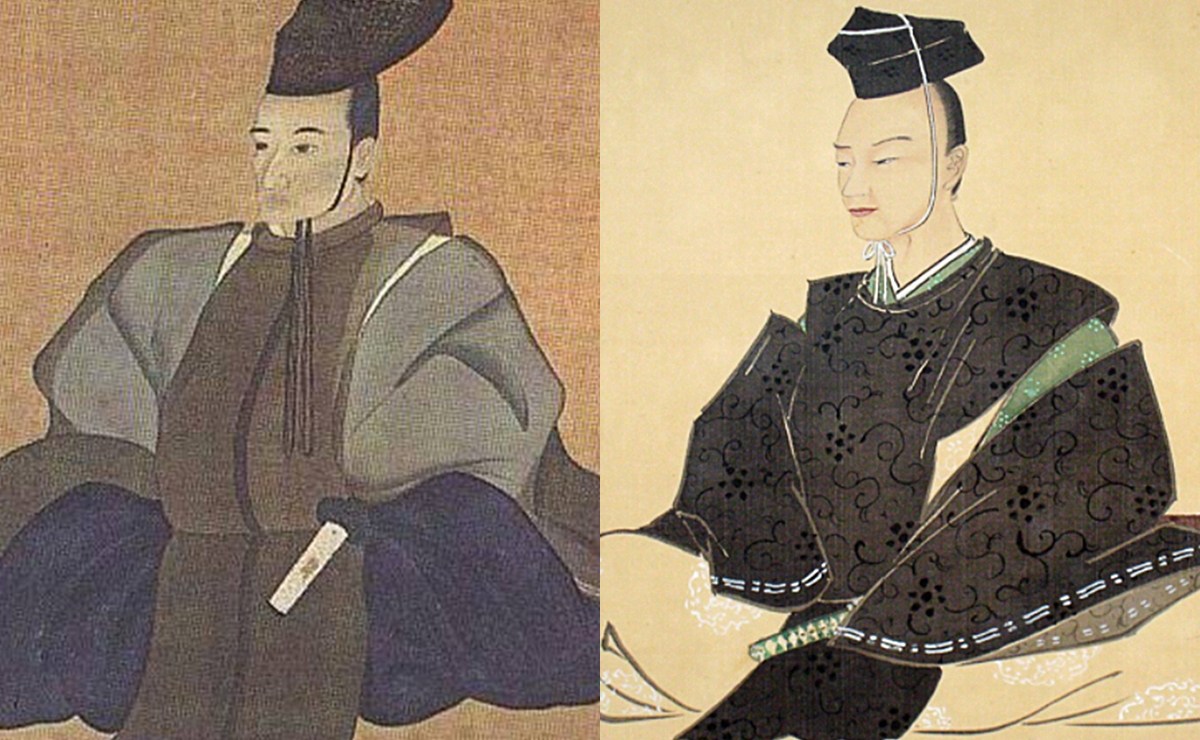こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【天明の打ちこわし】
をクリックお願いします。
米屋が価格を釣り上げ
こうなると、江戸をはじめとした都市部に影響が及ぶのも時間の問題。
徐々に入ってくる米が少なくなり、やがて米屋が出し惜しんで値を釣り上げ、私腹を肥やそうと企む始末です。人の心ないんか。
実際、米価はどれぐらい上がったのか?
打ちこわしが起きる2年前の時点で、米一升=百文くらいでした。
それが2倍の米一升=二百文になり、さらに釣り上がっていたというのですから、実際は3~4倍ってところでしょうか。
現在よりも米への依存度がはるかに高い江戸時代ですから、民衆が怒るのも当然ですね。

ちなみに大坂では、半世紀ほど後に起きる【天保の大飢饉】の際、役人が
「江戸に米を送らないといけないんで~」
と杓子定規な対応しかしていませんから、天明の大飢饉のときも一般庶民には米がいきわたりにくい状態だったでしょう。
一般人が米を得るため、実力行使に出るのも無理はない状況なんですよね。
そんなわけで、まず大坂で打ちこわしが始まりました。
噂は全国各地に広まり、各地方で頻発。
江戸では天明七年(1787年)5月下旬、数日間にわたって「南は品川、北は千住、四里四方の内」という広範囲で打ちこわしが起きています。
これら全てをひっくるめて【天明の打ちこわし】と呼んでいます。
勘定吟味役の伊奈忠尊が格安で販売
江戸の打ちこわしは特に規模が大きくなりました。
約5,000人もの民衆が980店の米屋を襲い、町奉行(警察官みたいな役職の武士)の手にも負えず、自然に鎮まるのを待つより他になかったとか。
山火事みたいな扱いですね……。
このとき、勘定吟味役首座を務めていた伊奈忠尊が各地から米を買い集めて、格安で市民へ売ったことにより、ようやく収まったのだとされています。
勘定吟味役というのは幕府の領地から収められる年貢や金銀の改鋳などを担当する役人で、忠尊はその責任者でした。
実際に米が手に入ったことも民衆の怒りが和らいだ理由でしょうが、何よりも
「お役人が刀を振り回さずに助けてくれた」
という点が、江戸市民を安心させたのでしょう。
この辺は、フランス革命と比較するとなかなか興味深いところがあります。
ほぼ同じ時代、フランスも冷害の被害を受けており、食料の値段が著しく上がっていました。
そして1789年にあのバスティーユ襲撃が起こるのですが、革命派は当初国王一家の命まで奪うつもりはなく、立憲君主制に近い形へ移行しようと考えた人たちもいました。

バスティーユ襲撃/wikipediaより引用
しかし、国王一家が民衆の食糧難もどこ吹く風で贅沢なパーティーを開いたり、監視下から逃げ出したりと、”民衆を蔑ろにしている”とみられる行動を取り続けたため、最悪の結末を迎えたのです。
もしも江戸幕府が天明の打ちこわしを武力で解決しようとしていたら、怒りの矛先が米屋から徳川家に変わり、ルイ16世一家と似たような経緯をたどったのかもしれませんね。
※続きは【次のページへ】をclick!