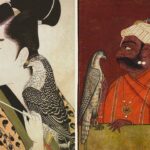前回(第33話)に引き続き、天沢和尚が武田信玄に語った織田信長。
第34話の今回は、一種類の話題に絞られています。
「鷹狩り」です。
戦国大名や江戸時代で武家の嗜みだった鷹狩り。
日本だけでなく、ヨーロッパや中東世界でも同じあり、現代でも愛好家がいますね。

世界中で愛された鷹狩/wikipediaより引用
とはいえ、動物愛護などの観点から、現代では鷹を狩りに使うよりも、海鳥などの害から防ぐための見張り役として使われることが多くなっています。
まずは鷹狩りの基本を確認して、その後、信長のやり方を見てみましょう。
◆通常の鷹狩り
手順としては以下の通りになります。
①うさぎや雉、鶴などの獲物をいろいろなやり方で探す(探し方は以下3つの方法などがある)
・鷹匠自身が草むらや水路などで探す
・勢子(せこ)という役の人が獲物を追い立てる
・犬など、他の動物に獲物を探させる
↓
②出てきた獲物に向かって鷹を放ち、捕まえさせる
↓
③鷹が獲物を美味しく食べてしまわないうちに、うまく別の餌とすり替える
文字にしてみると簡単そうに見えますが、もちろんこれは鷹をしっかり訓練しているからこそ。
「鷹匠(たかじょう)」という専門家が、幼鳥の頃から何年もかけて様々な訓練を行い、ようやく鷹狩りができるようになります。

そのためには、もちろんお金がかかります。
若く健康な鷹を捕まえること、良い鷹匠をずっと雇うことが必要になってくるからです。
故に日本では、皇族や公家だけができる高貴な娯楽とされていました。
それが戦国大名らの趣味になったのは、時代の移り変わりの中で、徐々に武家が富を得たから……という証左になりますね。
商業地帯を持つ尾張。
そのエリアを地元とする信長が、鷹狩りをしやすい環境だったとみることもできます。
では信長は、一体どんなやり方で、鷹狩りをしていたのか?
◆信長の鷹狩り
天沢の話によると、信長は鷹狩りにもいくつかの工夫をしていたようです。
まず、20人ほどを「鳥見の衆」という役に任じ、手分けして獲物を探させました。
勢子に近いやり方ですが、次からが少々違います。
獲物を見つけた場合、鳥見の衆は一人を見張り役として残し、別の人が信長へ位置を報告するのです。
おそらくは報告にかかった時間や距離などを信長が考慮し、最も狩りが成功しそうな獲物を選んでいたのでしょうね。
信長のまわりには「弓三張」「槍三本」という、弓や槍を得意とする者が三人ずつ控えており、護衛や狩りの手兵として用いていたそうです。
この「弓三張」の中に『信長公記』の著者である太田牛一も含まれていました。
牛一にとっては、とても誇らしいことだったでしょうね。
そして山口太郎兵衛という者が、「馬乗り」という役を受け持ちました。
彼は獲物の鳥の気を引くため、わらにアブをつけたものを持ってゆっくり近づきます。

イラスト・富永商太
同時に「向かい待ち」という役の者が、農夫のフリをしながら周辺で待機していました。
信長は太郎兵衛が充分に獲物を引きつけた後、タイミングを見計らって自ら鷹を放っていたそうです。
そして鷹が獲物にガッチリ組み付いたのを「向かい待ち」が確認してから獲物を押さえつけ、無事ゲット……というやり方だったとか。
信長殿は戦上手だと聞いている
見張り役と報告役を分けたり。
鷹匠ではなく信長自身が鷹を放ったり。
鷹狩においてもオリジナルの手法が見られますね。
この連載でも「信長は若い頃から馬の調練を毎日していた」と度々触れてきましたが、もしかすると、彼はただ単純に動物が好きだったからこそ、やる気が出たのかもしれません。
特にこだわりがなければ、鷹を放つのは鷹匠に任せていたでしょうから。
これらのことを聞いた信玄は、
「信長殿は戦上手だと聞いているが、その通りのようだな」
と感想を述べたそうです。

絵・富永商太
また、他にも聞きたいことがあったのか、天沢を送り出すときに
「帰りにも必ず立ち寄られよ」
と言っていたとか。
友好関係になるか、敵対関係になるか。
それは時の状況によるところが大きいものの、よほど信長への興味が増したんでしょう。
戦や領内政治の話だけでなく、こういった話題も彼らの人間性がうかがえて面白いものです。
次の第35話は👉️来るなら来やがれ桶狭間・準備編|信長公記第35話
あわせて読みたい関連記事
-

信長も家康も世界も熱中した鷹狩の歴史~日本最古の記録は仁徳天皇時代だった
続きを見る
-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

天下統一より過酷だった信長の尾張支配|14年に及ぶ苦難の道を年表で振り返る
続きを見る
-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか
続きを見る
参考文献
- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)
書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)
出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)
書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)
出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)
出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ