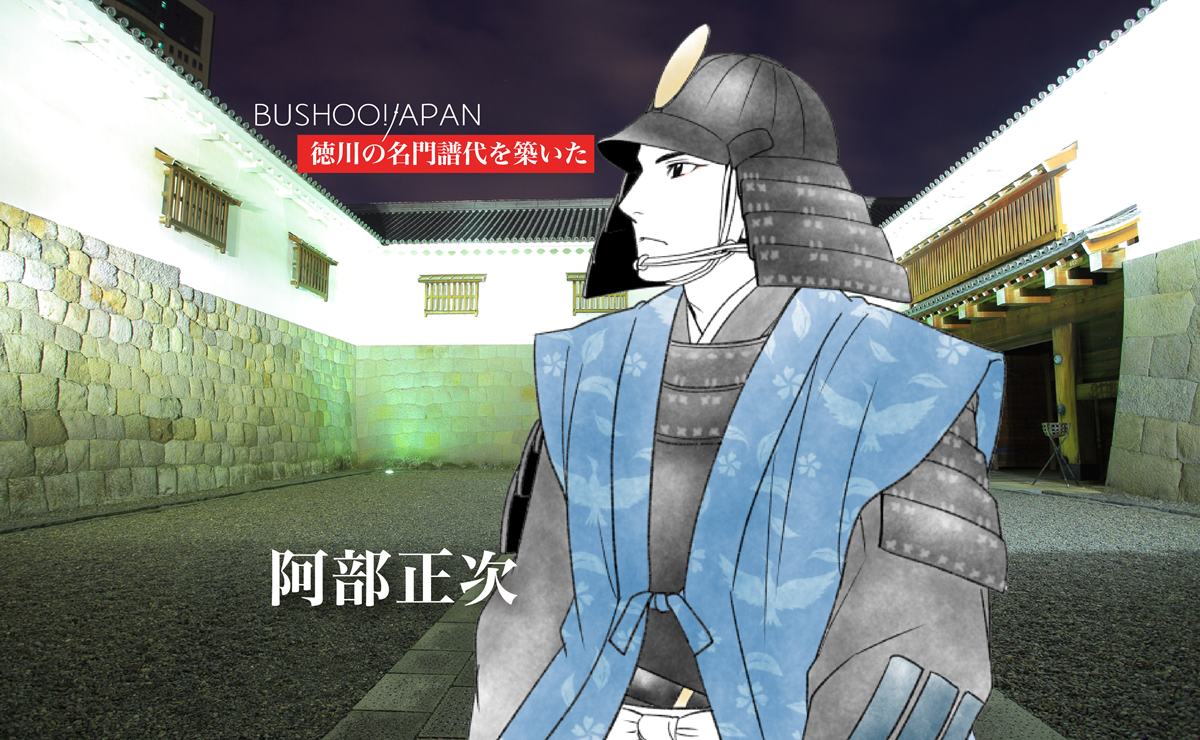正保4年11月14日(1647年12月10日)は阿部正次の命日です。
徳川配下の戦国武将であり、家康が江戸に政権を建てた後は、様々な要職にも就いた人物。
知名度という点では、徳川四天王や他の譜代家臣たちに劣るのは否めませんが、それでも欠かせない武将の一人といえ、幕末になると阿部正弘という重要なキーマンも輩出しています。
そんな名門阿部家の礎を築いた阿部正次とは一体どんな武将だったのか?
生涯を振り返ってみましょう。

こちらは阿部正弘の肖像画/wikipediaより引用
関ヶ原の年に家督継承
阿部正次は永禄十二年(1569年)、三河で生まれました。
この年は徳川家にとって非常に重要で、掛川城にいた今川氏真を開城させ、遠江を完全に支配するようになった一年です。

今川氏真/wikipediaより引用
今川家は、阿部家にとっても縁が深く、父の阿部正勝は、家康(当時は竹千代)が幼いころ今川家へ人質に送られた頃からの側近でした。
「今川義元が家康に舞を所望した際、正勝が代わりに披露して事なきを得た」
そんな逸話でも知られ、よしながふみ氏作の漫画『大奥』でも、幕末の老中・阿部正弘が徳川家に忠誠を誓う理由として登場していましたので、そちらをご記憶の方も多いかもしれません。
幕末でもそうした意識のある家でしたので、正勝の背中を見て育った正次の忠誠心は言わずもがな。
幼い頃から家康に近侍し、豊臣政権下で主君が忍耐を重ねる日々を間近に見ていたものと思われます。
慶長五年(1600年)4月7日に父・正勝が亡くなり、家督と遺領の武蔵国足立郡鳩谷5000石を継ぎましたが、これまた非常に重要なタイミングでもありました。
慶長五年(1600年)と言えば9月に関ヶ原の戦いが勃発した一年です。

関ケ原合戦図屏風/wikipediaより引用
6月に会津征伐が始まり、8月に伏見城の戦いで家康の忠臣・鳥居元忠が城を枕に討死し、9月で本戦へ。
激動の一年を迎える数ヶ月前に家を背負っていました。
当時すでに30代でしたし、正勝は前年から体調を崩していたようですので、覚悟はできていたものと思われますが……やはり、天下分け目の渦中では緊張したことでしょう。
正次は、旗本の一人として関ヶ原の戦い本戦に参加。
戦後の11月には従五位下・備中守の官位に叙任されました。
他に褒賞として相模・高座郡一宮5000石を与えられており、合計1万石で大名といえる基準になっています。
御書院番から伏見城番へ
阿部正次はこのころ「御書院番頭」という役職も務めていました。
御書院番とは江戸幕府の役職の一つで、主に将軍が外出する際の護衛を務め、「頭」はその責任者を表します。
他にも似た役職はありますが、御書院番の場合は後年
「毎年交代で駿府城の在番を務める」
という特徴を持つようになりました。
駿府城は大坂城と同じく、江戸時代を通して城代が置かれ、要所として扱われた城。
責任も重いだけに出世の道も開かれており、後年には旗本のエリートコースとなりました。

駿府城東御門
正次の時代にはまだ徳川家康が駿府にいましたので、城代という役割はなかったと思われますが、役目を立派に勤め上げます。
慶長十五年(1610年)には下野鹿沼で5000石を加増され、翌慶長十六年(1611年)には大番頭を任され、3年に渡って伏見城番を務めました。
慶長十六年から3年というとこれまた転機の年でして、大坂冬の陣が起きる慶長十九年(1614年)です。
伏見城番の正次は、大坂城豊臣家の監視を中心に、京・大坂の治安維持や情報共有の役割を果たしたことでしょう。
そしてついにその時を迎えます。
大坂冬の陣です。
※続きは【次のページへ】をclick!