こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【足利義澄の生涯】
をクリックお願いします。
親政を進める若き将軍に反発する細川政元
富子は足利義澄にとって叔母です。
日野家の血筋と富子自身の財力もあり、幼い義澄では到底逆らえません。
そんなわけでしばらくは義澄もおとなしくしていたのですが、明応五年(1496年)に富子が亡くなると、
「これからは自分で政治に取り組んでいかなくては!」
という意志を見せるようになりました。
15歳になった頃ですから、思春期でもあり反抗期でもあり、いわゆる「お年頃」だからこその感情もあったでしょう。
しかし、これを厨二病と思ったのか。
自らの手で政務を行おうとする若将軍の姿を、細川政元はよく思いません。
政元にとって将軍とは「お飾りでいなければならない」存在であり、意志や行動力を持たれては困るのです。

細川政元/wikipediaより引用
当然、両者は対立することになり、政元はスネて領地に帰ってしまいました。
管領という要職の人に勝手に辞められてはさすがに困るので、一時は義澄も譲歩します。
不思議なのはその後。
今度は義澄がお寺にこもり……なんだかお互いに「実家に帰らせていただきます!」みたいな状態になってしまうのです。子供かっ!
このときは、さすがに政元たちが引き留めました。
足利家の血を引く義忠を殺しておくべし
義澄は、将軍職に戻るためとして2つの条件を挙げました。
1武田元信の相伴衆登用
2足利義稙の異母弟・実相院義忠(ぎちゅう)の処刑
です。
武田元信とは、若狭武田氏の当主です。
若狭武田氏とは、元は安芸武田氏の武田信賢が若狭に根付いた一族で、では安芸武田氏は?というと、甲斐武田氏から分家した一族でした。
ややこしいので、ざっくりと
甲斐武田氏
↓
安芸武田氏
↓
若狭武田氏
という理解で間違いではないかと。
家としては細川氏とのつながりが深く、武田元信自身も政元と張り合ったことがあり、義澄としては側に置いて細川家を牽制したかったものと思われます。
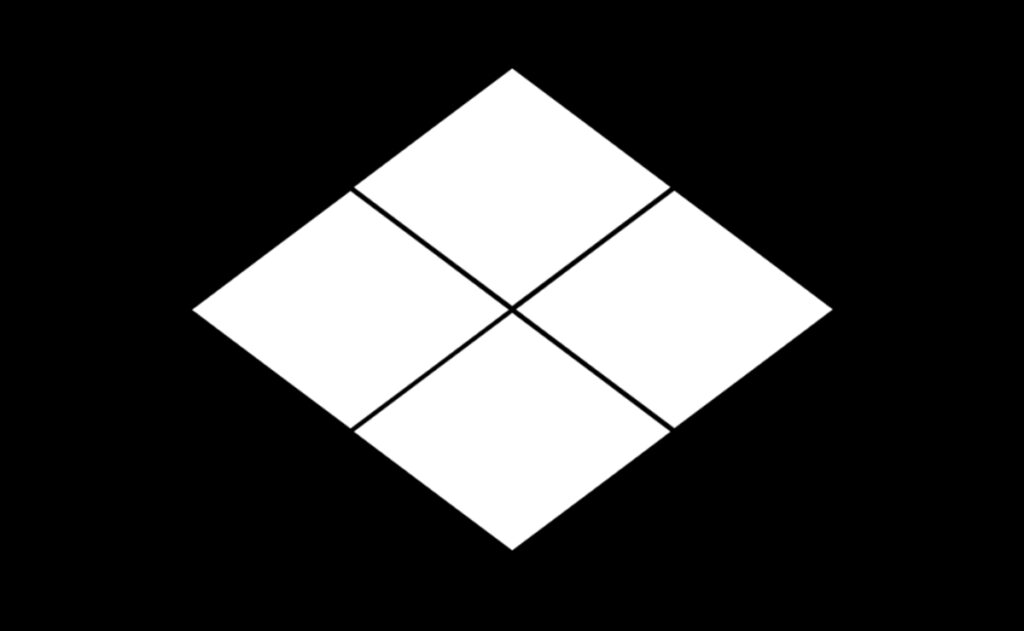
武田菱/wikipediaより引用
もう一つの条件である義忠は、義稙が京都から追放された後も京にいることを許されており、義澄の病気見舞いに行く程度には関係が良かったのですが……。
いかんせん、この状況では「足利氏の血を引く男子」というだけで、政敵になり得ます
そこで義澄は、見舞いに訪れた義忠をその場でひっ捕らえ、近くにあった阿弥陀堂で殺してしまったのでした。
義忠にとっては実に迷惑極まりない話ですが、彼がいなくなれば政元が義澄の代わりに担ぎ上げられる候補がいなくなるわけです。
こうして、義澄と政元は馬が合わないながらに、少なくとも職務上は協調していきました。
内心はお互い「ギギギ」な感じだったでしょうけど。
※続きは【次のページへ】をclick!
