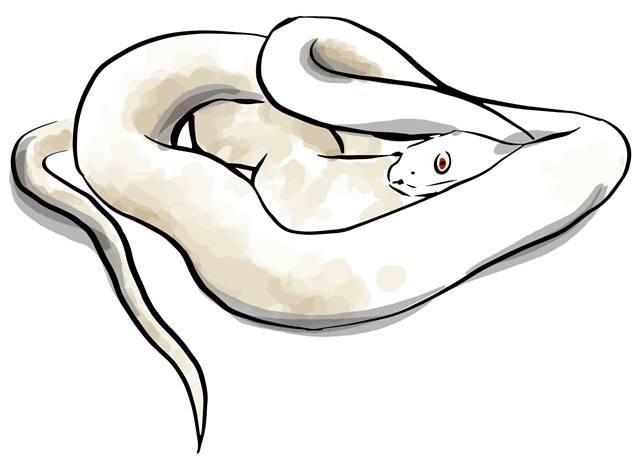こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【あまが池の大蛇と成政】
をクリックお願いします。
信長自ら脇差をくわえ、池の中へ
そして蛇替え当日、周辺の村からも住民が多々集められ、大規模な作業となりました。
しかし、どうしたわけか、元の7割ほどまで水を減らすと、それ以降は何度すくっても水が減らなくなってしまいます。

そこでなんと、信長自ら脇差をくわえ、池の中に入っていくという荒業に出ます。
7話でも述べましたが、信長は本当に泳ぎが得意だったんですね。
しかし一向に蛇は見つからず、信長は一度水から上がり、集まった村人の中から泳ぎの得意な者を一人呼んで、
「お前がもう一度調べてこい」と命じて、池の中を探させました。
それでもやはり蛇は見つからず、信長は諦めて清州城へ帰ります。
旧暦1月下旬=新暦2月下旬なので、いくらなんでも長時間の水泳には向かない季節です。
毎年3月から水練をしていた信長からすれば、「今年は少し早く泳ぎ始めるか」くらいの気分だったかもしれませんが。
隙を見て刺し信長公を道連れに飛び込みます
この節は、後半の話のほうが主題かもしれません。
前述の通り、この大蛇は、佐々成政の居城付近での話です。
現代の道路だと7~800mくらいしかないほど。実は当時の成政は、信長に反抗心があり、この日は仮病を使って蛇替えに参加しなかったといいます。
そのため成政は「信長が比良城見物を兼ねて、蛇替えの後ここに立ち寄って、切腹させられるのではないか?」と怯えていたのだとか。
それを成政が自分の家臣に告げると、家老の一人・井口太郎左衛門という者が言いました。
「信長公がここにいらっしゃるのなら、城の見物をしたいとおっしゃるでしょう。私が水辺へご案内し、隙を見て刺し、そのまま信長公を道連れに川へ飛び込みます」
そう言って成政を安心させました。
牛一が信長に心酔していたことがよくわかる
結局、信長はまっすぐ清洲城へ帰ったので、この計画が実行されることはなく、誰も死なずに済んでいます。
成政の取り越し苦労っぷりもすごいですが、太郎左衛門の捨て身ぶりもまた凄まじい。
さすが戦国時代としかいえません。
これについて、著者である太田牛一は以下のように信長を褒め称えております。
「一城の主たる者は、このようにいついかなるときも用心していなければならないのだ」
信長がこのときどう考えていたかはわかりません。
ただの偶然という可能性もありますが、牛一が信長に心酔していたことがよくわかる表現です。
※ あまが池……現在は「蛇池(じゃいけ)」と呼ばれる名古屋市西区の池。蛇池神社(正式名称は「龍神社」)という神社があるが、これは信長由来ではなく、20世紀になってから建てられたもの
あわせて読みたい関連記事
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

佐々成政の生涯|信長の側近から大名へ 最期は秀吉に敗れた反骨の戦国武将
続きを見る
-

織田信秀(信長の父)の生涯|軍事以上に経済も重視した手腕巧みな戦国大名
続きを見る
-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか
続きを見る
-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請
続きを見る
参考文献
- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)
書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)
出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |
Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)
書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)
出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)
出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |
Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)
書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |
Amazon: 商品ページ