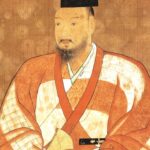慶長七年(1602年)5月1日、徳川家康が二条城の造営を命じました。
今も京都市にデーンと居を構えている立派な建物ですね。
しかし二条城というのは、歴史上、他にもいくつか存在していて、家康が建てさせた二条城と同じ場所とも限りません。
主に時代や関係する人物によって特徴が異なりますので、一つずつ確認してまいりましょう。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
十三代義輝&十五代義昭の「二条御所」
なぜ二条城という名前なのか?
もともと初代・足利尊氏から三代・足利義満までの足利将軍が、京都・二条の地に御所を構え、場所が変わってもその住居を「二条御所」と呼んでいたことからです。
ほんのちょっとだけ二条にも敷地があったからとも言われています。
あるいは足利義輝が刺客相手に奮戦し、あえなく敗れた地名だったり、
織田信長が足利義昭のご機嫌取りに献上した屋敷の名前でもあり。
足利家と関わるだけに、戦国時代にも影響する土地柄となってますね。
-

刀を握ったまま斃れる壮絶な最期~足利義輝13代将軍の生涯30年まとめ
続きを見る
-

信長と義昭「上洛戦」の一部始終!京都入りまでどんな敵と戦った?
続きを見る
信忠が最期を迎えた「二条城」(二条新御所)
【本能寺の変】では「織田信忠が二条城で最期を迎えた」とあります。
これは家康の建てた二条城とはまったくの別物です。
元は二条家という公家の持っていた屋敷だったのを「ここの庭はいいな!」と気に入った信長が譲り受けたところでした。
こう書くとカツアゲしたかのようですが、二条家はこの直前に信長の勧めで別のところへ引っ越していたので、特にトラブルもなく引き渡してもらえたそうです。
そして信長は屋敷を改修し、二年ほど京都での住まいとしていました。
その後、ときの皇太子・誠仁親王に献上し、本能寺の変までは皇太子一家の「新御所」となっていたのです。
二条家が持っていた頃から見事な庭園で有名なところだったそうなので、皇太子の住まいには相応しい佇まいだったことでしょう。
また、信長が改修した際に軍事拠点としての機能も追加されていたらしく、それゆえに御所でありながら「城」と称されるようになったようです。
元が二条家の持ち物だというので「二条城」とか「二条新御所」になった、と。
その防御機能を信頼して、信忠はここで篭城することにしたのですが、明智光秀の配下に襲われ、敗死へ……。
※続きは【次のページへ】をclick!