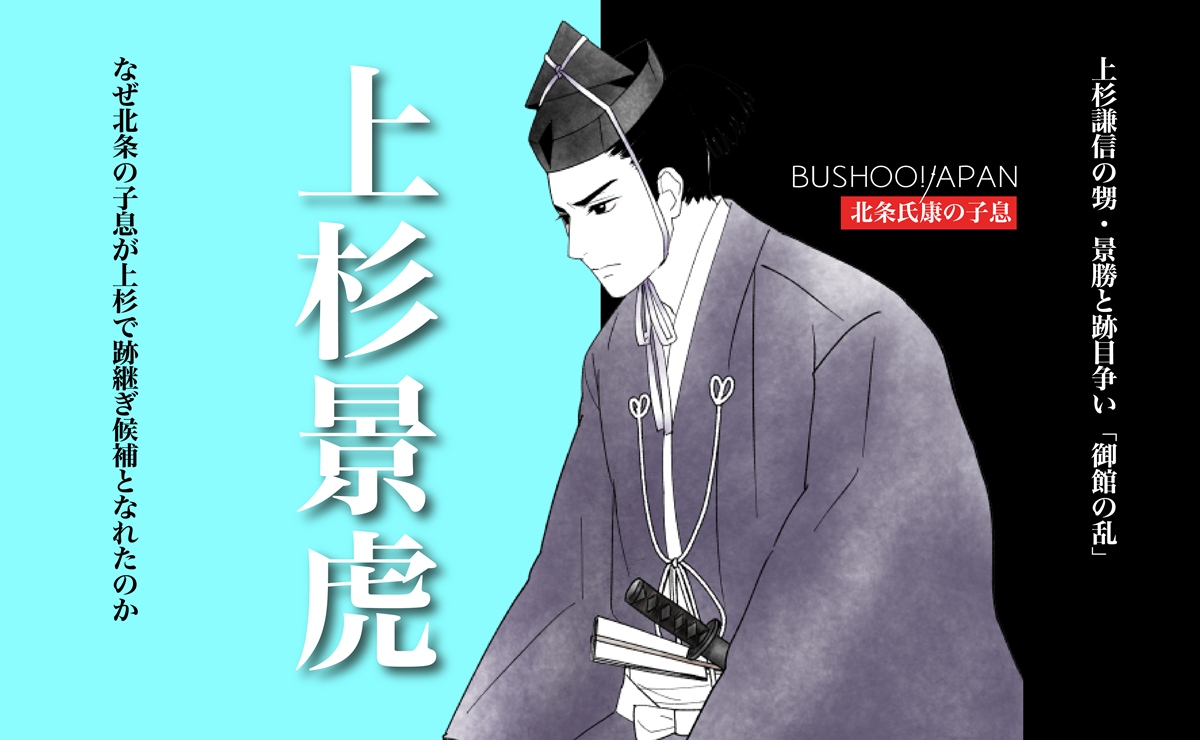戦国時代の大名家で当主が突然亡くなり、複数の男児がいれば、まず避けられないのが御家騒動。
「長男よりも次男のほうがデキがよい!」
「いや、三男のほうが民や将兵からの人望もある!」
こんな調子で、有力家臣も巻き込みながら危機的状況を迎えるもので、最も著名な例を一つ挙げれば上杉家でしょう。
軍神と称えられた上杉謙信には、上杉景勝と上杉景虎、二人の養子がいました。
しかし、どちらかを次の当主に指名しないまま急逝したため、残された二人は【御館の乱】と呼ばれる内乱を約一年にも渡って繰り広げたのです。
この御家騒動で、最大の謎が以下の点かもしれません。
・上杉景勝は、謙信姉の実子だった(甥)
・上杉景虎は、北条家からやってきた養子だった
血縁だけ見れば圧倒的に上杉景勝が有利なようにも思えるのに、実際は上杉景虎を支持する家臣もいて、だからこそ内乱は一年にも及びました。
いったい景虎はなぜ、上杉家の家臣達から支持されたのか?
そもそも北条から来た養子がなぜ跡取り候補となれたのか?
上杉景虎の生涯と共に振り返ってみましょう。

絵・小久ヒロ
北条氏康の六男あるいは七男
上杉景虎は天文二十三年(1554年)、北条氏康の六男あるいは七男として生まれました。
生年については今のところ不確定なのですが、天文二十三年が事実であれば、上杉謙信もう一人の養子・上杉景勝より一つ年上。
母は北条家臣・遠山康光の妹でした。
景虎は、氏康の息子という、北条家では最も有力な血筋となりますが、幼少期の頃の記録はほぼありません。

北条氏康/wikipediaより引用
数少ないものとしては、永禄二年(1559年)の『小田原衆所領役帳』に、”武蔵小机衆”筆頭「三郎殿」という名前で記されていることでしょう。
・武田信玄の養子となり武田三郎と称していた時期がある
・初名が「氏秀」だった
そんな説もありますが、江戸時代の書物に出てくる話で、一次資料には登場しません。
上杉家へ養子に行くまでの彼は、『小田原衆所領役帳』の記述とも合致する「三郎」のほうが相応しいようですね。
時が流れて永禄十年(1567年)、三郎は、北条幻庵の娘と結婚したとされています。

北条幻庵/wikipediaより引用
幻庵は小机周辺の領地経営に関与していたようなので、『小田原衆所領役帳』の記述と合わせて考えると、もともと三郎は幻庵の娘婿になることが決まっていたのかもしれません。
というのも、幻庵の息子が同じく「三郎」を名乗っていたのですが、永禄三年(1560年)に亡くなっていました。
さらにその後を継いだ次男やその下の三男も、三郎の結婚からさほど経っていない永禄十二年(1569年)討死してしまっています。
幻庵の次男や三男、あるいは北条本家に何かあったときのため、三代当主・氏康の息子と一族内で結婚させておけばひと安心。
と、実際に懸念どおりに進んでしまったわけですが、この妻とは間もなく別離を迎えてしまいます。
同盟と引き換えに上杉家へ
当時の北条家は、上杉家と和睦を結ぶべく交渉を進めている最中でした。
そして永禄十二年(1569年)、お互いに人質を出すことで合意し、その人選が始まります。
北条からは、北条氏政(景虎から見て兄)の次男である国増丸が謙信の養子に出されることで話が進んでいました。

北条氏政/wikipediaより引用
しかし、事態は急変します。
岩付城主・太田氏資が討死し、後継ぎがいなかったため、氏資の娘と国増丸を結婚させて跡を継がせることに決定。
「北条がまだ幼い国増丸を人質に出すことを躊躇った」という説もありますが、ともかくその影響で上杉へ入ることになったのが三郎でした。
元亀元年(1570年)4月、三郎は母方の叔父と思われる遠山康光らと共に謙信の本拠・春日山城へ移ります。
既に「上杉家の娘と結婚する」ことが決まっていたのか、越後行きにあたって幻庵の娘とは離縁。
夫婦で越後へ行ってしまうと、今度は幻庵の後継者がいなくなってしまいますしね。
彼女が再婚すれば幻庵の後継者を用意できますし、家の都合を考えれば致し方ない措置だったでしょう。
問題は、三郎の待遇です。
北条と上杉は幾度も戦闘を繰り返してきた間柄ですし、果たして三郎はスンナリと迎え入れられたのか?
※続きは【次のページへ】をclick!