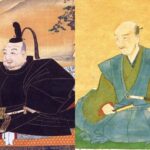「人生何があるかわからない」とは使い古された表現ながら、人間誰しも歳をとればとるほど実感の湧く言葉でもありますよね。
本日は、最晩年に思わぬ落とし穴が待っていた武士のお話。
寛永13年(1636年)3月19日は徳川家臣・酒井忠世が亡くなった日です。
酒井家はいろいろな系統があって少々ややこしいですが、忠世の家は「雅楽頭家(うたのかみけ)」と呼ばれ、徳川四天王に数えられる酒井忠次とは違う血筋でした。
忠次のほうは「左衛門尉家(さえもんのじょうけ)」と呼ばれています。
※以下は酒井忠次の関連記事となります
どちらも古い時代から松平家に仕えていた、まさに譜代の家臣でした。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
10代後半から家康や秀忠の側近
酒井忠世も幼い頃から徳川家康に仕え、10代後半辺りから家康や徳川秀忠の側近を務めました。
-

徳川家康はなぜ天下人になれたのか?人質時代から荒波に揉まれた生涯75年
続きを見る
家康が関東に移ると、父とは別に加増を受けて川越城主となっています。
この頃は10代後半で、秀忠付きの重臣として扱われるようにもなりました。
秀忠は忠世の7歳下なので、歳の近い側近として選ばれたのでしょう。
朝鮮出兵では名護屋城に滞在、関ヶ原の戦いでは会津征伐や第二次上田合戦に従軍しています。
-

上杉征伐と小山評定からの家康vs三成対決~そして関ヶ原が始まった
続きを見る
おそらく、上田では逸る秀忠をなだめる場面もあったのでしょう。
音楽の才? 家康の命で雅楽頭を名乗るように
秀忠からの信頼も上々でした。
特に、当人が二代目の征夷大将軍になると、忠世はそれまでの忠勤を評価されてか、筆頭年寄として一段と高い立場になりました。
-

なぜ徳川秀忠が二代目将軍に選ばれたのか 関ヶ原の遅刻は問題なし?
続きを見る
この場合の「年寄」は老中とほぼ同じ意味で、現代でいえば大臣のようなものです。
その後、大御所となった家康の命で雅楽頭(うたのかみ)を名乗るよう命じられました。
「雅楽頭」は朝廷の雅楽寮(うたりょう)という役所のトップのことです。
文字通り音楽を担当する役所なのですが、忠世が楽の才を持っていたとか、楽器が得意だったという話はありません。
むしろ無口で有名な人でした。
おそらくは、忠世の先祖が雅楽助(雅楽寮のナンバー2)を名乗っていたからの名乗りだったのでしょう。
同じ酒井氏でも、忠次のほうは「海老すくい」という踊りが得意で、大河『どうする家康』でも何度も描かれていますので、こっちのほうが何となく雅楽頭の通称が合う気がするかもしれません。
まぁ、このころ忠次は既に他界していますし、上記の通り忠次の系統は左衛門尉(さえもんのじょう)家と呼ばれていたのですけれども。
※続きは【次のページへ】をclick!