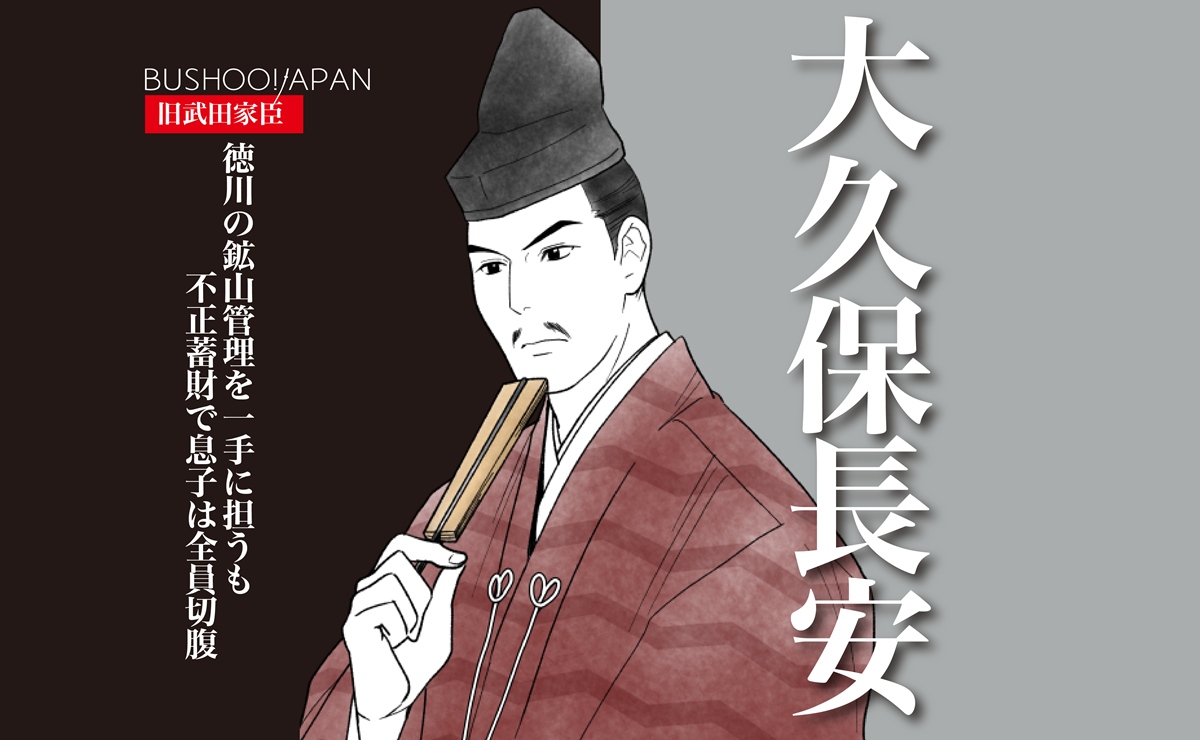桶狭間の戦いを皮切りに、幾度も死地をくぐり抜けてきた徳川家康。
関ヶ原の戦いに勝利して、天下の主導権を握ってからは、大坂の陣まで特に大きな事件もなく、割とスンナリ天下人に……とはいかず、実際は苦労の連続でした。
各大名の減封(石高削減)・移封(引っ越し)・改易(お取り潰し)あれば、将軍就任、外交問題、法律整備、豊臣対策などなど、課題は山積み。
極めつけが家臣同士の権力争いでしょう。
派閥争いや金銀のからんだキナ臭い話も当然あり、かなり後味の悪い事件も家康の生前に勃発しています。
慶長18年(1613年)4月25日に死亡した大久保長安――その名も【大久保長安事件】。
ド直球なまでに“カネ”が関わり、あまりにも生々しい話のせいか。
大河ドラマ『どうする家康』では全く描かれなかった同事件の顛末と、大久保長安の生涯を共に振り返ってみましょう。
猿楽師の流れを汲むともされる大久保一族
江戸時代以降、何代も続いているような家は、先祖のルーツや事績を記録しておくことが多いものです。
もしも大久保一族もそうだったら、多少は誇張が混ざっても一定量の確たる事績が残されていたでしょう。
しかし、それが叶わなかった。
大久保一族の出自は曖昧模糊としたままで、祖父が春日大社の能楽師であり、父・大久保信安の代で大和国から播磨国に流れ、猿楽の大蔵流に関わったとされます。
そんな諸国をさすらう能楽師の子として、生まれた大久保長安。
父の信安が流れ流れて甲斐へたどりつき、武田信玄に能楽師として仕えると、息子である長安も武田家に仕えることになりました。

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用
戦国時代は鉱山開発の転換点でもあった
武田家に落ち着いた大久保長安は、鉱山開発に携わりました。
流浪の過程で鉱山にかかわる新技術を身につけていたとしても不思議ではないでしょう。

戦国時代は、朝鮮半島から銀の採掘技術が伝わり、シルバーラッシュが起きたとされています。
隣国の明から銀を求められたからです。
戦乱真っ只中の日本では、急速に普及する火縄銃のため、火薬や弾薬の確保が必要でした。
それを海外貿易でまかなうためには銀が手っ取り早いということで、鉱山の開発も急ピッチで進められたのです。
火縄銃という軍事革命が起こる中で、武働き以上に新たな技術が重視されていく時代。
長安の特殊技能がよほど重視されていたのか。
兄が【長篠の戦い】に参戦しても、彼は戦地へ赴かず無事に生き延びています。
そして長篠から約7年後の天正10年(1582年)に武田家が滅亡へ追い込まれると、長安は徳川家康に召し抱えられました。
甲斐の鉱山技術を持つ者となれば、他家に移っても十分に働ける。
徳川にとっても必須の人材と言えました。
※続きは【次のページへ】をclick!