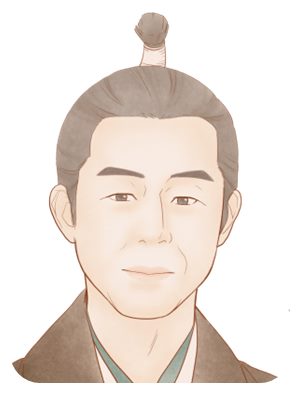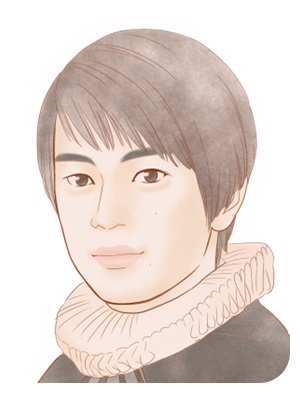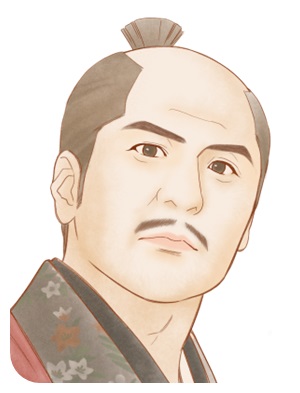花の都・フィレンツェには、陰謀と悪徳が渦巻いています。
メスキータがドラードに、マンショとミゲルの行方を尋ねると、そこへマンショだけが戻ります。
ミゲルは実は娼館にいるわけで。
娼婦から「また来てね〜」なんて言われながら、意気揚々と道をゆくミゲルです。
兄を殺したい
メスキータは、フェルディナンド1世・デ・メディチとなる枢機卿と話しておりました。
彼は、兄である大公のことを嫌っており、殺したいとすら訴えます。
古代ギリシャ・ローマの文明再興こそ、ルネサンスの精髄ではあります。
しかし、この時代はキリスト教誕生前で、堕落に耽っていたという批判もあります。
典型的なものが、男色を含めた好色です。
枢機卿は、色に溺れた兄を軽蔑し許せないと考えています。
史実においても、彼の統治は兄の時代と大きく異なるのです。
そんな兄なら殺したい——これでは日本の戦国時代と、さして変わらないとは思いませんか。これが花の都が見せる、悪徳の顔なのでしょう。
ミゲル、女体の素晴らしさを語る
ミゲルは、女体を描いた紙をマルティノに渡し、読めと迫ります。
「こんなにも豊かで、ふくよかで、えもいわれぬほど柔らかで、この世界に二つとない尊いもの……」
これには皆困惑しております。
と、そこへ、メスキータもやって来ました。
マルティノがその紙をメスキータに渡すと、当然困惑します。
女体を讃美した、有名なフランスの詩だそうで。壁に貼られていたものだとバレバレの言い訳をするミゲルです。
あっ、メスキータとドラードはわかっていて、ジュリアンはわかっていませんね。
ここでメスキータは、大公夫妻が面会を望んでいると告げます。
ちなみにこの頃には既に「フランス=エロスの本場」という認識がヨーロッパにはありました。イギリス人はフランス語のエロ本を買いあさっておりました。
「フレンチ・キス」(=ディープキス)
「フランス語の手紙」(=避妊具)
という言い回しが英語にあります。
これは、フランス人みたいにエロいアレということですね。フランス人からすれば、「何を言っているんだイギリス人!」という話になるわけですが。
どうにもこういう、異国にはエロい人がいるぜ妄想というのは、割とある話でして。
東アジアに目を向ければ、当時の明でも、ポルノの題材に【豊臣秀吉と淀が出てくる】なんてことがあったそうです。海の向こうにエッチなファンタジーを求める、って話です。
ヘンリー8世がアン・ブーリン(エリザベス1世の母)にメロメロになった理由も、このフランス妄想に一因があります。
アン自身はさほど美しくはありませんでしたが、フランスで身につけたマナーがとびきりエロチックだったのです。
黄金の茶室、欲望の間
そのころ、日本では……。
黄金の茶室で、豊臣秀吉が千利休と高山右近を従え、茶を飲んでおります。
それにしても豪華極まりない茶室です。
カメラワークもよくて、常にキラキラした映像が怖くなってくるほど。
その一因は、ギンギラギンの秀吉にもありますね、
右近が黄金の茶室を褒めると「利休の狭苦しい茶室の方が好きだろう」と秀吉が右近に言うのです。
怖い……これはもう圧迫茶室だ!
さりげなく
・利休の弟子が増えている
・キリシタンが多いそうだな、
と秀吉は誘導します。
右近は欲望を捨てることが、信仰に似ていると語るわけですが……黄金の茶室でそれは言わないほうがよいのでは……?
秀吉、ムッとしているような。
「欲望を捨てて、何になる?」
そこには心の豊かさがあると右近が返すと、秀吉は多くの女を侍らせることこそ、己の心の豊かさだと投げかけるのです。
私だったら、誤魔化すような気がしますが、右近はちがう。
そういう欲望は人を貧しくすると重ねるのです。秀吉から意見を求められて、利休は欲望を断ち切るために利休庵を作ったと答えます。
そんな二人に、金で囲まれた茶室が好きだと語る秀吉。
右近は利休から茶碗を受け取り、一服します。
黄金でキラキラしているはずなのに、華やかさどころか怖さしかそこにはありません。
秀吉は、二人に欲望にとらわれた己は貧しいと思っているだろう、利休庵でそう言っているのだろうと怒鳴り散らします。
怖い……怖いィ!
「わしから欲望を除いたら何も残らぬ! 力と女、それへの欲望があったからこそ、わしはここまで来た!」
秀吉はここで日本は神の国だ、山や木々に神が宿る、神同士は対立しない。
それなのにナゼ、バテレンはそのことを拒むのだと問いかけます。
自分たち以外の信仰は悪魔がもたらしたものだと言う。
それはナゼ?
右近は、戦いに明け暮れた心にイエスの教えが響いたと、恐れずに返します。
信仰心こそ、唯一の指針である。
争うことの無意味さを知ったからこそ、信じるのだと。秀吉と真っ向対立しています。
その教えを捨てろと言われたらどうするのか。秀吉とイエスが天秤にかけられる右近。そして彼は、神を選びます。
ここで利休が黄金の茶碗を差しだします。
茶をゆっくりとすする秀吉。
それだけなのに、おそろしい。
「利休庵を捨てろ、利休!」
怒鳴る秀吉。
右近にも、利休にも、信念よりも自分を選べと秀吉は迫ってくるのです。
このあと、利休は利休庵で茶を点てています。
そして切腹を遂げることになる運命が語られます。
あ、あああッ……こういう右近と利休の描き方、ありなのか!
信念のために死ぬ――そういうことか。
こんなにビリビリ震える描き方があるのか。
秀吉の心の動きは、わかりやすいものがあります。
女が閨に侍らない。キリシタンが神を選ぶ。利休が茶の湯の道を究めようとする。
自分を一番だと思わないものは排除する。それが、彼のやり口なのです。
そう来たか。
こういうやり方も、ありなのか!
こんなに怖い秀吉、見たことがない……うわあ、これはやられたあ!
これがイタリア陰謀の世界か……花の都か
ここで枢機卿が、ビアンカ妃について語り出します。
美貌のビアンカに一目惚れした大公。
その後、ビアンカの夫が刺殺され、そして大公の妃も窓から転落死を遂げました。
この妃ジョヴァンナ・ダズブルゴは、ハプスブルク家出身です。
血筋の面では申し分なかったのですが、痩せ型でセクシーではなかったそうで……。
うーん、これがイタリア陰謀の世界か……花の都が怖い!
日本のフィクションですと、時折こんな設定があります。
「日本人女性がキリシタンに心ひかれたのは、側室を認めないために夫婦愛が深まるから」
コレも、本音と建て前なんですよね。
ヨーロッパでも王族というものは、結婚は世継ぎ作りであり、性的な快楽は愛人と貪るものだという慣習がありました。
日本との違いがあるとすれば、非嫡出子に王位継承権がない点くらいです。
カトリーヌ・ド・メディシスも、夫の愛人には歯ぎしりをしていたものです。
国によっては婚外愛人関係を認めない貴族はむしろ「ダサい奴だよな〜」と笑いものになったくらいです。
大公とビアンカの場合は、愛人では満足できずに殺人までしているのですから、ヘンリー8世タイプということですね。
そんな曰く付き美女が、四少年と面会を果たすのです。
妃は茶碗をしげしげと眺め、何なのかと尋ねます。
茶を飲むものと聞いて、妃は興味深そうにします。メスキータはこんなものは鳥の餌入れにしか見えないと冷たく言いますが、大公は興味津々です。
色があるわけでもないし、形も平凡。
それでも心惹かれる。
これを作った者に会いたいと熱望するのです。
形あるものは壊れてしまうもの。
美しい花も儚い。
けれども、絵や彫刻は残るのだと大公は語ります。その前には信長の金屏風があります。
こうして残るものを作るものこそ、神の使わしたものであると大公は語ります。
一方で妃は、少年たちを舞踏会に誘うのでした。
美女に誘われて、これはドキドキしますよね!
明では嫌われた茶碗に高値がつく不思議
さて、大公の心を掴んだ茶碗ですけど。
美学だけでは言い切れないものもあります。
というのも、作られた明では特に価値がないものでも、『プレミアがつくのでウッハウハ〜!』という、日本ではあまり知られざる側面がありましてね。
「日本人ってさぁ、地味な茶碗でも高く買うからチョロいよね!」なんて思われていました。
曜変天目茶碗も、明では不吉とされ、不良品であったのです。
不良品であるからこそ割られてしまい、そのため極端に数が少ないのです。
「不良品でも買っちゃう日本ってどうよ?」
なんて思われていてもさもありなんですが、まあ……おかげで日本に残ったとも言えなくはありません。
明ではわからないセンスがあった、とも言えますよね。
舞踏会で踊ろう
四人は、舞踏会のために踊り始めます。
マルティノはジュリアン、マンショとミゲルに別れ、訓練開始。
当時はパヴァーヌ、ガイヤルドが流行中でした。
練習中、うんちくを語り出すマルティノも踊れと他の三人が言うわけですが、マルティノは断ります。
その理由は?
「機械は得意だが、女は駄目だ。前にすると何も考えられなくなる」
「お前が?」
「お前が?」
「……うるさい」
お、マルティノの意外な弱点だなっ!
こういうタイプは、理性を失うことがともかく苦手なんでしょう。こいつめ〜!!
練習をこなし、少年たちは、舞踏会に参加。
和装で草履の日本人が、フィレンツェで踊る!
あー、こういうのが見たかったんですよね。女性たちのドレスも素晴らしい。
四人とも楽しそうです。
ちょっと切なくなってきた……この先何があるか考えるとつらいものもありますが、こうして踊った思い出が彼らの中には生き続けることでしょう。
役者さんも、相当努力を重ねたはずですね。本当に皆、頑張りました!!
四人は馬車の中で、うっとりとした思いでおります。
ミゲルはあのエロ詩を繰り返し、止められています。ミゲル、大丈夫かっ!
馬車は長い道を進んでゆくのです。こういう移動ひとつとっても、美麗でうっとりしてしまいます。
日本から出発して三年。ついに彼らは法皇の待つローマに向かうのです。
しかし、手前で足止めをくらい、宿に逗留するほかありません。
メスキータは、使節団が偽物だという投書があったというのです。それはマンショのせいだというのです。
問題となったのは、血筋です。
しかし、マンショは問題がある。
領主の子ではなく物乞いの子で、母も生きているのだと。ヴァリニャーノは騙した、物乞いであるという目撃証言もあったのです。
マンショは、そのことを認めます。
保護した親がキリシタンであるため迫害され、村はずれで物乞いをしながら生きていたのでした。
物乞いの子で何が悪い?と憤るマンショに、メスキータは今まで騙してきた上に、法皇まで騙すのかと反論するのです。
「お前たちの旅はここで終わりだ!」
四少年はヴァリニャーノの操り人形で、もうそんな糸は切れかかっている――メスキータはそう突き放します。
それでも少年たちの耳には「マギ!」と歓迎する声が聞こえてきます。
法皇の前で、枢機卿は侃々諤々大論争を繰り広げられています。
ヴァリニャーノの野心も俎上にあがります。
ゴアで、ヴァリニャーノは告発状について聞かされています。
きっちりと彼の反応も描くわけです。ヴァリニャーノは、信長が光秀に討たれた件について語ります。
情熱は敵を招くと、諭されるヴァリニャーノ。
歓迎の声を前に、為す術もない少年たち。運命はどうなるのでしょうか。
MVP:秀吉、右近、利休
黄金の茶室は怖かった……悪夢のようでした。
豊臣秀吉の描き方が複雑で、面白い!
織田信長とはまた違います。
秀吉の自意識や名目は信長の後継者ということになっておりますが、むしろ対極上にあると本作では位置づけられているのでしょう。
本作は、信長の行動も、秀吉の行動も、信念が根底にあると丁寧に迫ってきます。
利休を殺すのも、右近を追放するのも、欲望が奥底にある。
秀吉の行動原理の背景に、欲求を置いているのです。
それでも強引ではなく、説得力があります。
新史料や説を丹念に追ってゆくドラマも魅力的ですが、人間の動機や欲求、ゆるぎない価値観に重きを置くこういう描き方もありです。
そして、こういうドラマこそ、大河がなくしてしまったものかもしれないと唸らされたのです。
総評
深い……。
本作のキャスティングについて、あれこれ考えておりました。
もしこれが日本であれば、宣伝効果を考えてマンショとメインビジュアルに緒形敦さんを据えたのではないかと思ってしまいまして。
四少年の役者さんは、どれも勝るとも劣らない魅力にあふれており、実力も充分にあります。
それでも、二世俳優という血統を重視し、緒形敦さんをメインにしたのではないかとちらっと思ってしまうわけです。
そこまで考えて、ハタと気づきました。
緒形直人さんの秀吉。
緒形敦さんのミゲル。
この二人は、ペアなのではないか?
四少年の魂のペアとも思える相手は、見つかりつつあります。
精神の強さと献身を求めたジュリアンには、医師カルロ。
知性と真理を求めたマルティノには、ガリレオ。
愛と真っ直ぐに生きることとは、マンショが信長から託された問いかけ。
こう見て来ると、ミゲルだけがまだいないように思えるわけで、それが秀吉ではないか?と思ったのです。
秀吉の欲深さ、業の深さ、権力者としての振るまい。
ミゲルの正義感の強さ。
これは対極にあるようで、そうでもないのかもしれない。
だとすれば、父子がキャスティングされる理由も納得できるというものなのです。
それにしても、本作っておそろしいですね。
イタリアのドロドロした陰謀劇も、しっかりとフォローしてきました。
かわいらしさすらあるビアンカ周辺のドロドロさ。
兄を殺したいと息巻く枢機卿。
とんでもない場所に踏み込んじゃったわけですよ!
むしろ日本のほうがぬるいような、と思わせてあの茶室です。
人間の欲望や業とは、洋の東西なんか関係ない。
本作はそう描いているのです。
文:武者震之助
絵:小久ヒロ
【参考】
◆アマゾンプライムビデオ『MAGI』(→amazon)
◆公式サイト(→link)