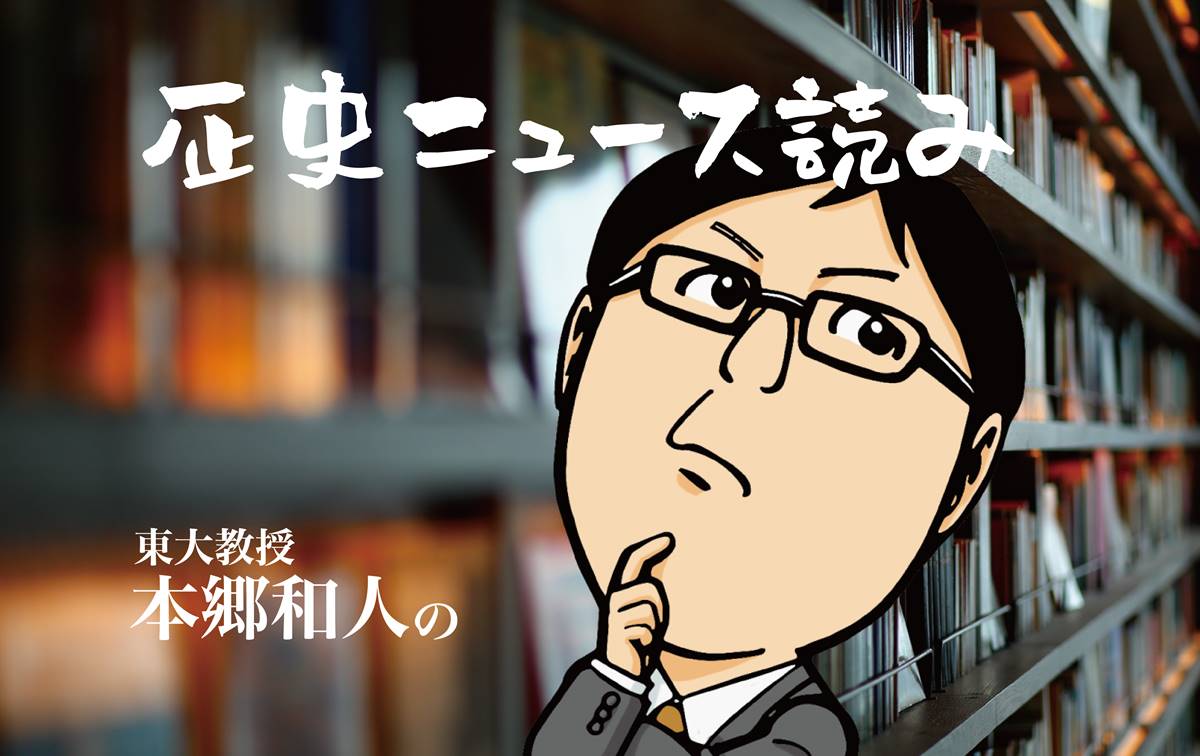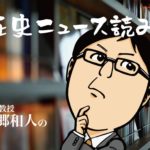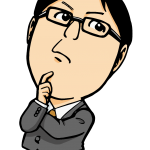2017年大河ドラマで柴咲コウさんが熱演していて話題の井伊直虎。
昨年末に突如として「直虎=男性説」が発表されて以来、ドラマの人気が高まる一方、依然としてその疑問はくすぶったまま。
スグに結論が導かれることはないかもしれないが、歴史ファンの心をざわつかせていることは間違いないであろう。
この問題、歴史学から考察すると、いかなる結論がより自然であるのか?
いったい直虎は男性なのか、はたまた従来の説通り女性なのか。
東京大学・本郷和人教授に考察していただいた。
※以下はこれまでの記事です
-

直虎は男か女か?歴史学から考察だ~東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
-

直虎の男説を追う~女説の根拠は? 東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
-

花押無き「次郎法師黒印状」と直虎生年の謎~東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
【直虎男性説これまで考えたこと】
◆『井伊家伝記』は資料的価値に疑問がある。古文書の分析こそが信頼できる。
◆井伊直盛は20代後半に子どもをもうけた。
◆井伊直盛が戦死し、井伊直親が自害した後、その子どもである次郎法師は井伊谷の領主として機能していた。
さて、これがどう続くか?
姫「なによ。なんか落ち込んでるわね」
本郷「うん。ぼくが書いたものをパクリだと主張するネットのページを見つけちゃってね」
姫「あらら。それはまた、たいへんね。将棋の三浦九段みたいね」
本郷「そんなすごい人とは比較にならないけど、本質的には同じかな。誤解を解いておきたいんだけれど、まず、パクリではない。ぼくが言いたいのは、古文書を読もうよ、これだけなんだ」
姫「今まで書いてきたことは、古文書を正しく読めば、無理なく導き出せる推論である、ということね」
本郷「そう。そこにはウルトラC的な発想はないんだ。歴史学に従事する人なら、まず順当にたどり着ける平凡な結果なんだね。逆にいうと、ことさらパクる必要もまた、ない。この記事には本郷和人としての個性はありません、だから本郷の研究業績にはなりません、で全く構わない。ただ、歴史学のちゃんとした手順を踏むと、井伊直虎はどう捉えられるか、ということが分かって欲しいだけなので」
姫「じゃあ、そういうことで、先に進みましょうか」
本郷「さて、切り替えていこうね。ではいよいよ『蜂前神社文書』の永禄11年11月9日、徳政の実施を命じる文書ね。これは関口氏経と井伊直虎が連署して発給している直状。『直虎』の名が明記され、花押の形状が分かる唯一のものだ。それから、署判の右上に小さな字で『次郎』とある」
姫「徳政令が出る経緯は分かっているの?」
本郷「『蜂前神社文書』にはこの徳政令が出される経緯を説明する文書が数点あるんだ。それを読むと井伊次郎が井伊谷を治める領主であることが分かる」
姫「それはどうして?」
本郷「たとえば同じ8月4日の日付をもった書状が2通あって、『早く徳政令を出せ』と催促している。文面はほぼ一緒で差し出し人は関口氏経。1通は『井次』、すなわち『井伊次郎』あて。もう1通は『伊井谷 親類中 被官衆中』あて。となると、年次は永禄11年となる。井伊次郎は井伊家の当主。親類とは井伊家の一族、被官とは井伊家の家来と解釈できるね」
姫「なるほどね。次郎は井伊家の当主なのね。それで、名は直虎ね」
本郷「ここで気をつけるべきは、直盛が信濃守を名乗っているのに、直虎がただの次郎なんだよね。これも次郎がまだちゃんと当主を務められない、成人したて、とかの事態を考えられるんじゃないかな」
姫「ふーん。そうすると、永禄8年に井伊谷を治める『次郎法師』がいて、3年後に『次郎直虎』がいるわけね。二人は同一人物、ということで良いの?」
本郷「幼名がそのまま通称に移行することは普通はないんだけれどね。でも、両者が別人である可能性はもっと確率が低いんじゃないかな。ぼくは次郎法師が元服し、『井伊次郎』、則ち直虎になったと考えるのが自然だと思うよ」
姫「なるほど。あなたは次郎法師と井伊次郎が別人、という説には賛同しない、ということね」
本郷「そういうこと」
姫「じゃあ、改めて、核心の部分を尋ねましょう。あなたは直虎が女性だと思うの?男性だと思うの?」
本郷「それは逃げたいな。NHK出禁、とかになったら、目も当てられない」
姫「ここまで来て、それはずるいわよ」
本郷「うん。たしかにそうか……。でもさあ、パクリ疑惑をかけられたり、出禁になる恐怖におびえたりしながら、なんでたいしたカネにもならないのに、ぼくはこんなことをやってるのかなあ?」
姫「お金や名声じゃないわよ。研究者は真理の追究が使命でしょう? びびってないで、しっかりして。それでも地球は回っている、よ。ガリレオに恥ずかしいと思いなさい」
本郷「うーん、まあ歴史研究という立場から腹をくくるか……。あのね、ここまで『井伊家伝記』が信用できないということは、この資料だけが説く『直虎=女性』説は考え直すべきかもしれない。そう思わざるを得ないんだなあ、これが」
姫「つまりは、男性だった、ということね。あなたが思うに、直虎はお・と・こ!」
本郷「いやいや、あんまり大きな声を出さないで……。ごくごく普通に、オーソドックスに歴史資料を読んでいくと、その可能性が高いなあ、ということだね。ぼくが子どもの頃だから、50年ほど前かな、八切止夫という作家がいた。彼は上杉謙信は女性だった、と力説して有名になったけれど、じゃあ客観的に謙信が女性だったとする研究者はいないよね。『謙信=女性』説はあくまでも、フィクションとして楽しむわけだ」
姫「すると、あなたは『井伊家伝記』は八切止夫だったかも、というわけね」
本郷「歴史解釈で大切なのは、特別に変わったことはやらない。普通に解釈できるなら、それが一番だ、ということかな。そうすると、井伊次郎直虎という人がいて、その人物が女性だと想定するのは、相当にヘンテコなことでしょう」
姫「まあ、そうよね。女性の名前では、ほぼないわよね」
本郷「文書に井伊次郎直虎と出てきたとして、それが女性かも、と疑ってかかることはほぼない。性別を考慮することは無意識のうちに排除される。男性だと考える方が無理がないわけで、だったら、それでいいんじゃないかな」
姫「ふーん。じゃあ聞くけど、田沼則子さんっていったら、どう?」
本郷「え? たぬま・のりこさん、でしょ? 女の人じゃないの?」
姫「それがねー、これが男性なんだな。たぬま・ただし、さんなのよ。この方の芸名は三木のり平。昭和期のコメディアンね。『ごはんですよ』桃屋さんのCMで有名よね」
本郷「ええー、そうなんだ。いやな実例を知ってるね。特別な事例もあるから、直虎が女性でもおかしくないっていいたいわけだね。でもさあ、世の中に絶対、というのはないわけでさあ」
姫「直虎が男性だと納得させたいなら、なぜ『井伊家伝記』は、その直虎を女性だと説いたか。それを考えるしかないわね。そこがきちんと説明できないと、『直虎=男性説』は 説得力を持たないんじゃない?」
本郷「そうかなあ? だって、もう一度言うけど、直虎という名前の女性がいた、という方が断然、確率の低い話だと思うんだけれどね」
姫「でも、繰り返すけれど、田沼則子はれっきとした男性なのよ」
本郷「……わかったよ。考えがないわけじゃない。それはまた次回にお話ししましょう」
姫「はい。期待しないで待つことにするわね」
-

直虎女性説は『井伊家のタブー』から?東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る