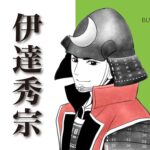明治三十七年(1904年)1月15日、元二本松藩主の丹羽長国が亡くなりました。
天保五年(1834年)生まれですので、幕末から日露戦争の直前までの時代に生きていた人ということになります。
それだけでもなかなか苦労の多そうな感じですが、彼の場合、さらに一風変わった苦労もしていました。
順を追ってみていきましょう。
奥羽越列藩同盟の一員で新政府軍に敗北
長国は、24歳のときに家督を継いで二本松藩主になっています。
そのとき安政五年(1858年)、まさに幕末の激動の中でのことで、長国自身も幕府から京都の警備を命じられたことがあります。
領地が近い上に役目も似ている松平容保とは、いろいろと関わっていたかもしれませんね。
-

松平容保の最期は悲劇だったのか?会津藩・孝明天皇・藩祖に捧げた誠実な生涯
続きを見る
そして戊辰戦争が始まると、二本松藩は【奥羽越列藩同盟】の一員となりました。
彼らは西軍を相手に和睦を拒否され、ドンパチが勃発。
-

戊辰戦争のリアルは悲惨だ|生活の場が戦場となり食料を奪われ民は殺害され
続きを見る
二本松藩では漢学重視で蘭学があまり浸透しておらず、それに伴って近代化も進んでいませんでした。
当然、装備は旧式ばかりです。
そもそも東北=人口が少なく=兵も足りないため、老人や少年(二本松少年隊)も駆り出されてたほどでした。
よくまぁそんな状態でケンカの売り買いなんて……と現代の我々は思ってしまいますが、それが当時の人の意地とか根性というものなのでしょうね。
結果、東北諸藩の例に漏れず、二本松藩も負けてしまいました。
-

奥羽越列藩同盟は何のために結成?伊達家を中心とした東北31藩は戊辰戦争に敗れ
続きを見る
二本松藩は最終的に降伏し、長国は隠居・謹慎を命じられた上で領地も半減されるというキツイ処分を下されます。
跡を継いだのは養子の長裕。
長裕は上杉家から丹羽家の養子になった人で、血を遡れば吉良上野介義央に行き着きます。
政府の許可を得て東京で遊学するなど、意欲を持っていたようで、新しい時代の殿様(藩知事)に似つかわしい人物でした。
えっ、わし? 67歳だけど今さら家督を?
しかし、長裕は37歳の若さで死んでしまい、跡を継いだ実弟・長保も若くして死亡。
そのため謹慎を解かれていた長国が再び家督を相続することになります。
藩は廃止されているので厳密に言えば藩主ではなく、家督を継いで子爵を授けられております。
これを知った上で晩年の長国の写真(以下の画像参照)を見ると「え、ワシが?」と言っているように思えてきます。
晩年の丹羽長国/wikipediaより引用
当時67歳なのでそう嘆きたくもなったのでしょう。
というより「カメラ」がまだまだ珍しい時代ですから、「これでホントにワシの姿が絵になるのか?」といった心情だったかもしれません。
★
こうして数奇な運命を辿り、2年ほど再び当主を務めた後、長国は亡くなります。
その間、新たに宇和島伊達家から長徳を養子に迎え、長国が亡くなった後の家督相続はスムーズに行われたようです。よかったよかった。
-

政宗長男・伊達秀宗の切なくてイイ話~もう一つの伊達家が四国に誕生した理由
続きを見る
江戸時代にも「藩主が早死にしたため、幼いその息子が後を継ぎ、ご隠居が後見した」という話はよくありますが、ご隠居が返り咲いたケースはそうありません。
時代の移り変わりの中で役目を全うすることができ、長国もホッとしていたでしょうね。
あわせて読みたい関連記事
-

戊辰戦争のリアルは悲惨だ|生活の場が戦場となり食料を奪われ民は殺害され
続きを見る
-

奥羽越列藩同盟は何のために結成?伊達家を中心とした東北31藩は戊辰戦争に敗れ
続きを見る
-

政宗長男・伊達秀宗の切なくてイイ話~もう一つの伊達家が四国に誕生した理由
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
国史大辞典
安岡昭男『幕末維新大人名事典』(→amazon)
丹羽長国/wikipedia
二本松の戦い/wikipedia