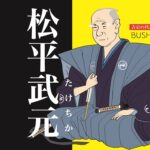こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【徳川治済(一橋治済)】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
定信が追い出された真の理由
「例え朝廷や皇族であっても、敬称をつける決まりに例外はない!!」
尊号一件でそう強調してしまった定信は、当然ながら治済を「大御所」と呼ぶわけにもいかなくなってしまいました。
もしここで「どうぞどうぞ」と言ってしまったら、朝廷から「お身内には随分優しいですなあ」と言われてしまいます。
そんなわけで定信は「大御所というのは将軍位に就かれていた方が名乗るものですから、治済様には当てはまりません」と言い続けることになります。

松平定信/wikipediaより引用
結果、治済と家斉を完全に敵に回してしまった定信は、幕府の中枢から追われてしまいました。
「白河の 魚の清きに 住みかねて 元の濁りの 田沼恋しき」
なんて狂歌があるくらい、寛政の改革も成功していたとは言いがたかったですしね。
定信は白河藩主としては成功を収めているので、領民にとってはよかったかもしれませんけれど、いかんせん規模の大きな政策立案には向いてなかったということでしょう。
暗躍する治済 圧を受ける家斉
憎き政敵を追い落とした治済は、その後も亡くなるまで豪奢な生活を送りました。
おそらく政治へ大いに口を出し、多大な影響を与えているはずなのに、具体的な逸話がはっきり伝わってこないあたりが、何とも不気味で「怪物」と言われるだけありますよね。
徳川治済の息子である11代将軍・徳川家斉といえば、子沢山な将軍としても有名です。
記録にあるだけで、抱えた側室の数は16人、生まれた子供はなんと55人(53人説も)!
治済から見ると孫に当たりますが、よしながふみ氏の漫画版『大奥』では「豚のように生まれる家斉の子」という、実にひどい台詞で表現されていました。
さすがに現実での治済はそこまでではなかった……と思いたいところ。

徳川家斉/wikipediaより引用
そのうち無事に育ったのは28人でした。
それでも養子先や嫁入り先を見つけるために(主に幕閣の)散々な苦労があり、タダで送り出すわけにもいかないので持参金その他諸々に費用がかさみ、江戸幕府のお財布事情がさらに怪しくなっていきます。
家斉もその辺の事情を知っていたはずですが、それほど漁色にふけったのも、父に逆らえないストレスからだったのかもしれません。
松平定信もこの件に関しては懸念を抱き、大奥泊まりの回数などにも口を出していたとか。
それによって余計に家斉の反感も買っていたと思われます。
定信は禁欲的な人でもありましたので、家斉の気持ちが理解できなかったのかもしれません。
家斉は寛政の改革中に「あまり大名たちに負担をかけないように」と言える人でもあるから、将来の懸念について話をしていれば敵対しなかった可能性もあるんですけどね。
もしも家斉が定信と敵対しなかったら、先に追い落とされたのは治済の方だったかも……。
定信が失脚した後も、改革に携わっていた幕閣の一部は”寛政の遺老”と呼ばれて用いられていましたので。
家斉は一生のうちに数回風邪を引いたくらいで、めちゃくちゃ頑丈な人でした。
外出がままならないのは将軍やお殿様の定めとはいえ、政治すら自分の意志を出せないというのは、相当窮屈に感じていたでしょう。
治済からも「子供をたくさん作って、跡継ぎはもちろん徳川の血筋全体をウチで固めるように」とも言われていたようですが……。
「娯楽が少ないと夜頑張る」というのは、現代のあっちこっちの国でも同じ。
家斉がただの女好きのバカ殿だったわけではない……と思いたいところです。
みんなが読んでる関連記事
-

『べらぼう』なぜ賢丸(定信)と意次は激しく対立するのか?背後でほくそ笑むのは一橋治済
続きを見る
-

子供を55人も作った11代将軍・徳川家斉(豊千代)は一体どんな人物だったのか
続きを見る
-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察
続きを見る
-

『べらぼう』徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍
続きを見る
-

『べらぼう』知保の方は史実でも田沼意次を憎んでいた?正気を失った彼女は何をする?
続きを見る
-

松平武元『べらぼう』で石坂浩二演じる幕府の重鎮は頭の堅い老害武士なのか?
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
山内昌之『将軍の世紀 上巻 パクス・トクガワナを築いた家康の戦略から遊王・家斉の爛熟まで』(→amazon)
国史大辞典
日本人名大辞典