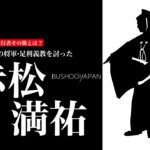血塗られた政治史――特に中世は凄まじく「何がどうしてそうなった?」としか言えない出来事があります。
嘉吉元年(1441年)6月24日、室町幕府の六代将軍・足利義教(よしのり)が暗殺された【嘉吉の乱】もそのひとつではないでしょうか。
初代の足利尊氏が征夷大将軍に任じられたのが暦応元年(1338年)。
幕府ができて百年ちょっとで早くも先が危うくなってしまったわけですね。
しかし、経緯を見てみると「そりゃ反乱したくもなるわ」と思いたくなってくる事情があるのでした。
※以下は足利尊氏の関連記事となります
-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様
続きを見る
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
くじ引き将軍
キーマンとなるのは、足利義教と赤松満祐(みつすけ)という人物です。
-

将軍暗殺に成功しながら滅亡へ追い込まれた赤松満祐~嘉吉の乱後の末路とは?
続きを見る
赤松家は室町幕府の中でも四職(ししき)と呼ばれていたお偉いさんの家柄で、領地もたくさん持っていました。
【四職】侍所のトップに就ける家
赤松氏
一色氏
京極氏
山名氏
【三管】幕府のNo.2・管領に就ける家
細川氏
斯波氏
畠山氏
※併せて【三管四職(さんかんししき)】とも言ったりします
しかし、大きな家にはよくあることで、領地分配などを巡って本家と分家の間に密かな確執が勃発。
一触即発の状態に火をつけてしまったのが義教です。
-

足利義教は“くじ”で決められた将軍だった?万人恐怖と呼ばれた最悪の治世
続きを見る
というか、将軍家でもずっと前から火種はくすぶっていました。
ナゼかと申しますと、五代将軍・足利義量(よしかず)が病弱で、四代・足利義持がずっと政治を執っていたのですが、この両氏が二人とも六代目をはっきりさせないままこの世を去ってしまったからです。
困った幕府の重鎮たちは「ここは神様に決めていただこう」ということで、義持の弟たち四人の名前をくじに書き、岩清水八幡宮でくじ引きを行いました。
そこで選ばれたのが義教だったのです。
このせいで義教は「籤引き将軍www」などと揶揄されましたが、当時はこういう揉め事になった場合、神仏のご意志ということにして事を穏便に収めようとするのが常。
最初から義教と決まっていて、あくまでクジは形式的にやったのでは?という見方があり、そっちの方が自然な気がしますね。
-

史上最も地味な将軍は足利義量か?酒を飲みすぎて19才で急逝というのは本当?
続きを見る
-

4代将軍・足利義持は地味だけどハイスペック?父義満を乗り越えて
続きを見る
突然、暴君に変身!人心は離れ
かくしてクジで将軍になった義教。
当初はともかく、しばらくすると暴君振りが目立つようになってきます。
大名の家督相続に口と手を出して、自分に従う者だけを当主に据えたり。
比叡山と大ゲンカして僧侶24人が焼身自殺する騒ぎになったり。
恐怖政治の見本のようなことをし始めたのです。
当然人心は離れ、それをカバーするためにますます義教は苛烈になるという悪循環――。
当時のとある皇族が「万人恐怖」とまで書いているくらいですから、朝廷も庶民も戦々恐々としていたことでしょう。
そして義教の乱暴振りが、ついに赤松家にも及びます。
このとき赤松家の当主が満祐であり、例にもれず義教に疎まれてしまっていました。
義教は赤松家にとっては分家筋に当たる貞村をひいきし、満祐の弟・義雅の領地を無理やり取り上げ、貞村に与えるという暴挙を働くのです。
この時点での満祐は、義教に愛想をつかして隠居しただけでした。
しかし「次に粛清されるのは満祐だろう」という噂があったともいわれています。
義教はホントに暴君の見本みたいな人で、あっちこっちの家の人を誅殺していましたので、完全にデマと言い切れないのがなんとも。
※続きは【次のページへ】をclick!