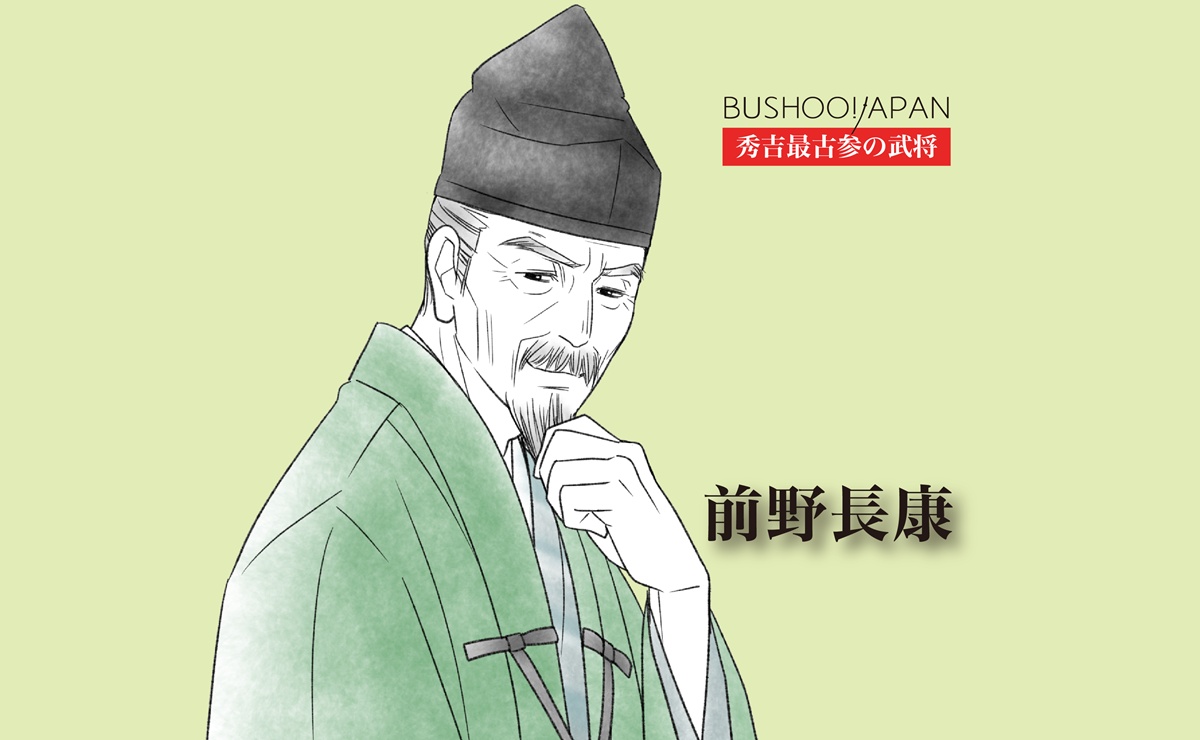前野長康という戦国武将をご存知でしょうか?
元々は織田信長より家格の高い織田家に仕えていた武将であり、その後は秀吉の下で働き、あの蜂須賀正勝とも並ぶ最古参の存在でもありました。
大河ドラマ『豊臣兄弟』でも早くから活躍してもよい人物であります。
しかし、今のところ長康のキャスティングは発表されておりません。
長康の最期は、なかなか刺激的な事件に巻き込まれるため、見どころは作れるはずですが、そこまでは放送されないのか?とも思ったり……。
いったい前野長康とはどんな存在だったのか――本記事でその生涯を振り返ってみましょう。

絵・小久ヒロ
元は岩倉織田氏の家臣だった
前野長康は大永八年(1528年)、前野右京介宗康の次男として生まれたとされます。
父の宗康は、岩倉織田氏(織田伊勢守家)三奉行の一人。
岩倉織田氏とは、織田氏の宗家にあたる家柄です。
その分家が清洲織田氏(織田大和守家)であり、その家臣の、さらに分家が織田信長の家(織田弾正忠家)でした。
つまり、本来であれば長康の方が織田信長より目上の出自ということになりますね。

信長甲冑イメージ/絵・富永商太
しかし、一番の問題は当主のやる気と能力でした。
当時の岩倉織田氏は、織田信賢(のぶかた)が当主。
戦国の荒波に呑まれて、岩倉織田氏は急速に勢力を弱めている最中であり、永禄元年(1558年)に信長が岩倉城へ攻め込んだとき、すでに前野長康は弾正忠家についていたとされます。
しかも、このときの功績で40貫文の土地を獲得していました。
一方、岩倉織田氏は翌年の永禄二年(1559年)、信長によって滅ぼされています。
せめてもの情けでしょうか。織田信賢は殺されずに追放で済まされ、その後の行方や動向は不明となってしまいました。
信長がつけたあだ名は“駒右衛門”
前野長康の出自や血縁関係には諸説あります。
ただし、弾正忠家の中で信頼を得るまでには、そう長くかからなかったと思われます。というのも若い頃と思われる時期に信長との逸話が2つもあるのです。
一つは通称に関するものでした。
長康は、信長に乗馬の才能を褒められ、”駒右衛門”という名を賜ったとされます。
信長は気に入った人にすぐあだ名をつける癖があり、秀吉の「はげねずみ」や、明智光秀の「きんか頭」と比べて、かなりマトモな名前を貰ったと言えるでしょう。
そこまで信長に言わせるなんて、長康の馬術がぜひ見たいものです。
もう一つは『信長公記』に載っているお話。
ある年の7月18日、信長が催した盆踊りで「弁慶に扮した面々」の一人として長康の名前が出ています。
「彼らは器用に扮装していた」とあるため、おそらく気合を入れて衣装や薙刀などを用意していたのでしょう。
単に参加しただけでなく、コスプレまでバッチリこなすとは、普段から生活に余裕があったことを思わせますね。
同じく岩倉織田氏の家臣だった山内一豊が、放浪中に長康を頼ったこともあります。

山内一豊/wikipediaより引用
長康の立場が早めに安定していたであろうことが、一豊の行動からもうかがえます。
蜂須賀正勝と義兄弟
経緯や時期は不明ながら、前野長康は蜂須賀正勝と義兄弟の契りを結んでいたともされます。
その縁が影響しているのでしょう。正勝と同時期に秀吉の与力になったとされ、真偽の程は不明ながら墨俣築城などでも活躍したされます。
おそらく正勝と同時期に秀吉に仕え始め、その後ずっと秀吉軍の一員だったことは確かでしょう。
にもかかわらず、前野長康の知名度だけ低いと思いません?

蜂須賀正勝/wikipediaより引用
長康に武働きがないわけではありません。
永禄十一年(1568年)5月には箕作城攻めで夜襲を成功させたり、元亀元年(1570年)4月の「金ヶ崎の退き口」でも織田軍に貢献したり、際立ったエピソードはなくとも堅実に活躍。
元亀元年(1570年)姉川の戦い後には、秀吉が横山城代に任じられた際、長康が城番の大役を任されています。
当時の秀吉与力としては、これ以上ない立場だったでしょう。
ならばなぜ知名度は低いのか?
※続きは【次のページへ】をclick!