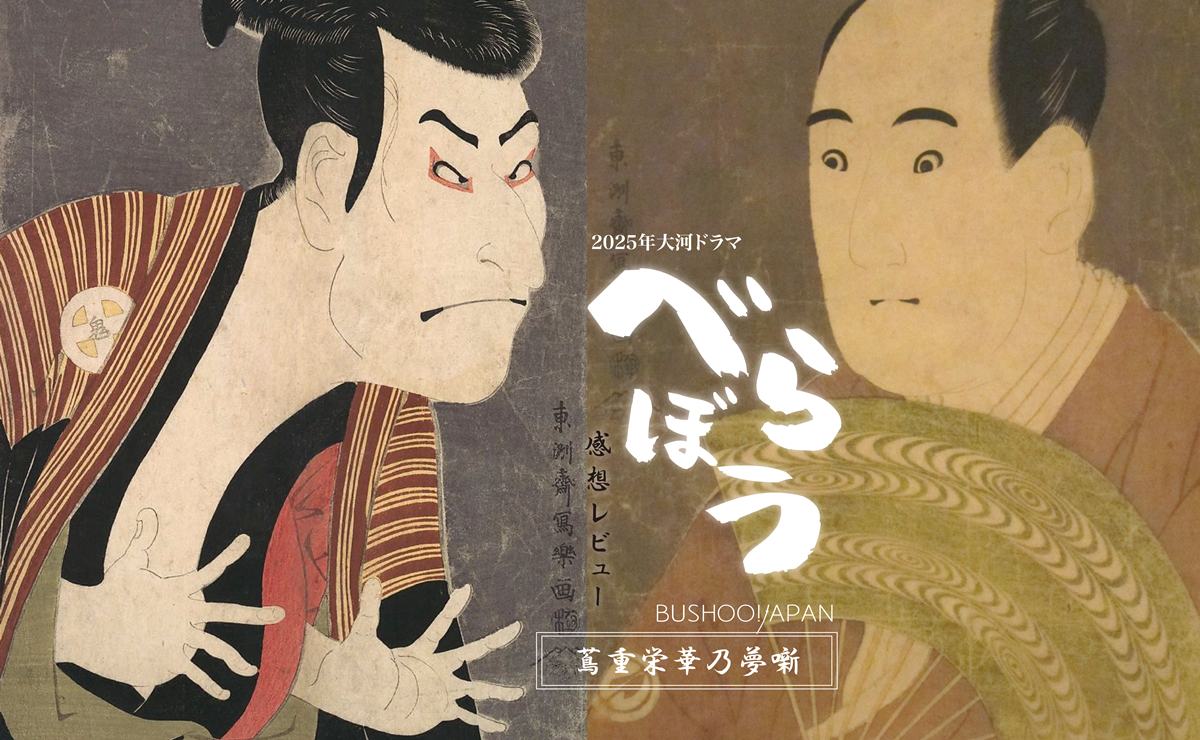松平定信から一橋治済に対する「仇討ち計画」を打ち明けられた蔦重。
帰りを待っていたおていさんに、源内がいたどころではないと説明します。
だとすれば、あの作品は誰が書いたのか。
当然の問いかけに対して狐だと誤魔化そうとするけれど、てい相手に誤魔化しは通用しません。
蔦重は全てを説明することになります。
定信の仇討ち計画
松平定信から仇討ちの提案を持ちかけられたとき、蔦重は苛立ちました。
てっきりあの作品は源内作かと思ったら、三浦庄司の話を元に定信が書いたものだったのかよ――。
蔦重は、あくまで源内先生に会いにきたのであって、彼らに用は無いとして帰ろうとします。
源内の仇討ちをしたくないのか?と定信が持ちかけますが、蔦重は「源内にあったこともねえくせに!」と怒鳴ります。
定信は、蔦重が本物の陰謀論者であったことに驚いているように思えます。まぁ、そりゃそうですわな。

松平定信/wikipediaより引用
それでも悪党成敗したくはないか?と迫ってくる柴野栗山。
長谷川平蔵や三浦庄司、高岳まで天誅を下すと言い出して、もはや大河でなくて民放時代劇みてえなノリになっちまってますね。
蔦重は真面目に「市井の本屋がそんなことはできない」と答え、強引に帰ろうとする。
と、定信が潜ませていた武士が一斉に襖を開けました。
なぜ、そうまでして蔦重に協力させたいのか?
いったい何をやらせるつもりなのか?
定信は、市井に源内生存説を流して欲しいのだそうです。
今回のシーンを振り返りますと、蔦重の怒り方からポピュリスト的ないやらしさが理解できて来ました。
後に蔦重は、定信から莫大な金も受け取ります。
権力と結びついて利益を得ているとも言える。清廉潔白とは言い難い。
それでも強い口調で権力者に刃向かえば、スカッとする人は一定数いるでしょう。
理詰めで話し合うよりも、ギャアギャアとキレる姿を見せつける方が支持を得られることもあります。
ポピュリストの手口でさあね。きっちり手続きを踏んで権力と対峙する人よりも、やたらとイキリ散らすパフォーマーの方がウケは狙える。
最近の蔦重にはそんな狡猾さが見え隠れして、どうにもうんざりさせられるのです。
パラレルワールドの物語
それにしても……。
どうしちまったんでえ、定信!
確かに版元と公儀の攻防は史料に残りにくいので、ある程度の潤色はできまさぁ。
しかし、これだと定信が大馬鹿者と言いますか、大変らしくねえことをしていませんか?
こんな復讐劇はとにかく隠密にやらねえとまずいでしょう。それなのに口も軽そうで謀略に向いていない蔦重を巻き込むのは悪手も悪手。
先週から急展開を迎えた本作の実質的最終回は、やはり前々回の43回と言えますな。
皆さんも、なんだか『べらぼう』の世界観が急に変わった気がしませんか?
今はもうパラレルワールドの物語と思うことにしやす。
蔦重を無理やり巻き込む動機が、定信自身というよりも、作劇上の都合、主人公補正にしか見えず、しらけることこの上ないのです。
なんせ蔦重は周囲をろくに確認せず、帰宅するなり、ていに全部語りますからね。隠密に全く向いていない。
ていも早産のあと、どうにも知略が低下しているのか、夫に対してろくに反対もしないし、懸念事項の確認すらしない。
「悪党を討つ」といっても、相手が誰かすら確認してませんからね。
しかも、陰謀論者らしいノリでどんどん盛り上がってゆく。
陰謀論にもスペクトラムというもんがあるんですが、あまりに吹っ飛んでる。こうしてどんどん悪化するんだな、という感想を抱いてしまいますぜ……。
何がひどいって、十返舎一九を巻き込む前提にしているんですよ。
夫妻は当事者の意見を確認しないで話を進めますよね。滝沢瑣吉が出てこなくなった理由がわかります。
婿入りもあるっちゃそうですが、それだけでもないとみた。理詰めでないと、あいつは納得しねえんですよ。こんな杜撰で馬鹿馬鹿しい計画には、まず乗ってこねえどころか、否定しかねませんからね。
夫妻は乱世舞台の大河なら、初夏には謀殺されてしまうでしょう。
それに、実在した版元よりも迂闊な気がします。
江戸時代後期、歌川国芳の風刺画を出した版元なんて、そりゃもう規制に対して用意周到でした。
本作は、43回放送まで江戸文化を肯定的に描いてきたのに、最後の最後で思い切りバカにしてきた気がする。いったい何を見せられているんでしょう?
江戸三座も封鎖された
九郎助稲荷が「江戸三座」の閉鎖を語っています。
江戸三座とは、幕府から興行の許可を得ていた「中村座・市村座・森田座」のこと。

歌川広重『東都名所 芝居町繁榮之圖』 /wikipediaより引用
普段は人で賑わっているはずの町並みが侘しく、なんだか蔦重もおかしい。
話がつながっていません。前回、役者絵が少なくなっていることに蔦重は気づいている。
となりゃ、江戸三座の締め付けやら何やら、もっと気づいていてもよいはず。何かうまくつながっておりません。
そこには長谷川平蔵と仙太もいて、葵小僧の話を始めました。
彼ら盗賊団の装束が芝居町に頼んだものだったそうで、しかもそれを注文していたのが“武家に詳しい女”だったというのです。
この女とは、大崎のことですが、江戸城大奥といった警備が厳重な場所にもいた彼女がそれほど気軽に出掛けられましょうか? 代わりの人を派遣してもよいと思います。
それと平蔵、誰が聞いているかわからねえ蕎麦の屋台で、ンなこと大声で喋ってんじゃねえぞ。
どういうセキュリティ意識なんでえ! カフェで機密情報入りノーパソおっ広げて仕事して、画面ロックせず離席する。そんなダメ刑事の大江戸版じゃねえか!
あとで始末書提出、情報研修受講な。ったく、こりゃセキュリティ担当者、情シスの精神が相当やられてんじゃねえか?
実は世の中には特殊な店ってものもあり、関係者以外が誤って注文すると緊迫感か溢れるような、偽装をしているところもなくはない。しかし、門之助がフラッときて注文できるからには、どうもそういう仕掛けもなさそうですね。
以降、蔦重と門之助の会話は、なんだか説明的で、三座が潰れたから曽我祭をするという話に持っていかれます。
そうした展開だけでなく、背景もエキストラが少ない。こういう場面では台詞はなくとも、役者とわかる人物が背景にいたものですが、会話する二人をアップにしていて背景が目立ちません。
『べらぼう』の魅力はカメラを引いて、動く浮世絵のような世界観まで見せることにあったはず。その魅力が失せちまっているようにも感じてしまう。
何がなんでもド派手に盛り上げ、写楽という花火を打ち上げたい。祭りにするという意図はわかりやすぜ。
しかし、どうにも強引でねえ。
三座閉鎖で重要なのは、三座と契約関係にあった勝川派と関係が切れて、役者絵という最大の売れ筋が独占状態でなくなったってこと辺りだと思うのです。
その辺りの説明を前回にしたということにしたいのでしょうが、説明不足ではないでしょうか。
史実をつなぎ合わせてプロットにするのではく、作り手の都合に史実を無理矢理当てはめるような、そんな歪みが出てきているように思えるのです。
その辺を全部いちいち説明される蔦重も、若けりゃともかく、そんなこと知らんかったのかと思ってしまうんです。吉原しか見てなかったんですかい?
ここで久々の熊吉と八五郎の妄想へ。
役者絵を見て「平賀源内だ!」とはしゃぐ二人が脳内再生されますが、これもおかしくないですかね。

平賀源内/wikipediaより引用
源内に画才はない。絵師として名を馳せているとは言い難い。
それなのに見た瞬間そういう反応になるでしょうか?
誰もが皆、蔦重のように源内に対して思い入れがあるわけではない。若い人は知らないでしょうし、知っている層も「ああ、あのインチキだったエレキテルの山師か」となってもおかしくはない。
平賀源内の知名度は、後世で高くなったようなところもあるわけです。
要は業績が中途半端なんですね。
「江戸のダ・ヴィンチ」と言われても、当時の江戸っ子はダ・ヴィンチのことなど知りませんから。
「プロジェクト写楽」
さて、そんなわけで『プロジェクト写楽』の始動です。
やっちまいましたね……写楽の正体でびっくりさせる展開って「これゼミで習ったやつだ!」となるパターン。
今どきこれで意外性を狙うんですか? 一体いつの時代なんでしょう? プロットを読むだけで悪い意味で鳥肌が立ちます。
写楽の正体で驚かせるのって、それで史実より面白くなければよいのでしょうが、そうならず陳腐にすらなるのが困りものなんですよ。
しかも「思いっきりふざけたくねえですか?」と呼びかける蔦重はなんなのでしょう。傾いた耕書堂を支えるみの吉あたりの気持ちを考えると、胸が痛くなってきます。
学問吟味試験勉強中の太田南畝は早速呆れています。
そのふざける内容が、役者絵を源内風味で描くんだそうで。
勝川春章の没後、役者絵がパッとしないという事情も語られます。
その恩人への追悼もなしに、それを逆手に取れると言い出す蔦重があまりに浅ましいと言いましょうか。
そしてこれも浮世絵の謎の一つであり、史実の蔦屋重三郎に対する評価を難しくする点なのですが、このころはまだ勝川春朗、のちの葛飾北斎を起用しないということでしょう。
かつて写楽の正体については「葛飾北斎説」もあったものでした。
そんな北斎の才能を見落とすという蔦重のセンスのなさは、ドラマでも再現されているといえばそう。
しかも絵心のない源内を持ち出してくることで、決定的にダメなヤツになってしまいます。
未来に輝く才能は見通せず、己が若い頃に培ったノスタルジー頼りだと示していることですから。
定信の依頼だからだという言い訳は用意されているといえばそう。しかし、田沼意次までならともかくとして、ああもやりあった定信の走狗になるというのも、どうにも冴えない話ですな。
そんな雑な思いつきに、恩着せがましく皆を乗せようというのもよくわかりません。
そしてここで、蔦重が源内の蘭画『西洋婦人図』を見せます。
さらには絵に描いた餅をペラペラと語りだす。
絵が売れる。話題になる。芝居にも人が戻る。しかも描いたのが死んだはずの平賀源内だ!
なんでしょう、このオカルトを売り込むような口調は。
神秘のブレスレットを身につければ宝くじも当たる、モテモテになる!
そんな広告の煽りにしか思えねえんです。
あるいは蔦重が悪徳広告代理店の営業マンにも思えてきたぜ。
象徴的なのは、ここで滝沢瑣吉が乗り込んできたこと。
彼は源内生存説は否定してきまして、みの吉に連れてゆかれます。
わかるぜ。滝沢はこういうことには乗っかってこない性格ですんで。曲亭馬琴を守るところだけは肯定したいところですね。
滝沢は秘密を漏らしそうだから仲間に入れないと蔦重は説明しますが、そうでなく全力で場の空気を読まずにぶち壊してくるからそうしているように思えます。彼は現実主義者なんでね。
すると朋誠堂喜三二から雅号は「しゃらくさい」でどうか?という案が出てきます。
なんだか気持ち悪いのは、死んでいるはずの源内の思いを勝手に代弁しているところですかね。
もはや完全にオカルトです。霊言シリーズ「平賀源内」に突っ込んできていて、そりゃあ滝沢はこんなもん乗っからねえわな。
それにしても、江戸時代を代表する文人を、まとめてオカルト陰謀論者集団にされて、あっしゃぁどうすりゃいいんですかい!
「写楽!」
と皆で同時に叫ぶところは本当に辛かった……。
※続きは【次のページへ】をclick!