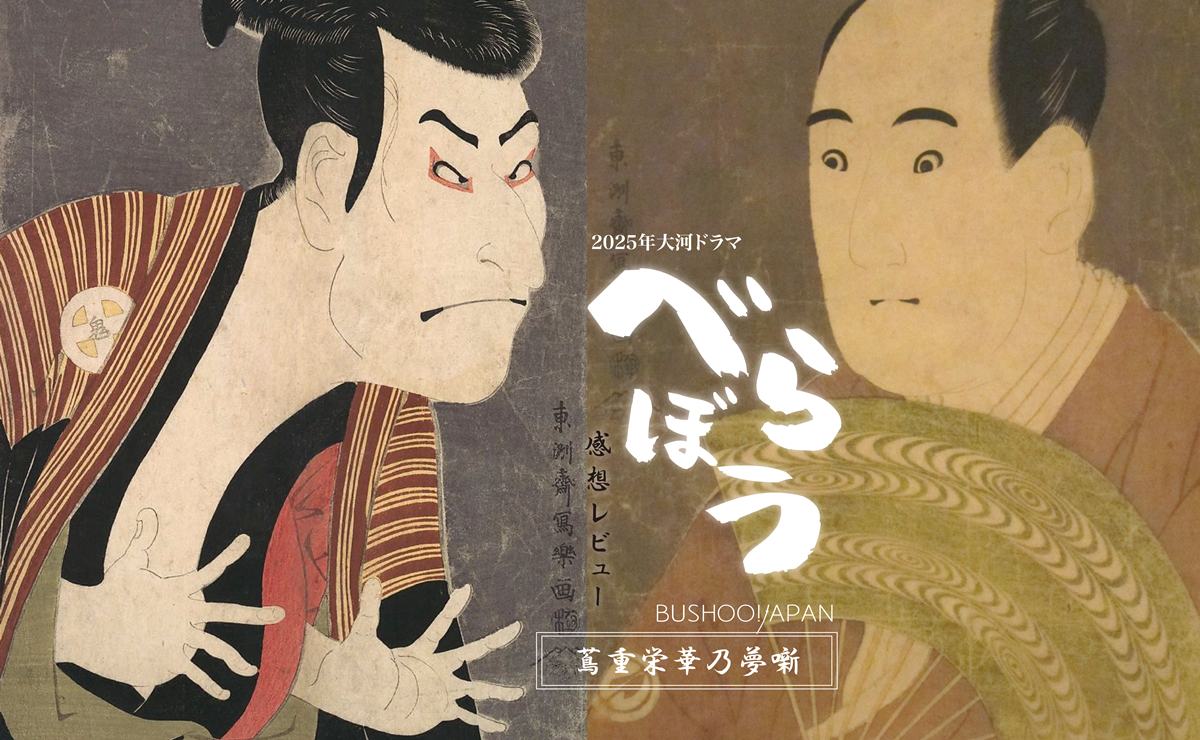こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第45回その名は写楽】
をクリックお願いします。
壁になりたい女子がカップリングを修復する
蔦重は、源内風はいったん横に置いて(んなモンねえからにゃ、はなから横に置くも何もないんですが……)、似絵から始めると言い出しました。
そこからかい! と、西村屋与八と万次郎が聞いたらツッコミを入れそうな話です。二人は今ごろ歌川豊国に色々と注文を出しているでしょう。
ていと蔦重は、今さらながらに歌麿の絵を再評価しています。そしてアリバイのように、蔦重の評価が足りないと吉原で暴れる歌麿の姿が出てくる。
いや、歌麿は、蔦重以外の版元でも傑作を手掛けていますので、これは歌麿本人にも失礼な話ではないでしょうか。
歌麿が自宅で絵を描いていると、ていがやってきました。
そしてブロマンス大河の極みを見せてきます。
下絵だけを預かった『歌撰恋之部』を仕上げたのは、蔦重からの恋文だと言い出しました。
それでいいんですかい?
恋文の往来をしたから通じ合ってハッピーエンドってことで?
ていは、渾身の説得をしますが、染谷将太さんと橋本愛さんが熱演すればするほど虚しいもんがあります。
もしも歌麿写楽説を採用するのであれば、劇中で彼が芝居を見ているといった伏線がなければおかしいでしょう。
役者絵は売れ筋なので、どの絵師も手掛けております。
しかし、劇中の歌麿はほぼ美人画にしか焦点を当てて来ておりません。伏線がちゃんと張られていない。
しかも多くの絵師が写楽について何も語り残していない中、例外と言えるのが歌麿でした。
歌麿は写楽に対してかなりの酷評を残しているのです。
歌麿は描くものの魅力を引き延ばす。写楽は欠点を強調する。俺と一緒にするんじゃねえ!
というように、かなりきつい言い方で批判しており、自分と混同するなと怒っております。これは蔦重への怒りにも思えるところですね。
それをよりにもよって、歌麿を写楽の正体にするって、ほとんど侮辱ではないでしょうか。
ていもおかしい。これじゃ「推しカプを見るために壁になりたいオタクの私」ではないですか。
出家まですると言い出していて、何事かと思いました。江戸時代の儒教規範と、現代の推し活に勤しむ女子の悪魔じみたハイブリッド感があって目眩がしてきやしたぜ。
夫を諌めるおていさんがあっしは好きでした。こんなのもう別人じゃないかと思ってしまいます。
ブロマンス大河であることは理解していたつもりですが、だからといって壁になりたい女子まで出さなくてもよいでしょうに。
『麒麟がくる』の帰蝶、駒、伊呂波太夫はその点わきまえていたものです。
どうしてこんなことをするんでしょう?
それだけは辞めて欲しかった。
MVP:松平定信
ここまできて、彼の評価を決定的に下げるとは思いませんでした。
滅多にフィクションで映像化されない人物でこういうことをされますと、大変困った話ではある。
2023年の大河ドラマ『どうする家康』は、家康以下、人物像が最低最悪の描かれ方でした。それでも数年後には『豊臣兄弟!』もあり、挽回のチャンスはある。
しかし定信はなぁ……。次がいつになるか、全く予測はつきません。それなのに、再来年の小栗忠順以下、幕臣チームが見たら悪い意味で「べらぼうめ!」と吐き捨てそうな描かれ方をしました。
結果的に、定信の策は幕府権威低下につながっているんですよ。
平賀源内は、幕府の法で逮捕し、裁くはずだったにもかかわらず、獄死しました。それが生きているとなりゃ、幕府の司法に穴が空いているということになっちまう。
しかも、一橋治済が悪いという噂が市井に流れたら、その子である家斉の正統性にも疑義が生まれますわな。
結果的に将軍権威が低下しかねないんでさ。
定信はそういう因果関係をふまえず、私怨で市井まで巻き込んでいるように思えます。しかも、蔦重なんて信頼できそうにないし、機密情報を守れる性格に思えませんからね。
史実でも家斉は将軍としては最長、半世紀にもわたる治世において、日光社参もしておりません。
子沢山ゆえ、男子に官位を授けようとして、朝廷に頭を下げて、結果的に価値を上げてしまった。幕末へと向かってゆく思想潮流に一役買ってしまったことは否定できません。
そうした史実を定信にまで絡めるというのはいかがなものか。
敬愛する神君家康公なり、祖父の吉宗がこんな振る舞いを見たら、どれだけ呆れ果てることか。やっちまったなぁ、としか言いようがねえんでさ。
総評
人生で大事なことは全て大河ドラマから学んだ――とは決して申しません。
といっても、学んでいないわけでもありません。
まず今回はこれを引用させていただきます。
「朝令暮改の何が悪い! より良い案が浮かんだのに、 己の体面のために前の案に固執するとは愚か者のすることじゃ!」
『真田丸』真田昌幸より
「朝令暮改」を「君子豹変」に変えてもよいですかね。
この間まで褒めていたのに、裏切られた気持ちになるかもしれませんが、私なりの真田昌幸マインドの発露と思ってください。
昌幸は根性が悪いからコロコロ裏切るわけではない。
真田の領土を守ためには致し方なくそうしたまでのこと。ノリがあまりに飄々としているし、策が痛烈なので誤解されがちですが。
今回、私としては、裏切られた気分で一杯なのです。
ここまでよくも見事に浮世絵を再現するものだと感動してきたのに、最後の最後でやられた! そんな気持ちでいっぱいでして。
写楽は斎藤十郎兵衛説以外ないと私は思っていました。森下佳子先生もそう口にされていたものです。
今どき斎藤十郎兵衛以外を採用するのは、ともかくセンスが悪いうえに古臭い。
関ヶ原の戦いを語る上で、司馬遼太郎由来の「メッケルは西軍が勝つと予測した」と持ち出してくるとか。
あるいは『麒麟がくる』では否定した本能寺黒幕説とか。
持ち出されたら「今どきそれを言うの?」と困惑してしまう。言っている側は古びていることを自覚できずにいたら、ますます辛い。そんな話なんですよ。
もう一点、大河ならではの懸念があります。大河はゆかりの土地が観光を盛り上げることが通例です。
今年も斎藤十郎兵衛ゆかりの徳島ではPR事業をしております。それがこういう空振りをすると、遺恨を残すからやめた方がいい。
勝手な都合でゆかりの地を裏切るのは本当に悪手なんです。おもしろさ以前、信頼性の話であり、大河のブランドを毀損しかねません。
『天地人』では最上義光を出さなかったため、放映後の山形市でのトークショーではかなり痛烈な応酬を受けたとか。
ネットでのエコーチェンバーに籠っていると気づきにくくなりますが、ゆかりの地から嫌われるのは本当にまずい。
強がってSNSで「批判する奴、しゃらくせえ」だのなんだの書き込めば、それを引用したコタツ記事は出来上がりますね。しかしそんなものにどれだけ価値があるのやら。
それに対して、地元の支持は大事ですからね! こんなこと私が言うまでもなく、手練揃いの本作チームは理解していると思っていたのですが。
ただ、それでも通じてしまうのは、浮世絵愛好者がそれだけ少ないということですかね。
浮世絵知識についていえば、海外先行がまだ残っている状況ですし、幕末明治の絵師はまだ評価が低いままです。
それに引っかかるのは、写楽をやたらと持ち上げるというのは、明治以来の脱亜入欧の残滓と、広告代理店臭を感じさせるところなんでさ。
写楽をテーマにした小説や、映画の脚本を手がけた方は「斎藤十郎兵衛説以外ありえないけど、やむなく」と苦笑しつつ語ることがよくありました。
これしか成立しないけれども、写楽でともかく奇想天外なことを書けばそれなりに注目を集める。だから内心困惑しつつも書いていたわけです。
それを今どきやられたところでどうしたものでしょうか。
写楽高評価の源流を辿るため、先週あげた野口米次郎の本など、読み返しているところです。
どうしたって感じるのは、明治以来の脱亜入欧思想です。黒船来航、そしてアジア太平洋戦争敗北と、近代以降、自信喪失ばかりをさせられてきた日本人。
そんな傷ついた心を癒すためには、西洋人から「スゴーイですね!」と褒められたい心理が湧いて来てしまう。
写楽は西洋で評価された。そう舞い上がってしまったんですな。
この野口の論は今読むと一周回って腹立たしくなることも多い。
彼は歌川豊国、歌川国芳を「芸術家とは言えない」と評してもいます。日本人に受けようと、西洋人目線で「芸術家」認定されないと無意味としていたわけです。
これが書かれた大正という時代の限界もあるのでしょうが、豊国や国芳だけでなく、当時の日本人の価値観まで貶めていて何事かと思う次第です。
野口一人でなく、フェノロサの価値観もこのあたりには影を落としておりますが、ともかく払拭したい偏見ありきの評価だと言わざるを得ません。
そんな古臭い劣等感ありきの価値観なんて、私は御免被る。
それなのに、2025年にもなって大河ドラマで見せつけられるとはどうしたものでしょうか。これを裏切りと呼ばずしてどうしようというのやら。
それと、ドラマとしての作りがおかしい。
伏線が欠けた描写があるとここまで指摘しました。うまくつながらず、なんとかおさめようとして相当雑になっているように感じてしまう。
ここまでおかしいと、本来は、斎藤十郎兵衛説でいくつもりだったのではないか?と推察してしまいます。
過去の大河ドラマでも、当初の案が途中で変わったことはあります。
例えば『八重の桜』は、当初発表されていたプロットに忠実であるのは会津戦争終結までで、明治以降は誰かが改変したような展開をしていました。
『いだてん』は、序盤にあったキレがないし、語彙力も低下したように思えます。中盤以降は惰性でいやいや書いているような不自然さがあったものです。
登場してもおかしくない事柄や人物が、描かれないこともあります。
『真田丸』で関ヶ原本戦が一瞬しか描かれなったことはあてはまりません。あれは上田合戦重視という取捨選択のうえの結果であり、そこまで問題にはなりません。
『いだてん』で西竹一はじめ、戦没オリンピアンを無視したことは、局内でも問題視されていたと私は推察します。放映中の別の番組で、潜没オリンピアン特集が組まれていたのです。
ドラマの出来はさておき、最低限良識的な判断をする人がちゃんと局内にいたことに安堵したものです。
『青天を衝け』の池田屋事件で、遅れて到着した土方歳三だけが出て来たこと。渋沢成一郎が出ていながら彰義隊すら言及されない。これはただの手抜きでしょう。
不可解だったのが『天地人』の慶長出羽合戦です。
主役である直江兼続は出てくるのに、対戦相手である最上義光すら出てこない。有名な味方である前田慶次もいない。この二人の場合、それぞれ持ち主が判明できる兜と朱槍は出て来ましたので、途中で何らかの都合があって出せなくなったことがわかります。
『べらぼう』の場合、この『天地人』に近いといえる不可解な消失があります。
写楽を出しておいて豊国を出さないというのは、慶長出羽合戦で兼続を出して義光を出さないくらい不自然な話なのです。
二代目西村屋与八も、すっかり目立たなくなりました。
二代目西与は鱗形屋孫兵衛の二男です。彼にせよ、初代西村屋与八にせよ、序盤で蔦重と何かと因縁があった人物です。両者ともに後半も登場しています。
二代目西与はセンスもこだわりもある人物として描かれて来ており、彼が「歌麿の名前だけ欲しがった」版元になるわけがないといえる。
当初は彼が歌川豊国を擁して蔦重と対峙する案で途中までは来たのではないかと思えます。
それがここにきて、パラレルワールドに迷い込んじまった。
話している相手が、「ゴム人間」、「ディープステート」、「キャンセルカルチャー」、「ナチスはよいこともした」などと言い出したら、その時点で私は話すことを諦めますね。
自分とは交わらない平行線上を生きる相手とは、話しても疲れるだけだし、揉めることは目に見えておりますので。
いわば『べらぼう』の写楽は、もはやパラレルワールドです。
平行線の世界上、私のいる側には滝沢瑣吉、二代目西村屋与八、歌川豊国がいるって寸法でさあ。
で、向こう側では写楽が売れて、蘇我祭も盛り上がって、一橋治済も始末されて、これでめでたしめでたし!
よよよいよよよいよよよいよい、めでてぇな!
いや待てよ。そりゃ民放時代劇の世界観じゃねえか?
大河ドラマの限界点
どうしてこうなったのか?
頭にふと思い浮かんだのは『ゴールデンカムイ』です。
作品のネタバレもあるので、嫌な方は飛ばしてください。
あの作品は途中まで主人公の杉元と、敵役の鶴見を、生死不明退場か、死なせるようにしてきたのではないかと私は予測していました。
それが両者ともに生存します。
鶴見は単行本で展開を変えてまでそうされてしまいました。想定通り退場させた尾形の方がストーリーとして遥かに綺麗にまとまっていると思えたものです。
どうしてそうなったのか?
これは現代社会の病理ともいえるのですが、バッドエンドを回避し、無理にでもハッピーエンドにしたい欲求があるのでしょう。
人間は複雑な世の中を生き抜くうえで、ありのままに物事を見ていくことに耐えきれなくなることがあります。
そこで古代の人々は、穴が二つ開いていて、その下に線のような傷や、大きな穴があるような木を見つけると神だと想像して、宗教を見出し、生き抜く力として来ました。
人が生き抜くにはこうした物語が支えとなるのです。
とはいえ、宗教は近現代において否定され、弱められてゆきます。それを埋めるように人はフィクションにのめり込むようになってゆくのです。
かつては宗教、現代はフィクション。
生きるための力がバッドエンドで終わってしまったり、否定されることは実に辛いこととなりました。そのことはドラマの感想を書いていると痛感させられます。
過去、私が大河を批判すると、そのファンはこんな怒りを書き記すことが往々にしてありました。
私の心を傷つけた、と。
いや、ドラマの感想でそんな大袈裟ではないか――そう思ったものですが、現代人にとってのフィクションとは、かつての宗教のようなものだと思えば腑に落ちるところではあります。
誰しも信仰は否定されたくないし、妥協点を探れるものでもないのでしょう。
近年、ファンダムが過激化する「トキシック(有毒)ファンダム」現象が問題視されます。ファンダムの水源に毒が流し込まれると、ついていけない人は黙って消えてゆく。
独の沼地に敢えて浸かり続けるものは、論理や批評を無視して、忠誠心を証明することばかりを重視するようになる。作品がトンデモ暴走展開すればするほど、忠誠心が問われます。ますます危険になってゆくわけですな。
『べらぼう』は、いわば神を作り上げた側が、その神を引き摺り下ろすことに耐えきれなくなったのか。下ろしたことで信徒が石をぶつけてくることが怖くなったのか。
当初の予定や歴史を捻じ曲げてでも、ハッピーエンドを作り上げようとするようになった。
そんな悲しい現象なのかもしれません。
この展開により、このドラマは私の中で話題にのぼらせてはいけない作品になりました。
いちいち写楽や歌川派の説明をしたくありませんし、したらしたで、ほぼ確実に場の空気が重くなり、下手すりゃ恨まれ、絶縁宣言を送られる羽目になる。
このドラマが話題の俎上にのぼったら、三十六計逃げるに如かずってことになりまさぁね。
どうせ相手は「こっちの浮世絵への思い入れなんて理解しない」でしょう。
『べらぼう』は、もはや忠誠心アピールの場と化しつつある。批判に対して返す言葉がいちいち過激になってきてやがる。そういうところにあっしが身を置きたくないのは、もはや仕方中橋なんですよ。
『忠臣蔵』ごっこはやりたい人だけにしてくんな。
私自身の戸惑いは横におきまして、大河ドラマ全体の話をしますと。
大河ドラマは、ひとつの限界点に到達したのかもしれません。
史実に忠実にし、バッドエンドにするところは見たくない。捻じ曲げてでもハッピーエンドにしたい。
時代劇でそれは可能なのか?
不可能ではありません。
韓流や華流で取り入れられている「フュージョン時代劇」がこれにあたります。
モデルとなった時代や出来事、人物は想像できる。しかしバッドエンドを変えて、より見やすい展開にするものです。
あるいは「SF時代劇」。SFと時代劇を組み合わせた新機軸です。
『べらぼう』とスタッフが重なるNHKドラマ10『大奥』のような作品が該当すると言えます。
『べらぼう』がよいドラマであることは確かですので、この路線でいくのであれば、大河以外の枠ではいかがでしょう。あるいは大河をもう少し柔軟度が高い枠にしても良いかもしれません。
いずれにせよ、今年の大河ドラマは逸脱が過ぎてしまったと私は思えるのです。それにより限界点が示されたという点では評価すべきかもしれませんが。
念の為に申しておきますが、再来年はそういうことをやめてほしい。
小栗忠順が実は生きていて、栗本鋤雲の前に現れるような展開にはしないでください。
最後に私のわがままといえばそうですが、願掛けとして書いておきます。
このスタッフで歌川国芳とその弟子でもドラマにしていただけませんでしょうか。今回歪められた浮世絵の歴史を糺す、罪滅ぼしとしていかがでしょうか。猫もたくさん出せますよ。
以前、この手のぼやきとして『柳生一族の陰謀』リメイク希望を書いたところ、実現しました。
小栗忠順大河も、岩下哲典先生考証の大河も、熱烈に見たいものの実現は無理だろうと思っていました。それが当たりましたので、厚かましくここに記す次第でやんす。
🎬 大河ドラマ特集|最新作や人気作品(『真田丸』以降)を総まとめ
あわせて読みたい関連記事
-

なぜ東洲斎写楽は1年足らずで表舞台から消えたのか~蔦重が売り出した浮世絵師の顛末
続きを見る
-

べらぼう必須の浮世絵知識:基礎編|どんなジャンルがあり何が一番人気だった?
続きを見る
-

死絵や無惨絵あるいは横浜絵などもあった|べらぼう必須の浮世絵知識:応用編
続きを見る
-

浮世絵は実際どんな手順で作られていたか|絵師以外の版元や職人も超重要!
続きを見る
【参考】
べらぼう公式サイト