こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【島津義弘の生涯】
をクリックお願いします。
九州征伐
天正十四年(1587年)12月、秀吉の命にて仙石秀久や長宗我部元親らの軍勢が九州にやってきました。
島津から圧迫を受け続け、風前の灯となっていた大友氏が秀吉に救いを求め、ついにそれが実現化したのです。
そして緒戦となる【戸次川の戦い】が勃発。
ここで島津家久が再び鬼神の如き働きをして仙石・長宗我部軍を一蹴するのですが、
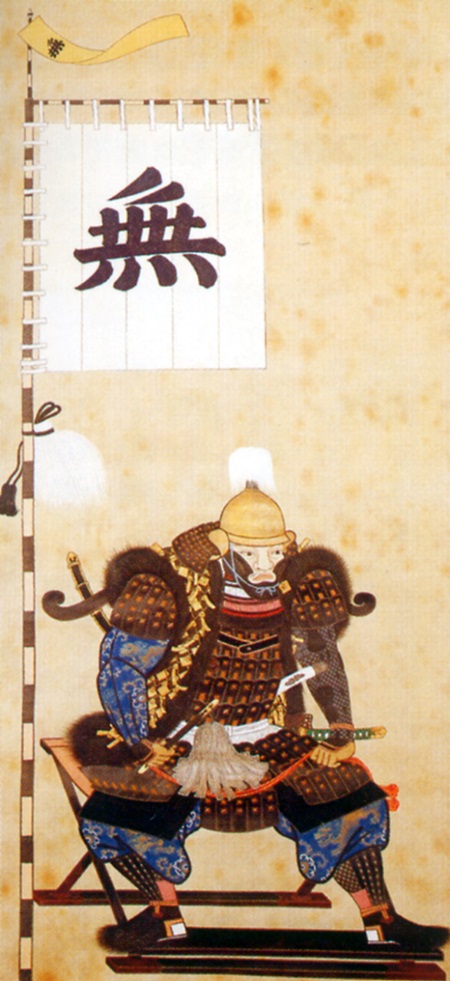
仙石秀久/Wikipediaより引用
あくまでそれは勝利を急いだ先鋒隊・仙石秀久の失策とも言え、関白秀吉の名のもとに集められた諸大名の本軍はまだまだ待ち構えています。
その数、一説には20万から27万とも。
島津にどれだけ地の利があったとしても、2~5万ともされる動員数では、さすがに太刀打ちできません。
結果、天正十五年(1587年)5月、豊臣秀長(羽柴秀長)に降伏。
その前後、島津義弘は、兄の島津義久から家督を継いだと見なされることもありますが、史料では根拠が薄いということで論争の的になっています。
ややこしいことに秀吉から安堵された所領が、
◆義久に薩摩
◆義弘に大隅
◆久保(義弘の子)に日向の一部
というカタチだったのです。
人たらしとも呼ばれ、人情の機微に敏感な秀吉のことですから、義弘と義久たち四兄弟の結束を割いて、弱体化しようと考えたのでしょう。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
しかし、祖父の教えもあってか、義弘は兄を当主として盛りたて続け、この離間策は失敗します。
人の欲や生存本能を衝いた秀吉の嫌らしい策に対し、それを見抜いて毅然と対処した義久と義弘。
派手な戦に比べると地味ですが、こういった政治的な駆け引きもなかなかに胸が躍りますね。
文禄・慶長の役にも渡海し奮戦
島津義弘は豊臣政権に対してかなり協力的に接しました。
【文禄・慶長の役】の両方で渡海し、奮戦しています。

文禄の役『釜山鎮殉節図』/wikipediaより引用
ゲスい見方をすれば、秀吉にとって表向きは「島津の武勇を大陸でも見せてくれ」であり、真の狙いは「さすがの島津も苦戦して勢力を弱めるに違いない」というところですかね。
しかし、ここでも義弘以下の島津軍は秀吉の思うようには行きません。
文禄・慶長の役では、戦死者の他に餓死者・凍死者が多かったのですが、義弘が日頃から兵を気遣う姿勢でいたこともあってか、島津軍の凍死者は少ないものでした。
むろん全く被害がなかったわけではありません。
なんと朝鮮滞在中に嫡男の島津久保を病気で失っているのです。餓死という説もあります。
義久には男子がなく、久保が義久の娘・亀寿を正室にしていたため、島津家の次期当主とみなされていました。
そんな人物が餓死するとは何事か……と思ってしまいますが、久保には兵を気遣うあまり、自らを省みないところがあったのかもしれません。
これにより義弘の子で久保の弟である島津忠恒(のちに島津家久)が亀寿と結婚して島津家の次代を担うことになります。

島津忠恒/wikipediaより引用
慶長の役でも島津軍は他家と協力して朝鮮水軍を挟み撃ちにし、敵将を討ち取ったり、三倍以上の敵に打ち勝ったり、かなりの奮戦しています。
義弘にとって、慶長の役は久保の弔い合戦という意味もあったでしょう。
忠恒の悪行と庄内の乱
慶長三年(1598年)8月、豊臣秀吉が亡くなりました。
それから2年後の慶長五年(1600年)に関ヶ原の戦いが勃発するのはよく知られた話ですが、秀吉の死後、島津ではそれどころではない別の大問題が起きていました。
先に流れだけ追ってみましょう。
①慶長四年(1599年)3月、島津忠恒が、秀吉の直臣でもあった家老の伊集院忠棟(ただむね)を手打ちにした
↓
②伊集院忠棟の息子・忠真(ただざね)が日向で反乱
↓
③石田三成が激怒
↓
④徳川家康が忠真討伐を許可
↓
⑤家康の仲介で和睦
詳細は、以下の記事に譲らせていただきますが、この一連のトラブルは【庄内の乱】とも呼ばれ、薩摩を揺るがした内乱となっています。
-

戦国島津家ドロドロの内紛「庄内の乱」とは? 関ヶ原直前に起きた薩摩の大乱
続きを見る
同時に島津家は、家康に借りを作る形になってしまいます。
関ヶ原の戦いで島津がなんだかよくわからない中途半端な動きになっているのは、こうして事前に起きていたトラブルなどが影響したとされます。
それを踏まえて先へ進めましょう。
※続きは【次のページへ】をclick!

