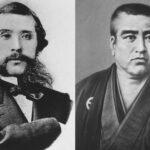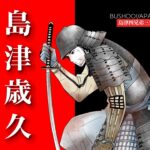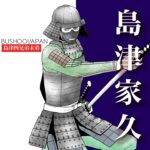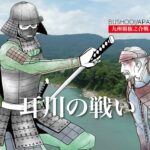こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【島津義弘の生涯】
をクリックお願いします。
弩級のインパクト・島津の退き口
慶長五年(1600年)9月に関ヶ原の戦いが勃発。
島津義弘の武功といえば、伝説的に語られる【島津の退き口】が有名であり、この戦いの最中に起きたものですね。
単純に説明すると以下の流れとなります。
①成り行きで西軍となってしまった義弘軍
②敗戦後、何が何でも義弘を薩摩へ帰すため
③数少ない将兵たちが命と引き換えに退路を確保した撤退戦
1600名ほどいた部隊のうち、生きて薩摩に帰れたのは数十名とまでいわれるほど凄まじいものであり、そこからがいよいよ島津義弘の胆力の見せ所となります。
皆に生かされた義弘は、薩摩に帰ると、国境の防備を固めながら徳川家との和平交渉に挑むことに。
薩摩隼人というと、とにかく勇猛果敢が売りのようにも見えますが、事態が変われば臨機応変に応じることができるのもその特長。
義弘は、退き口の際に激突した井伊直政を頼ったり、代々付き合いのある近衛前久(信長とも親しかった公家)に頼んだり、事前に抜け目なく話を持ちかけています。

井伊直政/wikipediaより引用
むろん徳川家康も簡単には引けません。
「あくまでワシに逆らうのか、よろしい。ならば合戦だ」(超訳)
と、黒田・加藤・鍋島ら各家を含めた3万の軍を派遣します。
しかし、実際には攻めきれません。
島津家は積極的に西軍へ参加しようとしていたわけではありませんし、そもそも家康の連絡不足も絡んで義弘が西軍に取り込まれるという流れがありました。
しかも薩摩本国には、関ヶ原へ派兵できなかったことから精強な兵が温存されていて、義久も健在のまま攻め込むとなると、さすがの家康も「真っ向勝負は得策ではないか……」という判断になります。
そして「ワシと義久は友達だし、あれは義弘の独断だったんだもんな」(超訳)という理由で討伐を取りやめました。
義弘たちが勝ち取ったお家安泰
家康は、真田昌幸や真田信繁(幸村)についても、最終的には「許せんが命までは取らん」という判断でした。
島津に対しても、私情に完全に流されることなく平等な扱いをした、と言えるかもしれません。
この辺はさすがの政治的センスというべきなのでしょうか。

徳川家康/wikipediaより引用
島津家と全面戦争を始め、仮に苦戦でもしようものなら、九州や西日本の大名たちが蜂起するかもしれません。
「徳川なんて大したことないんでは? だったら島津と組んでもう一戦やろう」
九州中に、そんな雰囲気が蔓延したら最悪です。
なんせ義弘による島津の退き口もあり、薩摩の恐ろしさは知れ渡っています。
家康としては、結局、そうした手間を増やすよりも島津を傘下に組み込み、大々的に逆らわないようにさせるのが最もリスクが少なかったという判断ですね。
こうして島津が正式に本領安堵されたのは、慶長七年(1602年)のことでした。
隠居後
その後、島津義弘は現在の鹿児島県・加治木に隠居しました。
今も鹿児島市に対するベッドタウンになっているそうで、隠居所にほどよい場所だったのかもしれません。
義弘が朝鮮の役の際に連れ帰った職人によって、”薩摩焼”と呼ばれる数々の製陶も始まりました。
最初の窯は金海(日本名:星山仲次)が作ったもので、現代では「竪野(たての)窯」と呼ばれています。
金海は勉強熱心な人だったようで、瀬戸へ修行に出て、薩摩へ戻ってきてから窯を開いたのだそうです。

薩摩焼の壺
異国の地で言葉を学びながらの修行はさぞ大変だったでしょうね。
彼は義弘が加治木へ移った後もついていき、御里(おさと)に御庭窯を作ったため「御庭焼」の名がついたのだとか。
金海は義弘が亡くなった後も、息子の家久(忠恒)に招聘されて新たに竪野窯を開いたといいます。
他にも苗代川(なえしろがわ)焼・竜門司(りゅうもんじ)焼など、薩摩では多くの名窯が開かれ、一大産業となりました。
また、このエリアには「龍門滝」という滝があり「滝壺で洗濯していたら大蛇が現れた」とか、「1m以上もある大亀が住んでいた」などのいわくがついていました。

龍門滝
最晩年の義弘は、ときに職人の作品や名瀑を眺めたりしながら、穏やかに過ごしていたのかもしれません。
さらに義弘は、若者の教育にも力を入れていたそうです。
これが薩摩藩の伝統である【郷中教育(ごじゅうきょういく)】の元ではないかともいわれています。
詳細は以下の記事にお譲りしますが、
-

西郷や大久保を育てた薩摩の郷中教育とは?泣こかい飛ぼかい泣こよかひっ飛べ!
続きを見る
ざっくり言うと、年長の藩士が問答や武道の稽古を行い、若年者に教育を施し、「女性にはできるだけ近寄るな! 交際などもってのほか!!」などの厳しい掟をベースとした教育です。
それが後の衆道関係に影響したとか……まぁ、その辺は別の話ですね。
★
義弘が亡くなったのは元和五年(1619年)7月21日のことでした。
享年85。
義弘の人生をまとめると
「若い頃の失敗に学び、壮年時代にはそれを活かした戦上手となり、日頃は家族や家臣に優しく、晩年は後進のために自らの知識を惜しみなく与え、傘寿を超えて大往生した」
なんて、出来すぎなほどの御仁になってしまいます。
でも本当だから仕方がありませんし、それが魅力ですよね。
今後も彼のファンは増え続けることでしょう。
あわせて読みたい関連記事
-

薩摩の戦国大名・島津貴久の生涯「中興の祖」とされる四兄弟の父 その功績とは?
続きを見る
-

戦国大名・島津義久の生涯~薩摩から九州制覇を目前にして秀吉に敗れた無念
続きを見る
-

薩摩で戦の神と称される戦国武将・島津歳久の生涯~秀吉に矢を放ち最後まで抵抗
続きを見る
-

薩摩最強の戦国武将・島津家久の生涯~次々に大軍を撃ち破った軍神の戦績とは?
続きを見る
-

耳川の戦い1578年|島津軍が釣り野伏せで大友宗麟に完勝!九州覇者へと躍り出る
続きを見る
【参考】
新名一仁『戦国武将列伝11 九州編』(→amazon)
『戦国武将事典 乱世を生きた830人 Truth In History』(→amazon)
峰岸純夫/片桐 昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)
国史大辞典
日本大百科全書(ニッポニカ)