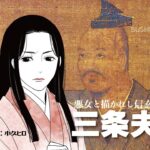こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【「小倉百人一首」の作者リスト】
をクリックお願いします。
定家の生きていた時代
83 皇太后宮大夫俊成(藤原俊成)
→選者・定家の父
84 藤原清輔朝臣
→若い頃から飄々とした歌人
85 俊恵法師○
→鴨長明(方丈記の著者)の師匠
86 西行法師○
→旅に生きた僧侶歌人

西行法師/wikipediaより引用
87 寂蓮法師○
→三夕の歌で有名な僧侶歌人
88 皇嘉門院別当☆
→技巧的な恋歌が得意な女流歌人
89 式子内親王☆
→以仁王の妹、定家の憧れの人?
90 殷富門院大輔☆
→悲しい歌が多い女流歌人
91 後京極摂政前太政大臣(九条良経)
→書道の後京極流開祖、最期が……
92 二条院讃岐☆
→鵺(妖怪)退治で有名な源頼政の娘
93 鎌倉右大臣(源実朝)
→鎌倉幕府三代将軍、定家の弟子

源実朝/Wikipediaより引用
94 参議雅経(飛鳥井雅経)
→蹴鞠の名人、蹴鞠の飛鳥井流の開祖
95 前大僧正慈円
→藤原忠通の息子、愚管抄の著者
96 入道前太政大臣(西園寺公経)
→鎌倉幕府と親しかった公家
97 権中納言定家(藤原定家)
→百人一首の選者、当時の歌壇主導者の一人
98 従二位家隆(藤原家隆)
→定家の兄弟弟子で良きライバル
99 後鳥羽院
→承久の乱で流された上皇、新古今和歌集など文化的功績多し

後鳥羽天皇(後鳥羽上皇)/wikipediaより引用
100 順徳院
→承久の乱で流された天皇
小倉百人一首の歴史
さて、小倉百人一首そのものについても見ておきましょう。
成立は鎌倉時代で、収録されている歌はそれ以前……というか平安時代が中心です。
当時の歌壇第一人者だった藤原定家が、親戚かつ歌人仲間である宇都宮頼綱の依頼で、個人の邸宅の装飾用に撰んで書いた「和歌の色紙」が元とされています。

藤原定家/wikipediaより引用
現代でいえば、個人のPCのブックマークやお気に入りが巡り巡って世間に広められたようなものなのかもしれません。
そう考えると「やめてやれよwww」という気がしないでもありませんね。
勅撰和歌集は公的なものですから、政治的配慮や世間の評判などを意識せねばならない……といったの暗黙の了解がある一方、小倉百人一首はそもそもプライベートなものなので、そういうものがいらなかったと思われます。
なぜかと申しますと、55番の藤原公任や86番の西行法師など「その人ならもっといい歌があるよね? なんでこんな駄作入れたの?」というツッコミが古くからされているのです。
しかしそれは「定家は立場上、技巧的な歌や古来から名歌と讃えられる歌を評価せねばならないが、個人的には単純な歌も好きだった」という好みが反映されたからではないか?と思います。
それまでは忘れられていた歌人や歌が、定家が高く評価したことによって、世の中に知られるようになったケースもありますしね。
また、後鳥羽院や順徳院など、定家の時代=承久の乱があった頃は勅撰和歌集への入選が控えられた歌人の歌も入れられました。
これを「暗号」と捉える説もあります。
ミーハー目線で有名人の歌から楽しんでみては?
もしも「かるた」に挑むのでしたら「決まり字」などのセオリーを覚える必要があります。
「和歌の本でも読んでみようかな?」という方は、まず百人一首の中から気になる歌を探してみると良いかと思います。
特に百人一首の前半、50番までは割と平易な歌が多く、季節の情景を描いていてわかりやすい作品も少なくありません。
あるいは、天智天皇や紫式部・清少納言など、誰もが知っている人の歌について、解説を読みこんでみるのもいいでしょう。
”やまとうたは、人の心を種として、よろずの言の葉とぞなれりける。”
これは「古今和歌集」の序文の冒頭です。選者の一人である紀貫之が書いたといわれています。
意訳すると
「和歌というものは、人の心という”種”から数多くの言の”葉”となって生まれるものである」
つまり、素直な感覚が数多の言葉となり、それを三十一文字にまとめたものが和歌なのです。
学校の授業では変化形や古語特有の単語の暗記が中心になってしまいますが、当時の歌人たちは、現代の我々がなんとなく五・七・五でつぶやくのと同じように、自然と言葉をまとめていったでしょう。
もちろん、技巧や背景となる知識が重んじられることもありますが。
古今和歌集をはじめとした勅撰和歌集は数百~数千首あります。
その中から気になるものを見つけるのはなかなか難しいですけれども、百人一首ならばそこまででもありません。
季節や恋、人生の悩みなどを散りばめた百首の中に、きっと一つはピンとくるものがあるはずです。
かるたをやるやらないにせよ、少しずつ眺めてみるのもよろしいのではないでしょうか。
あわせて読みたい関連記事
-

清原元輔(清少納言の父)は底抜けに明るい天才肌~身分低くとも歌人として名を残す
続きを見る
-

『光る君へ』清少納言は史実でも陽キャだった?結婚歴や枕草子に注目
続きを見る
-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは
続きを見る
-

藤原公任の生涯|道長のライバルはモテモテの貴公子だった?
続きを見る
-

三条夫人の生涯|信玄の正室は本当に高慢ちきで何もできない公家の娘だったのか
続きを見る
【参考】
『田辺聖子の小倉百人一首〈上〉 (角川文庫)』(→amazon)
『田辺聖子の小倉百人一首〈下〉 (角川文庫)』(→amazon)