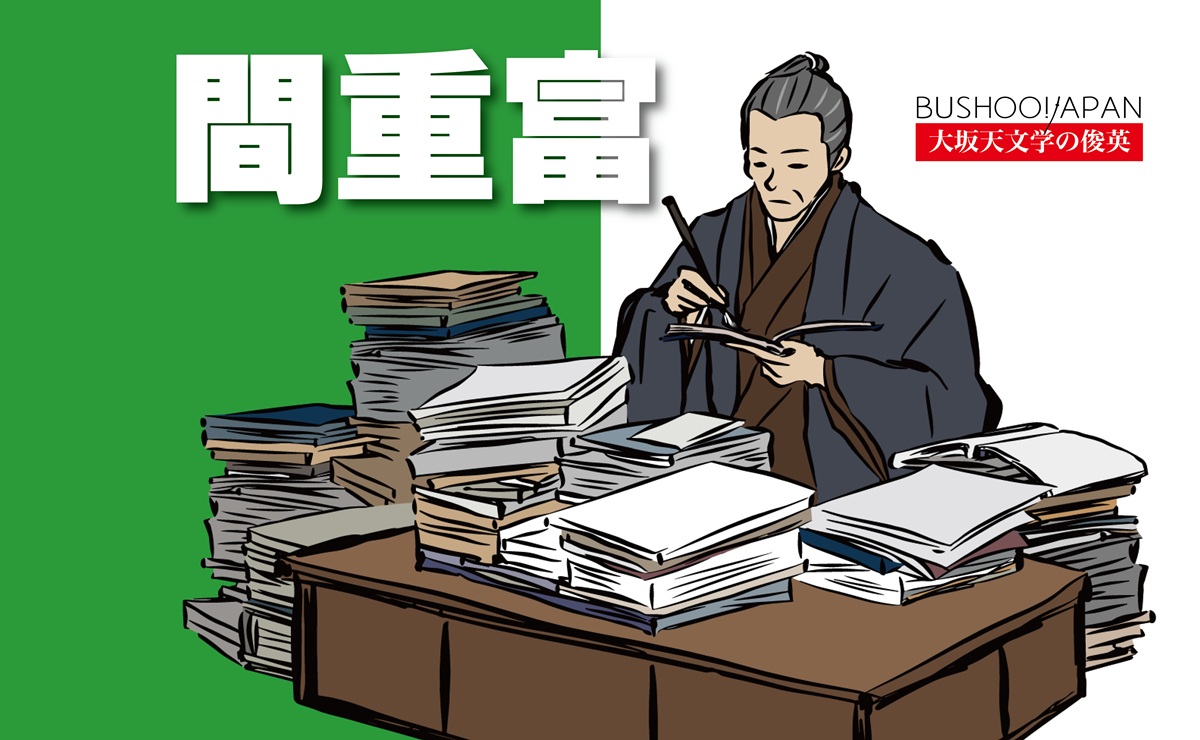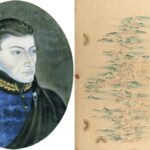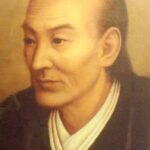こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【間重富】
をクリックお願いします。
伊能忠敬に天文観察の指導
寛政八年(1796年)、高橋至時が一時的に京都へ向かうと、その弟子である伊能忠敬に天文観察等の指導をしたこともありました。
といっても間重富よりも伊能忠敬のほうが歳上でしたので、当初は教えるのも難しかったかもしれませんね。

伊能忠敬/wikipediaより引用
しかしそこは50を過ぎて至時に弟子入りするぐらいの忠敬ですから、指導者によって態度を変えることはなく、マジメに取り組んでいたようです。
至時は、全国測量による日本地図作製計画を立てた際、西日本の分については重富に頼むつもりでいたようです。
ところが至時が病で休養したため、計画は先送りになってしまうどころか、享和四年(1804年)に亡くなってしまい、この話はさらに遅れることになります。
重富は至時の子・高橋景保(当時20歳)を後見して、解読を続けるよう幕府から命じられました。
このため文化元年(1804年)に再び江戸へ行き、同六年(1809年)四月まで滞在して作業を進めています。
長崎の通詞(通訳)をしていた馬場佐十郎という人の協力も得て作業を進めましたが、文化十年(1813年)に浅草天文台が火事になり、『ラランデ天文書』も翻訳した草稿も燃えてしまいました。
その頃には重富も大坂へ戻っていたのですが、何らかの形でこのことは知ったと思われます。さぞ残念だったでしょうね……。
機材を作る職人も育て上げ
こうして名を上げた重富でしたが、家業の質屋も続けていました。
さらに手元で機材を作る職人を育て上げ、陰ながらその後の測量・天文界の発展に寄与しています。
重富が亡くなったのは文化十三年(1816年)3月24日のこと。前年の秋から病みついていたそうなので、病死と思われます。
伊能忠敬が9回目の測量で伊豆へ向かっている間のことであり、その結果を見届けられなかったのは無念だったかもしれません。忠敬も、年下の師匠二人に先立たれたのは辛かったでしょうね……。
重富のお墓は、大阪市天王寺区茶臼山町の統国寺にあります。
こちらのお寺は他にも江戸時代の文化人が多々あったり、ベルリンの壁の一部が保管されていたりと、いろいろと見どころが多いようです。
天王寺動物園と近いようなので、この一角だけでも丸一日観光できそうですから、お近くを訪れる際は立ち寄ってみるのもいいかもしれません。
みんなが読んでる関連記事
-

イギリス人も驚嘆した伊能忠敬の大日本沿海輿地全図~作り始めたのも驚きの56才
続きを見る
-

シーボルト事件に巻き込まれた高橋景保 その最期はあまりに不憫な獄中死だった
続きを見る
-

地図を渡しただけで獄死!だった江戸の国防事情 まんが日本史ブギウギ204話
続きを見る
-

聖人・緒方洪庵 54年の生涯~適塾で医師を育て種痘撲滅に奔走した偉大なる功績
続きを見る
-

「蘭学の化け物」と称された前野良沢『解体新書』翻訳者の知られざる生涯とは?
続きを見る
【参考】
吉田光邦『江戸の科学者 (講談社学術文庫)』(→amazon)
中江克己『江戸のスーパー科学者列伝 (宝島SUGOI文庫)』(→amazon)
国史大辞典
デジタル大辞泉
日本国語大辞典
世界大百科事典
日本大百科全書(ニッポニカ)