昭和の古い世代には高倉健さんの映画『網走番外地』で知られ、同映画をご覧になられていなくても「恐怖の刑務所」というイメージをお持ちでしょう。
そもそもは明治23年(1890年)3月、道路工事のため囚人が使役されたのが契機なのですが……。
いったい誰が作ったのか?
どんな罪人が送られ、どんな暮らしぶりだったのか?
知名度の割に、意外と史実は知られていないようにも感じます。
現代人から見ると、当時は背筋も凍るような記録も残されていて、昨今の歴史ファンであればマンガ『ゴールデンカムイ』でその様子を垣間見たかもしれません。
マンガの登場人物は網走監獄をどのように評したか?
というと……。
土方歳三
「旭川の発展をもたらした『上川道路』札幌と旭川を結ぶ道路脇には…おびただしい死体が埋まっている
ヒグマと狼に怯えながら寒さと飢えに苦しみ死んでいった(網走監獄の)囚人たちだ」
鈴川聖弘
「(網走監獄の)囚人はもとより悪徒であるから、懲罰として苦役させれば工事が安く上がり、斃れ死んでも監獄費の節約になる」土方歳三
「樺戸集監に収容されたのは戊辰戦争や西南戦争で負けた国事犯と呼ばれる武士たちだ勝てば官軍 負ければ賊軍 戦争というのは負けてはいかんのだ」
※『ゴールデンカムイ』10巻収録 第97話・土方の台詞より(→amazon)
命を命とも思われない――虫けらのように扱われる過酷な言葉がずらりと並び、ただごとではない雰囲気を感じられるでしょう。
実は、明治維新まで遡る。
網走監獄の歴史を振り返ってみましょう。
※本稿には差別的な語彙や表現が出てきますが、差別の実態を描写するために敢えて記載しております。ご理解ください
※マンガ『ゴールデンカムイ』登場人物アシリパの「リ」は小文字になります
北の果ての監獄――それが網走
現在、網走監獄と聞いてざわつくのは『ゴールデンカムイ』のファンでしょう。
前述の通り、かつては映画『網走番外地』シリーズが定番でした。
その歴史は明治維新まで遡り、当時、日本の政情は、とても安定していたとは言いがたいものでした。
相次ぐ不平士族の反乱により、政治犯が激増。
司法改革にも迫られています。

神風連の乱(不平士族の反乱の一つ)を描いた錦絵/wikipediaより引用
江戸時代のように、凶悪犯をその都度、斬首しているようでは、西洋諸国から非文明的とみなされてしまいます。
明治12年(1879年)。
高橋お伝の斬首を最後として、この制度は終焉を迎えました。
こうなると政府としては、あり余る犯罪者をどこかに集めなくてはなりません。
ドコにすべきか?
実は新政府の成立以降、候補地は決まりきった話でした。
戊辰戦争で敗れた佐幕藩の士族を、屯田兵と称して北海道開拓に送り出していたのですから。
-

とにかく過酷だった北海道開拓~明治維新敗者に新選組や囚人達の苦難とヒグマの恐怖
続きを見る
-

敗者の会津藩士たちが極寒の北海道余市で栽培した 開拓リンゴ「緋の衣」とは
続きを見る
屯田兵や開拓に挑む人々の境遇は、若干改善されてはいたものの、初期は過酷そのもの。
彼らのほとんどは、戊辰戦争の敗者や災害で土地を失った者でした。
そう、持たざるものの新天地が北海道であったのです。
しかし寒冷の地を開拓することは、危険でハイリスクであります。
もちろん明治政府は理解しておりました。
いっそ、危険で過剰な労働の結果、死んでも仕方がない人員がいればうってつけではないのか――そんな非情極まりない決断の結果、北海道に監獄が置かれるのです。
それこそが網走監獄(いわゆる網走刑務所)でした。
長期刑者か無期懲役が大半の囚人たち
『ゴールデンカムイ』から鈴川の言葉を引用しましょう。
「囚人はもとより悪徒であるから
懲罰として苦役させれば工事が安く上がり
斃れ死んでも監獄費の節約になる」
死んでもいいような囚人を強制労働させよう――そんな狙いですから、当然、刑罰の重い者が収容されることになります。
多くは無期懲役や長期刑の重大犯罪者。
『ゴールデンカムイ』の「刺青人皮」囚人も、連続殺人犯や凶悪犯が多いですね。
連続脱獄に手を焼かれた白石も、網走収監となったわけです。

網走刑務所正門前/photo by achappe wikipediaより引用
史実での有名収監者も、大物揃いでした。
「凶悪犯の吹きだまり」
「一度入ったら二度と出られない」
そう呼ばれた網走監獄には、凶悪犯だけではなく思想犯、政治犯も多く収容されております。
ザッと挙げてみましょう。
・安部譲二
・伊藤一(『網走番外地』原作者)
・小山豊太郎(李鴻章狙撃犯)
・白鳥由栄(白石のモデル)
・徳田球一(政治運動家)
・津田三蔵(大津事件犯人)
・西川寅吉(「五寸釘寅吉」の異名を持つ泥棒)
・野村秋介(右翼活動家)
・ブランコ・ド・ヴーケリッチ(ゾルゲ事件で逮捕されたスパイ)
・美能幸三(元暴力団員、『仁義なき戦い』の原作者、作中では広能)
・宮本顕治(日本共産党の政治家・文芸評論家)
こうした囚人を収監しながら、政府には、あわよくばという考え方もありました。
収監後、彼らが北海道に定住すれば、もう本州にはやって来ませんし、北海道の住人も増えて一石二鳥というわけです。
しかしこれは現地に住む人にとっては、たまったものではありません。
白石のモデルとなった白鳥由栄のような脱獄囚の存在もあります。
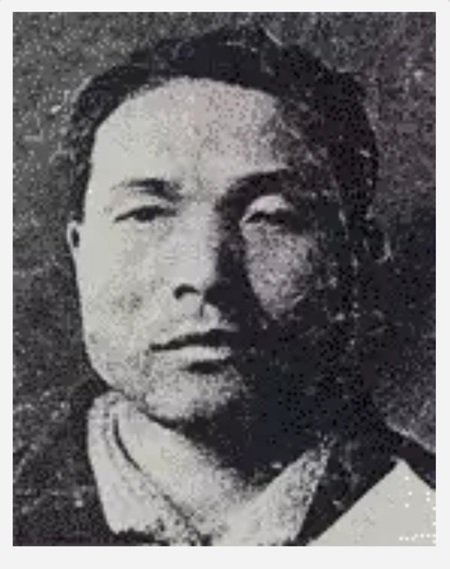
白鳥由栄/wikipediaより引用
網走は、野生動物の存在や過酷な周辺気候から、日本一脱獄が困難な刑務所とされていました。
大泥棒で「五寸釘寅吉」と呼ばれた西川寅吉は、標茶集治監では七回も脱獄したほど。それが、網走移転後は模範囚となっております。
しかし、例外も出てくるわけです。
『ゴールデンカムイ』の白石はチャーミングな人物です。
ただし、そのモデルとなった白鳥のような脱獄囚は、周辺住民にとっては大迷惑。住民はたまったものではなく、ビクビクしていたそうです。って、そりゃそうですわな。
マンガの杉元らは、刺青を持つ囚人をノリノリで捕まえに行きますが、一般人には無理な話ですし、そもそも関係ないでからね。
※続きは【次のページへ】をclick!


