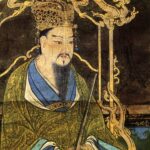延長元年(923年)9月28日は、平貞文が亡くなった日です。
名前の読みは「さだふみ」「さだふん」両方ありますが、とにかくこの方、悲しくマヌケな逸話をお持ちでして。
恋した人妻を諦めるため“あるもの”を盗み出そうとして、とんでもなく恥ずかしいエピソードを歴史に残してしまったのです。
いったい何を盗み出そうとしたのか? 振り返ってみましょう。
桓武天皇の玄孫にして和歌で知られる
平貞文は桓武天皇の玄孫(孫の孫)にあたる、高貴な家柄に生まれました。
※以下は桓武天皇の関連記事となります
-

なぜ桓武天皇は遷都のほか様々な改革を実行したのか? 平安前期と共に振り返る
続きを見る
物心付く前に親戚に下り、その後は主に武官を務めていましたが、そこは平安貴族。
彼の名が出てくるのは、ほとんど和歌に関することです。
例えば古今和歌集の選者である紀貫之・壬生忠岑(みぶのただみね)・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)などと交流がありました。
この三人はいずれも小倉百人一首にとられているので、ご存じの方も多いかもしれません。
ついでですから、その歌を出しておきましょう。
29番 凡河内躬恒
「心あてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花」
【意訳】おやおや、初霜で一面白くなってしまった。どこともなく戯れに手を伸ばしたら、白菊の花を折れるだろうか
30番 壬生忠岑
「有明の つれなく見えし 別れより 暁ばかり 憂きものはなし」
【意訳】あなたと会えるようになってから、夜明けが憎らしくなってしまったよ。有明の月もあなたも、早く帰れとつれないものだから
35番 紀貫之
「人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香(か)に匂ひける」
【意訳】あなたの心は変わってしまったかもしれませんが、この里に咲いている梅は、変わらぬ香りで私を迎えてくれていますね
百人一首にとられているだけあって、いずれも名歌ですね。
忠岑だけちょっと毛色が違う気がしますが、これは彼が身分の低い武官であったことや、それだけに恋が成就するのも難しく、叶ったときの執着も大きいからなのかもしれません。
「歌人」と一口に言っても、写実的な歌が得意な人もいれば、滑稽味のある歌を多く詠んでいる人、恋の歌ばかりの人もいるので、個人的な推測ですけれども。
在原業平と並び称されるイケメンかつ恋多き男
では貞文の場合は?
といえば、この三人の中では忠岑が一番近いかと思われます。
恋の歌が多いからです。
「なぜ恋の歌が多いのか」という理由については、だいぶ違いますが。
貞文は、あの平安きっての色男・在原業平と並び称されたほどのイケメン、かつ恋多き男でした。
彼に関するエピソードで一番有名なのは、後世の『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』に出てくる話でしょう。
ちょっと下ネタなので、苦手な方はご注意ください。
ときの左大臣・藤原時平の妻とされる、本院侍従(ほんいんのじじゅう)という女性に、貞文が言い寄った時の話です。
「侍従」なので、お相手は宮仕えしている人ですね。
既に人の妻なので、いくらイケメンの貞文が言い寄っても、のらりくらりとかわされてうまくいきませんでした。
しびれを切らした貞文は、わざと激しい雨の夜に本院侍従を訪ねていきます。
「こんな天気の日にわざわざ来てくれるなんて、本当に私のことが好きなんだわ」と思ってくれるはず、と考えたわけです。何だかなあ(´・ω・`)
しかし、本院侍従は一度は貞文の待つ部屋までやってきたものの、「戸を閉め忘れたから」と言ってすぐに席を外してしまいました。
そのまま戻らず、貞文は待ちぼうけ。
※続きは【次のページへ】をclick!