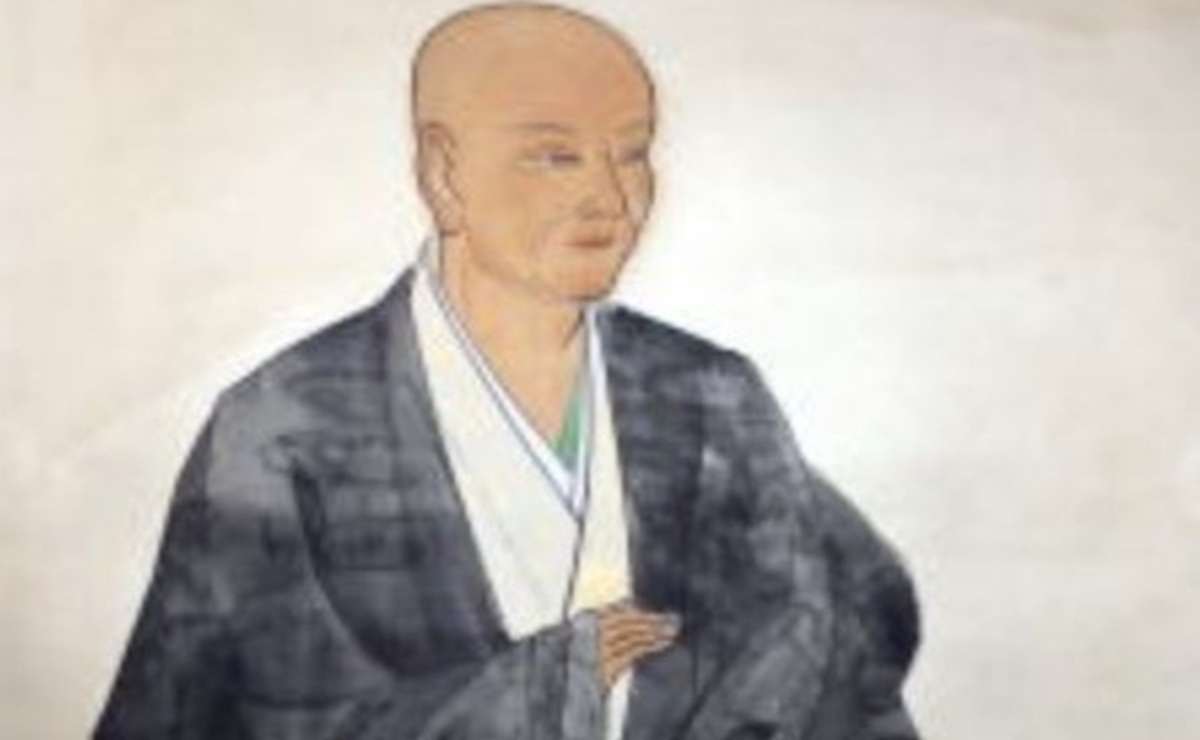天正十七年11月1日(1589年12月8日)は北条幻庵が亡くなったとされる日です。
字面からしてなんだか雰囲気のある名前ですが、実際、関東に一大勢力を築いた北条氏の“長老”という存在であり、80代までの長寿を全う。
武田信玄や上杉謙信らと鎬を削った北条氏康の叔父であり、その氏康より18年も長生きしています。
しかも単に長いだけではなく、北条氏が関東一円に勢力をぐいぐいと広げていく中で、重要な役割も果たしていました。
そんな北条幻庵とは一体どんな人物だったのか?
生涯を振り返ってみましょう。

北条幻庵/wikipediaより引用
父は北条早雲 兄は北条氏綱
北条幻庵は、後北条氏初代・北条早雲(伊勢宗瑞)の末子で、2代・北条氏綱の弟として生誕。
母は駿河の有力豪族であった葛山氏の娘とされています。

北条早雲(伊勢宗瑞)/wikipediaより引用
この時代によくあることで、幻庵の生年はハッキリしておらず、永正年間(1504-1521)生まれが妥当と考えられています。
幼名は菊寿丸でした。
いかにも長寿になりそうな名前で、“幻庵”はもっと後になりますが、本稿ではこちらで統一させていただきます。
彼は末子ということもあって、幼い頃から箱根権現(神奈川県箱根町)に入れられており、世俗での元服をしていません。
箱根権現とは今日の箱根神社(神社公式サイト)のことで、祭神は以下の三柱。
瓊瓊杵尊(ににぎのみこと):天孫降臨で地上に降りた神様、天照大神の孫で神武天皇の曽祖父
木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと):瓊瓊杵尊の妻
彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと):瓊瓊杵尊と木花咲耶姫命の子
もともと相模にあった山岳信仰と、三柱への信仰が習合してこの形になったと見られています。
鎌倉時代から武家の尊崇を集めており、早雲も神仏を庇護することで相模周辺の武士を慰撫する目的があったと思われます。
早雲は死の直前の永正十六年(1519年)4月、4400貫文もの広大な領地を幻庵に与えました。
その大半は箱根権現の領地だったとされる場所であり、名実ともに幻庵がこの地を掌握できるようにしたのでしょう。
大まかな計算では銭一貫文=米一石ですので、少年のうちに4400人を養えるだけの収入を得たことになります。

現代の箱根神社拝殿
箱根権現の僧侶へ
北条幻庵は大永二年(1522年)、近江三井寺上光院(滋賀県大津市)に入り、大永四年(1524年)の春に出家して僧侶の道を歩み始めました。
法名は当初「長綱」と言い、読みはおそらく「ちょうこう」だと思われます。
「長綱」は真言宗でよく用いられる字で、箱根権現が真言宗と密接に関わっていたことからつけたようです。
そして天文年間(1532-1555)後半から「幻庵宗哲」を使うようになったと思われますが、2つの名を併用していた時期もあるため、厳密に切り替えたわけではなかった様子。
ここでの注目も、父である北条早雲(伊勢宗瑞)ですかね。
宗瑞が出家後に「早雲庵宗瑞」としたため、幻庵宗哲の名も父に倣ったものと考えられています。
大徳寺系の寺院が「宗・紹・妙・義」の中から一字取ることを慣習としていた影響もあるとか。
しかし、聖職だからといって静かに神仏と接するだけではないのが戦国時代の僧侶。
隣国・今川義元の参謀である太原雪斎を彷彿とさせるように、幻庵もまた戦場に出向くのでした。
武田や上杉との合戦に武将として出陣
箱根権現は聖職ですし、前述のように法名も名乗っていたわけですが、北条幻庵は合戦の場にも多く登場するようになります。
例えば、天文四年(1535年)8月には、信玄の父・武田信虎との【甲斐山中合戦】に参戦。
同年10月には信玄の舅だった上杉朝興と【武蔵入間川合戦】へ(※信玄最初の妻は上杉朝興の娘だった)。
いずれも武将として参加しています。

武田信虎(左)と息子の武田信玄/wikipediaより引用
幻庵の出家はあくまで「家督相続からは外れる」ことを内外へ示すためであり、完全に聖職者になるためではなかったのでしょう。
天文九年(1540年)には箱根権現別当の地位を退いたとされます。
しかし、その後もこの土地は幻庵のものだったため、実権は手放していなかったと思われます。
北条氏といえば早雲からの五代当主が注目されますが、寺社で学びを修めた幻庵という存在が、知恵袋として勢力維持に貢献していたことを実感させます。
当時の寺社は高等教育を受けられる重要な機関でもあり、今川義元も栴岳承芳(せんがくしょうほう)と名乗り、京都の妙心寺や建仁寺で修行していましたね。
実際、若い頃に近畿にいたこともあってか、北条幻庵には和歌を愛する一面もありました。
冷泉為和を招いて歌会
天文三年(1534年)12月18日には、公家の冷泉為和を招いて歌会を開催。
天文十四年(1545年)2月には、小田原へ連歌師の宗牧を招いて連歌会を開いたこともあったそうです。
連歌とは、五・七・五と七・七の長短句を複数人で繋げて詠む遊びで、以下の記事にありますように、明智光秀や細川藤孝、あるいは真田信繁(幸村)が熱中していたことでも知られます。
-

戦国武将たちが愛した連歌をご存知?光秀も藤孝も幸村も皆んなハマっていた
続きを見る
いかにも幻庵に向いた交流と言えるでしょう。
戦国大名や有力武将に欠かせない参謀の一人というイメージですね。
また、天正八年(1580年)閏8月には、同じく北条氏の家臣である板部岡江雪斎に古今伝授についての証文を与えており、幻庵が長期間にわたって和歌の研鑽を積んでいたことがうかがえます。
北条氏では、三代・北条氏康と四代・北条氏政も和歌に通じていたとされていて、

北条氏康(左)と北条氏政/wikipediaより引用
幻庵の薫陶があったことも想像させますね。
しかし幻庵自身の子については、非常に不幸な状況に追い込まれてしまいます。
※続きは【次のページへ】をclick!