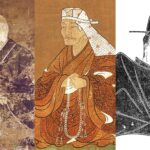皆様は「学校」にどのような思い出をお持ちですか?
充実していたという方もいれば、そうではなかった人、今まさに学生だという方もいたりして、いずれにせよ多かれ少なかれ何らかの思い出はありますよね。
今回は日本屈指の歴史を持っていた、あの学校に注目。
文安三年(1446年)6月30日は、上杉憲実(のりざね)が【足利学校】に「学規三条(校則)」を制定した日です。
日本最古の学校とされる同校の校則を作った――そんなイメージで良いかと思います。
では、同校の歴史的背景やその他諸々を見て参りましょう。

『本朝百将伝』上杉憲実/国立国会図書館蔵
創立者は諸説あり 足利義兼が有力か
足利学校の明確な創立時期はわかっていません。
諸説あり、平安時代から室町時代という幅広さです。入り乱れるにも程があるやろ。
といっても、平安時代説は「天才・小野篁が承和六年か承和九年(それぞれ839年・842年)に作った」という、いかにも信憑性が薄いものです。

小野篁/wikipediaより引用
篁が東国へ来たことはありませんし、承和六年には流刑で隠岐に行っているはずですからね。
小野篁は「毎日地獄へ通って閻魔様の補佐役をしていた」なんて伝説があるような人ですから、「地獄へ通えるくらいなら、上野へ通うなんて朝飯前だろう」とか思われてた?そんな無茶な。
頭のいい人だったからこそ、無理やり結び付けられたのかもしれません。
この小野篁説よりも信憑性が高いのは、12世紀末に足利義兼によって設立されたという説ですね。

足利義兼/wikipediaより引用
義兼は足利氏の二代目。
後の室町幕府初代将軍・足利尊氏の遠いご先祖様です。
校則を作った上杉憲実が、足利学校そのものを作ったという説もありますが、彼以前の時代に「足利には学校がある」という記録が存在しています。
名前や組織はどうあれ、それ以前からこの地に学校があった可能性は高いということです。
また、憲実の主君にあたる関東公方・足利持氏が関わっていた説もあります。
この人がいろいろアレなので、教育という長期的な視野を持っていたかどうかはアヤシイですが。
-

足利氏の始まりは尊氏ではなく義康! 初代~七代までの歴史を一気に振り返る
続きを見る
足利持氏に苦労させられまくりの上杉憲実
少々本筋からずれますが、バックグラウンドとして上杉憲実や足利持氏の話を少々挟みましょう。
上杉憲実は、関東管領を務めてきた山内上杉家の人です。

『本朝百将伝』上杉憲実/国立国会図書館蔵
生まれは越後上杉家ですが、従兄であり山内上杉家の当主だった上杉憲基(のりもと)に跡継ぎがいなかったので、養子入りして関東管領にも就きました。
室町幕府は京都・室町に御所を置いたことからそう呼ばれていますが、鎌倉幕府のシマだった関東を放置するわけにはいきません。
そこで「鎌倉公方」という部署を鎌倉に設置し、睨みを利かせることにしていました。
しかし、尊氏の四男・足利基氏(もとうじ)の家系が代々鎌倉公方に就いたことで、かえって本家である将軍と対立が生まれます。

足利基氏像(狩野洞春画)/wikipediaより引用
要するに「もしかしたらウチが将軍になれてたかもしれないのに!」というわけです。
そんなこと言ったってしょーがないやろ……と後世の我々はツッコミたくなりますが、この問題はかなり長く尾を引きました。
鎌倉公方の補佐役である関東管領は、何かと上方の事情に首を突っ込もうとする鎌倉公方をなだめすかすのが仕事の半分を占めていたといっても過言ではありません。
憲実もその一人で、直接の主である足利持氏が面倒を起こすたびに、幕府へ詫びを入れたり、上方のお坊さんに頼んで仲裁を頼んだりしています。
が、これによって持氏は憲実をやっかむようになりました。
反抗期の高校生かいな……。
永享の乱
足利持氏が応永五年(1398年)、上杉憲実が応永十七年(1410年)生まれといわれているので、持氏はちょうど一回り歳下の若者にあれこれ世話を焼かれていたことになります。
立場や世代の差による価値観の相違があるにせよ、情けなや。
しかも幕府からは「憲実をこっちに引き入れれば、いろいろアヤシイ鎌倉公方を大人しくさせられるかも」と妙な方向に期待されてしまいます。
そして、”永享の乱”という室町幕府vs鎌倉公方の争いに巻き込まれました。
-

室町幕府と鎌倉府が対立した「永享の乱」足利持氏の挙兵で関東に何が起こった?
続きを見る
憲実は幕府方とみなされて戦うことになりましたが、そもそも彼には鎌倉や持氏と敵対する意志はなかったため、家臣が兵を指揮しています。
憲実は幕府に持氏の助命嘆願をし、これが叶えられず、逆に
「お前、そんなに言うなら持氏と一緒にブッコロしてもいいんだよ?^^」(超訳)
と脅されました。
かくして覚悟を決めた憲実。
儒教の本や絵画を足利学校に寄付して身辺整理を進めます。
持氏は自害 教実は親族もろとも隠遁生活へ
しかし、幕府と鎌倉公方の連絡役を勤めていた柏心周操という僧侶に説得され、立場を一転。
憲実は持氏を攻めることに決めます。
結果、持氏は自害し、永享の乱の乱は終わりました。

足利持氏自害の図/wikipediaより引用
憲実は持氏の墓前で自害しようとしたほど後悔していました。
山内上杉家の当主を弟の清方に譲り、隠遁しておりますので、覚悟の程は伝わってくるでしょう。
その後、上方で嘉吉の乱(第六代将軍・足利義教暗殺事件)などが起き、幕府からは「お前がシッカリして関東を抑えといてくれないと困るんだよ!」(意訳)とプレッシャをかけられます。
しかし、公的には復帰しませんでした。
憲実の態度は徹底したもので、自分の子供達も(甥に預けていた次男を除いて)出家させ、決して還俗しないように!と命じているほどです。
自分だけでなく、子供にも権力と関わるな……というのは相当ですよね。
これにより、幕府は上杉清方を正式に関東管領と認めざるを得なくなりました。
しかし、文安元年(1444年)に清方が先に亡くなってさらにゴタゴタしていくことになります……が、そろそろ話を足利学校のほうに戻しましょう。
※続きは【次のページへ】をclick!