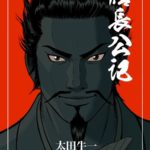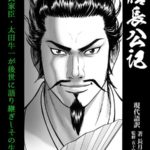加賀百万石と言えば前田利家――。
天文7年12月25日(1539年1月15日)はその誕生日です。
信長・秀吉と共に大出世を遂げた大大名として知られますが、若き日は猛々しい武闘派武将であり、まさしく戦場を駆け回るタイプ。
その頃の利家をざっと三行でマトメますと……
【若き日の前田利家】
・信長側近のエリート集団「赤母衣衆」を引っ張る
・信長お気に入りの茶坊主をたたっ斬る→謹慎
・謹慎を解いてもらうため戦場で敵の首を取りまくる
非常に血気盛んな武将のようであり、この三行だけ読むと「もしかして暴れん坊タイプか?」という印象を受けると思います。

前田利家/wikipediaより引用
では次は前田利家の生涯を、三期でマトメてみたいと思います。
【前田利家の生涯】
第一期:織田信長の側近で大暴れ
第二期:柴田勝家のもとで北陸平定
第三期:天下人秀吉の親友かつ有力家臣
信長に始まり、勝家、秀吉――と、まさに織田家の超中心人物たちと共に過ごしてきたことがご理解いただけると思います。
いわば天下統一事業を常に補佐してきたわけで、彼らに好かれた理由は何だったのか?
前田利家とはいかなる人物だったのか?
62年の生涯を追ってみましょう。
👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅
前田利家 若い頃は信長と
前田利家は天文五~天文七年頃(1536~1538年)、尾張国愛知郡荒子村(名古屋市中川区)で生まれました。
生涯深い付き合いとなる豊臣秀吉とは、同い年かごくごく近い生年です。
父・利春(利昌)が織田弾正忠家に仕えていたため、利家も幼いときから織田信長に仕えました。
長じてからの利家は推定182cm、かつ細身の美丈夫だったといわれているため、おそらく子供の頃から目を引くような容姿だったのでしょう。
いつ頃からなのかは不明ですが、信長と衆道関係にありました。
これは後年になって本人が認めているため、事実と思われます。日頃の行いもさることながら、そういう意味でも信長の目に留まったのでしょうね。
初陣は天文二十一年(1552年)【萱津の戦い】です。
元服前ながら、自ら朱色に塗った目立つ槍を振るい、首を挙げてきたといわれています。
背丈も当時としては相当な大きさなため、力自慢でもあったでしょう。ゆえに「槍の又左」とも呼ばれておりますよね。
実際、初陣を終えた後に信長から「犬千代は肝に毛が生えておる」と称賛された程の戦いぶりだったとか。
萱津の戦いは以下に詳細がございますのでよろしければ併せてご覧ください(記事末にもリンクございます)。
-

萱津の戦いで勝家も活躍|信長公記第11話
続きを見る
右目下に矢を受けたまま敵陣へ
初陣から4年後の弘治二年(1556年)、信長が弟の織田信勝と軍事衝突しました。
【稲生の戦い】と言います。
鬼柴田として恐れられる柴田勝家が、まだ信勝派だった時代で、前田利家は信長サイドで戦いました。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用
このときの活躍が圧巻です。
右目の下に矢を受けながらも、そのまま敵陣に飛び込んだといいます(まるで夏侯惇)。しかも、その矢を射た本人を討ち取ったのだとか。
利家の勇猛さが窺える話でありましょう。
もちろん、これも信長に大いに褒められ、味方を鼓舞することになりました。
「利家はそのまま、矢を抜かずに首実検に参加していた」という話もあるのですが、さすがにちょっと信じがたいですね。このとき隻眼になったという説もあるのですが、定かではありません。
しかし、活躍したのは間違いない話で、今回の功績で加増され、利家は初めて自分の家臣を召し抱えることができました。
そのうちの一人・村井長頼は、要所要所で利家と前田家の窮地を救うことになります。
なお、稲生の戦いの詳細もまた以下にございますので、興味のある方はご確認を。
-

稲生の戦いで信長一騎打ち!|信長公記第19話
続きを見る
茶坊主を信長の前でなで斬り!
松嶋菜々子さん主演で話題になった大河ドラマ「利家とまつ」。
その、まつ(篠原家)と結婚したのは永禄元年(1558年)のことです。
二人の母が姉妹、つまり前田利家とまつはイトコ同士であり、結婚当初から円満な夫婦だったようです。翌年にはさっそく子宝に恵まれています。
しかし程なくして、公私共に順調に見えた利家を、思わぬトラブルが襲うのです。
信長の側近くに使える茶坊主の拾阿弥。
この男が、利家の笄を盗み、更にはあろうことか利家を侮辱したのです。
笄というのは髪を整えたり、髪型を崩さずに頭皮をかくための道具です。利家は若い頃から傾奇者としても有名でしたので、身だしなみには特に気を使い、愛用していたのでしょう。
しかも、このとき盗まれたのは、まつの父・篠原主計の形見の品でもありました。利家にとっては、二重に大事なものだったのです。
当初、利家は怒りをこらえて信長に訴えました。
なぜか信長は拾阿弥を咎めることはせず、さらに佐々成政までもが拾阿弥の肩を持ったため不満と怒りは膨らんでいくばかり。

佐々成政/wikipediaより引用
そしてとうとう、拾阿弥を自分の手で斬り捨ててしまうのです。しかも信長の目の前で斬ったといわれていますから、当てつけもあったのでしょう。
当然、信長は大激怒!
一時は利家を死罪にしようとして、他の家臣たちになだめられ、出仕停止に留めておくこととなりました。
桶狭間で首3つ さらには森部の戦いで
たとえ命が助かっても、武士は武功を立てて家臣や家族を養わなければなりません。
出仕停止は、いわば無職状態。生活は困窮します。
前田利家はなんとか許しを得るべく、密かに信長の戦に参加し、功績を挙げようとしました。
例えば、あの【桶狭間の戦い】に参加したときには敵の首を3つもとる大殊勲。
それでも許されず、今度は【森辺の戦い(森部の戦い)】で足立六兵衛という武将の首を討ち取ると(美濃では「首取り足立」として知られていた)、ようやく帰参が許されます。
しかも新たな所領も与えられました。
言葉で説明してしまいますとあっという間ですが、謹慎から復帰までにおよそ二年間。
子供も生まれていますので、妻のまつも相当の苦労をしたでしょう。
利家は、信長に勘当される前から「赤母衣衆」という織田家の側近エリートに選ばれていた可能性があり、普通に出世していれば生活苦などとは無縁のはずでした。

織田信長/wikipediaより引用
そんなこともあってか、利家は生涯、この二年間のことを教訓としていました。
「落ちぶれたときに声をかけてくれる者こそ、本当に信用できる」
おそらく豊臣秀吉もその中の一人でしょう。さらには加藤家勝という武将にもお世話になっていたとか。
また、利家は後に自ら算盤を用いて計算もしておりました。
それもこの二年間で、相当お金に苦労したからだそうで……よほどキツかったのでしょう。
赤母衣衆として、常に信長の側にいて
無事に帰参を許された前田利家は、その後、織田家の主な戦いに参加していきます。
斎藤龍興を稲葉山城から追放し、岐阜城とあらためた【美濃攻め】に始まり、伊勢への侵攻や、浅井長政・朝倉義景らとの戦い。
【野田城・福島城の戦い】でも本願寺相手に戦功を挙げておりますが、その割に、他の合戦であまり大活躍の話が聞かれないのは、前田利家が信長の馬廻衆として、主君のすぐ側で旗本を率いていたからと目されております。
一番槍を狙って敵に突撃するような立場ではなかったんですね。
そして、信長が岐阜に本拠地を移動した1567年から約10年後、利家にとっては運命の潮目が変わります。
天正三年(1575年)から、不破光治・佐々成政らと共に、北陸方面の責任者・柴田勝家の目付役として着任するのです。
不破・佐々・前田の三名は、府中三人衆とも呼ばれました。
佐々成政と前田利家は、【長篠の戦い(1575年)】で共に鉄砲奉行として活躍しており、越前でも同じエリアを府中三人衆で信長の代官のような役割で統治しております。
そして勝家の目付役も請負ながら、北陸方面軍での戦いに参加していくのです。
元朝倉家臣団のドタバタから発生した【越前一向一揆】は、すでに信長が出陣して平定しており、次は加賀へ。
一進一退を繰り返しながら、徐々に、諸衆を攻略していきました。
しかし、そう簡単にことは進みません。越後から最強の敵が現れるのです。
そう、上杉謙信です。

上杉謙信/wikipediaより引用
軍神に襲われフルボッコにやられる
織田家の加賀侵攻に対し、当初、謙信は一向一揆を扇動するなどして対抗しておりました。
上杉家は北陸方面だけに注力すればよいのではなく、信濃の武田や上野の北条など、強敵と接するエリアが多かったからです。
が、その状況も武田信玄の死などにより変わりつつありました。
そして1577年、ついに柴田勝家率いる織田家の北陸方面軍とぶつかりました。
【手取川の戦い】です。
簡単に言うと
「味方を助けるため七尾城に向かっていたら城が陥落しちまった。仕方ないから引き換えしたら、手取川を渡ったところで軍神に襲われて木っ端微塵にされたぜ」
というものです。
※松任城のすぐ南にある手取川が主戦場となった手取川の戦い
織田家としては消化不良の敗戦だったんですね。
もともとこの合戦は、援軍に来ていた豊臣秀吉がいきなり戦線離脱をするなど、最初から雲行きの怪しい展開でした。
いずれにせよ、この手取川の戦いは柴田勝家の合戦という印象もありますが、前田利家も参加しており、おそらく軍神の恐怖と屈辱を味わったことでしょう。
信玄に続き謙信も亡くなる信長の強運
織田信長は実力も凄いが運もハンパじゃない――それを思わされるのが武田信玄の死のタイミングであり、そしてそのライバル上杉謙信でありましょう。
手取川の戦いでフルボッコにやられたその翌年の1578年、軍神と恐れられた謙信が突如亡くなるのです。
トイレで脳出血を起こしたと目され、跡継ぎも決めないままの死亡だったため、上杉家では景勝と景虎による内紛が勃発し(御館の乱)。

上杉景勝/wikipediaより引用
織田家にとっては最高の展開を迎えました。
そうは言っても織田家も決して順風満帆ではありませんでした。
1578年、有岡城の荒木村重に突如裏切られ、前田利家も同城への攻撃参加を命ぜられたのです。
前田利家は、いったん北陸を離れ、有岡城の包囲戦や三木城(播磨)の戦いに駆り出されます。
そして、その翌年に荒木村重が城を脱出し、有岡城の戦いが終わると、今度は柴田勝家と共に加賀平定に尽力し、無事にこれを平定します(1580年)。
合戦ばかりが続く織田家に、信長がご褒美のイベントを用意したのは、その翌年、天正九年(1581年)のことです。
織田家の各武将たちが着飾り、高価な名馬に乗って、京都の街をパレードする【京都御馬揃え】が開催されました。
前田利家は、これに越前衆の一人として参加。
名実ともに織田家の重臣として存在感を放ち、同年8月には、信長から能登一国を与えられて大名の仲間入りを果たしました。
能登入りして七尾城を築城した後も、攻撃の手を緩めず、6月3日には柴田勝家や佐久間盛政らと共に魚津城を陥落(魚津城の戦い)。
さらなる作戦を講じているところで、その一報は届けられました。
本能寺の変です。
本能寺直後は北陸で動けなかった
明智光秀が織田信長を討ったことで有名な本能寺の変。

明智光秀/wikipediaより引用
当然、北陸方面の諸将にも迅速かつ的確な判断が迫られました。
もともと北陸方面に厚い体制が敷かれていたのは、越後の上杉家に備えるためです。
謙信はおらず、御館の乱で一度は分裂していた同家も、上杉景勝と直江兼続のもとで再び家中はまとっており、将兵の忠誠心は決して低くはありません。
景勝も、自ら討ち死にする覚悟で織田家との対決に臨んでいました。
そんなに気合の入っていた上杉家の面々が、もし信長の急死を知ったとしたら……どうなるかは火を見るより明らかですよね。
攻守どころか形勢逆転さえ見えている状況の中、勝家の甥である柴田勝豊・佐々成政・佐久間盛政などが仲違いをしてしまったといわれています。
また、勝家と成政の間にも、剣呑な空気が流れていたようです。
その間に立って仲裁したのが、前田利家。
結局、利家は能登の一揆勢力や反織田家の諸衆の動きに囚われ、その場から動けずに、明智光秀は山崎の戦いで秀吉に滅ぼされるのでした。
本能寺の変から11日後、6月13日のことです。
勝家と秀吉に挟まれて
前田利家は、たびたび他者の仲裁に動いたという記録が多々あります。
しかし、それだけに板挟みを味わったこともありました。
最大の問題は
◆自身が共に戦ってきた柴田勝家
◆利家の娘(豪姫)を養子入れさせるほど仲の良かった豊臣秀吉
という両者の争いに巻き込まれてしまったことでしょう。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
清洲会議などを経て、利家にとっては旧友ともいえる間柄の秀吉と、上司的存在の勝家が対立し、ついに軍事衝突に至ると、苦しい立場に追い込まれてしまいます。
単純に「秀吉の調略によって、利家は早い段階で勝家を裏切るつもりになっていた」という見方もありますね。
かくして天正十一年(1583年)【賤ケ岳の戦い】が勃発すると、敗れた勝家は妻のお市と共に自害、利家は生き残りました。
賤ヶ岳の戦いについては、秀吉が戦場から離れたのをキッカケに佐久間盛政が中川清秀の陣へ突撃し、その後、柴田軍に属していた利家が実質秀吉に味方をするようなカタチで戦線から離脱したことで、柴田軍が敗北しております。
勝家陣営から見れば、利家の裏切りで敗れたとなるでしょう。
この辺の詳細は、以下、佐久間盛政の記事でご確認いただけると幸いです。
-

佐久間盛政の生涯|鬼玄蕃と称された柴田勝家の甥は秀吉の誘いを笑って一蹴
続きを見る
最大のピンチ!末森城の戦い
1584年、豊臣秀吉と徳川家康の間で小牧・長久手の戦いが勃発。
前田利家は、佐々成政と北陸方面にとどまっておりました。
しかし、ここで前田家最大のピンチが訪れます。
秀吉と袂を分かった佐々成政が、突如、前田利家の末森城に襲いかかったのです。
同城は、規模はさほど大きくないながら、能登半島の付け根の部分という要衝に位置する重要な城でした。
※黄色い城が末森城の位置
地図をご覧のとおり、南(加賀)・北(能登)・東(越中)という三カ国への侵攻が可能。
利家にとっては金沢へ攻め込まれる危険性があり、佐々成政にとっては自領を防衛するための最前線基地になり得たのです。
そこで利家は、連絡が届くやいなや兵わずか2,500で救援に向かい、同城の防衛には成功します。
が、佐々成政との戦いは始まったばかりで、そのまま北陸で小競り合いを続けることとなりました。
しかし小牧・長久手の戦いで秀吉と家康が手打ちになり、豊臣秀長と豊臣秀次の援軍が利家のもとにやってくると、後ろ盾を失った佐々成政は敗北を覚悟。
ほどなくして秀吉傘下に降伏することとなるのでした。
晩年の秀吉に最も信頼され五大老に
それからの前田利家は、秀吉の友人かつ第一の家臣というような立場で、武働きと出世を繰り返していきました。
九州征伐などでは京・大坂の警護を担当し、小田原征伐や奥州出征の際には、戦だけでなく統治・外交でも能力を発揮しています。
武勇がよく話題になる利家ですが、丹羽長秀や堀秀政のような万能タイプだったんですね。
朝鮮の役では渡海はせず、名護屋城(佐賀県)に駐留していました。

ドローンで空撮した名護屋城の本丸と遊撃丸
また、文禄元年(1592年)5月に朝鮮の首都・漢城府が落ちた時、自ら渡海しようと逸る秀吉を、家康と利家が諌止したといわれています。
この件に限らず、秀吉存命中の利家と家康は、政務などで協力することも珍しくありませんでした。
天正二十年(1592年)7月に秀吉の母・大政所危篤がもたらされ、秀吉が名護屋を離れたときも、名護屋にいる諸将の指揮などを二人で行っています。
慶長三年(1598年)3月の醍醐の花見には、正室・まつと参加しました。
そして、その翌月には老齢や病気を理由として、嫡子・利長に家を譲っています。草津温泉(群馬県)へ湯治にも行っていたそうなので、寿命を意識して養生しようとしていたのかもしれません。
しかし、秀吉は家督の継承は認めても、利家が隠居生活に入ることは許しませんでした。
いわゆる「五大老」を任じたのは、利長に家督を譲った後の話。幼い秀頼の後見になることも頼まれ、大坂城にとどまることになります。
自分の家の仕事は手放していますが、隠居とは言いにくい状態ですよね。
ちなみに五大老、そして石田三成らの五奉行とは以下のメンバーになります。
【五大老】
・徳川家康
・前田利家
・宇喜多秀家
・上杉景勝
・毛利輝元
※小早川隆景が生きている頃は6名だった
【五奉行】
・浅野長政
・前田玄以
・石田三成
・増田長盛
・長束正家
家康を制するため誓紙を交わしたその後で……
慶長三年(1598年)8月に秀吉が逝去すると、いよいよ前田利家には頭痛の種が増えていきます。
家康が伊達家や蜂須賀家に養女を嫁がせ、自分の勢力を強めようとしたのです。
秀吉は生前、こうした政略結婚を防ぐため「大名同士の婚姻を禁ずる」と明確に決めていました。
逆らうということは、豊臣政権を守るつもりがない、と宣言したも同然。
利家たち、豊臣恩顧の大名・武将たちにとって見過ごすことのできない事態となると、利家・家康双方の屋敷に、それぞれの派閥の大名が集まったりして、半年近く騒動が続きました。
徳川家康も、さすがに前田利家との全面対決は避け、互いに誓紙を交換することで和解としています。

徳川家康/wikipediaより引用
利家としては秀吉の遺志通り、家康や他の大名たちと共に、秀頼を守り立てていくつもりだったのでしょう。
しかし、その前に自身の寿命が尽きてしまいました。
家康との和解からおおよそ2か月ほど経った慶長四年(1599年)閏3月3日に、利家はこの世を去っています。
享年62。
政治的な場面では決して荒々しい言動をしなかった利家ですが、武将らしい気概は最後まで持っていました。
「閻魔でも牛頭馬頭でも相手にしてくれるわ」
前田利家とまつとの間でこんな話が残っております。
「貴方は若い頃からたくさん戦で人を殺めたので、後生が恐ろしゅうございます。どうかこの経帷子(きょうかたびら)をお召しになってください」
「確かにわしは多くの敵を殺してきたが、理由なく殺したことも、惨い殺し方をしたこともない。だから地獄に落ちるわけがない。もしも地獄に落ちたなら、先に逝った者たちとともに、閻魔でも牛頭馬頭でも相手にしてくれるわ。その帷子は、お前が後からかぶってこい」
閻魔は言わずもがな閻魔大王で、牛頭(ごず)と馬頭(めず)はそれぞれ、牛の頭・馬の頭をした地獄の拷問人のことです。
「悪鬼羅刹相手だろうとまとめて戦ってやる」という気概は、死の床にある人とは思えませんね。
勇猛さと、人の間に立って仲を取り持つという二つの面。
それが利家の大きな魅力だったのでしょう。
👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅
あわせて読みたい関連記事
-

利家の妻・芳春院まつは戦国一の女房か~加賀百万石を補佐した生涯を振り返る
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

佐々成政の生涯|信長の側近から大名へ 最期は秀吉に敗れた反骨の戦国武将
続きを見る
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
-

信長に美濃を追われた斎藤龍興の生涯~織田家へ執拗に反撃を繰り返した道三の孫
続きを見る
【参考】
国史大辞典
岩沢愿彦『前田利家 (人物叢書)』(→amazon)
谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)
前田利家/wikipedia