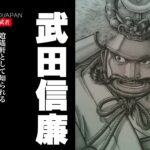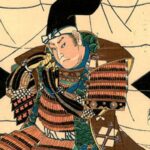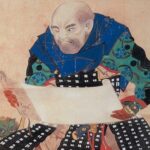まずは以下の肖像画三枚を見比べて欲しい。

武田信玄の肖像画三枚/wikipediaより引用
中央にいる恰幅の良い武将、これぞ武田信玄!と、思う方もいらっしゃるであろう。
では右側にいる武将は?
こちらも信玄を描いたものとして有名であり、ウィキペディアなどでもTOPのイメージ画像に使われてるのでご存知の方も多いはず。
少し戸惑うのが左側の武将か。
もしかして、これも?……というと、実は上掲三枚のうち二枚が信玄を描いたものとされ、「もう一枚は別人」と考えられている。
一体どういうことなのか?
三枚の肖像画を確認してみよう。
高野山持明院「武田晴信像」
まずはこちらの一枚。

高野山持明院に寄進された武田晴信像/wikipediaより引用
高野山持明院に寄進された「武田晴信像」として有名な一枚。
侍烏帽子をかぶり直垂(ひたたれ)を着用した正装姿であり、出家前の姿と推定されているため「武田信玄像」ではなく「武田晴信像」と呼ばれている。
信玄といえば、フィクションでも恰幅の良い姿を思い浮かべてしまいがちなので、いささか違和感を持たれる方もいらっしゃるだろうか。
意匠(デザイン)に用いられている武田菱も、よく知られたひし形の「割菱」ではなく、花をモチーフにした「花菱」であることも違和感の一つかもしれない。
しかしこの一枚、武田氏滅亡後に高野山引導院(後に持明院)へ寄進された武田勝頼遺品とされることから、本物の信玄であろうとされる。
高野山成慶院「伝吉良頼康像」
次にこちらの一枚。

高野山成慶院「伝吉良頼康像」/wikipediaより引用
「伝吉良頼康像」ともあるので、これが別人なんだな……。
と一瞬思ってしまうかもしれないが、実は武田信廉(逍遙軒)が描いた信玄とされている。
武田信廉は、戦国武将というより絵師としての実力が高く評価され、この一枚も原本ではなく模写されたものながら、経年劣化による色彩の衰えを感じさせない色使いがなんとも絶妙ではないか。
足元に法螺貝が置かれた甲冑姿は今にも戦場に臨みそうな迫力があり、信玄の弟だからこそ描くことのできた作品とも言える。
信廉の絵師としての実力は、父・武田信虎像や母・大井夫人像の作者としても折り紙付き。

武田信虎/wikipediaより引用
なお、武田信廉の生涯については以下の記事を併せてご覧いただきたい。
-

武田信廉(逍遥軒)の生涯|信玄の影武者として 一族を描いた絵師として
続きを見る
高野山成慶院「武田信玄像」
最後にこの一枚。

高野山成慶院「武田信玄像」/wikipediaより引用
頭脳明晰で怜悧な判断力を持ち合わせた最強の武田信玄――その事績については「武田信玄の生涯を史実から徹底解説」に詳しくあるが、この一枚こそまさにイメージ通りであろう。
三枚のうち二枚が本物で残り一枚が違うのであれば、最も信玄っぽいこの作品が実はそうではない?
結論から申し上げると、こちらは「能登畠山氏の可能性」が指摘されている。
作者は、あの長谷川等伯。
当時を代表する偉大な絵師であるが、だからこそ信玄ではないのでは?と指摘される。
等伯が、生前の信玄に対面する機会が無いであろうということや、太刀や笄などに武田菱ではなく二引両紋が用いられているためだ。
さらには労咳(結核)を患っていたとされる割に恰幅が良いことからも不自然さが窺えるという。
ではなぜ「能登畠山氏の可能性」なのか?
というと長谷川等伯が能登国七尾(石川県七尾市)の武家出身であるため。
等伯は天文8年(1539年)に生まれ、染色業者・長谷川宗清の養子となった。
能登を出て上洛したのは元亀2年(1571年)であり、元亀4年4月12(1573年5月13日)に亡くなった信玄を描ける可能性は低く、逆にそれ以前に「能登畠山氏」に接する機会はある。
これぞ信玄っぽい――その一枚が実は違うとは悲しいが、長谷川等伯ら絵師の凄さに触れることでもあるのだろう。
あわせて読みたい関連記事
-

武田信繁の生涯|理想の補佐役とされる信玄の実弟“古典厩”は川中島に散る
続きを見る
-

武田信虎の生涯|信玄に国外追放された実父は毒親に非ず?81年の天寿を全う
続きを見る
-

山本勘助の生涯|実在すら疑われていた隻眼の武将は信玄の参謀と言えるのか?
続きを見る
-

穴山信君(梅雪)の生涯|信玄の娘を妻にした武田一門の武将は卑劣な裏切り者か
続きを見る
参考文献
- 国史大辞典(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979–1997年刊)
出版社: 吉川弘文館(ジャパンナレッジ公式紹介ページ) - 萩原三雄 編著『武田信玄 謎解き散歩』(新人物文庫, KADOKAWA/中経出版, 2015年3月9日, ISBN-13: 978-4046004260)
出版社: CiNii 書誌 NCID: BB22273551 |
Amazon: 商品ページ