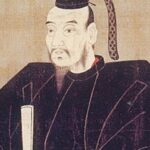慶長十五年(1611年)12月3日は、島津家の家臣・新納忠元が亡くなった日です。
漢字のクセがなかなか強い御方ですよね。
「にいろただもと」と読みます。
印象的な名前だけでなく、彼は「戦国名家臣ランキング」なんてものがあったとしたら、おそらく上位に入るであろう名家老。
島津と言えば、父親の島津貴久と、その息子・四兄弟ばかりに目が移りがちですが、ここは一つ強力な家臣団も見てみたいと思います。
なお、島津には、新納だけでなく【島津の退き口】で大きな働きをした「中馬重方(ちゅうまんしげかた)」という魅力的な武将もおります。
記事末にリンクを張っておきますので、よろしければ後ほどご覧ください。
お好きな項目に飛べる目次
貴久~忠恒の戦国島津家四代に仕える
忠元は、大永六年(1526年)に生まれました。
新納氏は島津家の親族にあたる家で、忠元はその中でも庶流の生まれです。
彼も鎌倉以来の名家の一員というわけですね。
-

母が頼朝の乳母子だった島津忠久~九州・薩摩に屈強な武家を築く
続きを見る
13歳で当時の島津家当主だった島津忠良(日新斎)にお目見え。
以降、その息子の島津貴久、続けて島津義久、島津義弘、島津忠恒に仕えました。
一騎打ちで勝ったり、負傷しながらも戦い続けたり。
戦場ではかなり勇猛な武将だったといわれています。
若気の至りかと思いきや、後者のエピソードは43歳のときのことであり、当時としては老人に入りかけた頃合ですから、忠元の勇猛さがうかがえますね。
それでいて決して猪武者ではない文武両道の勇将で、1年以上も籠城していた敵を降伏させたこともありました。
しかも、自ら人質となって城を明け渡させたのだそうです。タクティクスオウガか。
-

島津四兄弟の父・島津貴久は大隅を支配した中興の祖!その実績に注目
続きを見る
-

島津義久は大友や龍造寺を相手にどうやって戦国九州を統一した?
続きを見る
-

島津義弘(四兄弟の次男)が鬼島津と呼ばれる功績が凄い 85年の生涯
続きを見る
戸次川で討ち取った長宗我部の遺骸を丁重に送る
そんなデキる武将ですから、もちろん島津家の主要な戦いにも参加。
天正12年(1584年)の【沖田畷の戦い】では「ただ一直線に斬り進め!」というムチャクチャにも程がある、されど、ある意味薩摩らしい戦術で、龍造寺隆信を討ち取っています。
そうかと思えば、実に泣かせる男気もあり、最たる例が豊臣秀吉の九州征伐における緒戦【戸次川の戦い】でしょう。
-

四国の戦国武将・長宗我部信親の最期「オレは戸次川の戦いで死ぬ」
続きを見る
-

秀吉の下で大出世と大失態を演じた仙石秀久~センゴク64年の生涯
続きを見る
戦闘そのものの経過は上記の記事をご覧いただくとして、忠元にはこの戦いが終わった後の逸話があります。
戸次川の戦いの後、自分が倒した相手である長宗我部信親(元親の嫡男)の遺骸を引き取るため、長宗我部家の家臣がやってきました。
忠元は「信親殿ほどの人物を討ってしまったとは申し訳ない」と、涙を流して詫びたというのです。
父親の長宗我部元親に負けず劣らず、長宗我部信親は、この世代の武将でもかなりの傑物とされており、薩摩にも評判が伝わっていたんですかね。
-

長宗我部元親は戦乱の四国をどう統一した?失意に終わった61年の生涯
続きを見る
誠意の証として、長宗我部家の本拠である土佐の岡豊城(おこうじょう)まで、僧侶を同行させたともいわれています。
僧侶は大変な旅だったでしょうが、忠元の律儀さ誠実さがうかがえるでしょう。
秀吉に向かい「何度でも敵になってみせましょう」
一方で、秀吉に従うことは最後まで是とせず、主の義久が降伏してようやく矛を収めました。
「自分の意見が異なっていたとしても、主の判断に従う」
まさに家臣の鑑ですね。
盲従すればいいというものでもありませんが、義久は後に徳川家康から「大将の鑑」と評された逸話があるほどの判断力の持ち主ですから、忠元も従おうと思ったのでしょう。
しかも降伏後に秀吉から「まだワシと戦う気は持っておるのか?」と問われたところ、「島津義久様が立ち上がるなら何度でも敵になってみせましょう」と返答しています。
この手のヤリトリ、大好物なのは秀吉だけじゃなく薩摩武士たちにも刺さったようで、後に語り草となっています。
まぁ、自分が一介の武士だとしたら「こんな人についていきたい!」と思わせるようなセリフですよね。実際についていったら「ただ一直線に斬り進め!」と言われて戦慄してしまいそうですが。
-

徳川家康はなぜ天下人になれたのか?人質時代から荒波に揉まれた生涯75年
続きを見る
-

豊臣秀吉のド派手すぎる逸話はドコまで本当か?62年の生涯まとめ
続きを見る
なお、新納は知名度の割に知行(領地)も少なかったようで、秀吉から引き抜きのお誘いがありましたが、これも断っています。
ますます薩摩隼人の心を惹きつけたことでしょう。
金銭欲にあまり興味を示さない(というかむしろ遠ざける)姿勢というのは、この辺りからの伝統もありそうですよね。
※続きは【次のページへ】をclick!