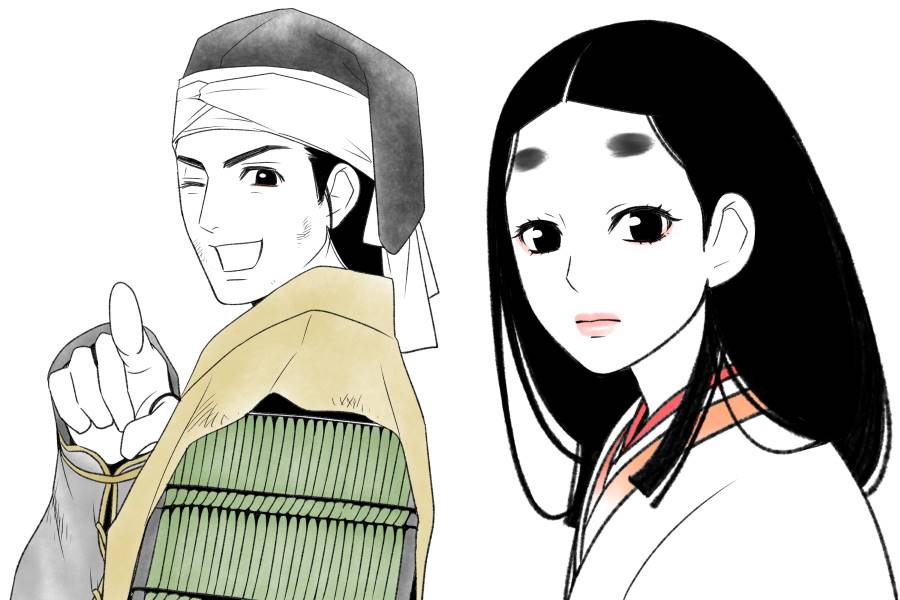織田信長が京都で政務や社交をしていた、天正三年(1575年)3月。
その下旬に、東の方で動きがありました。
甲斐の武田勝頼が、三河の足助へ攻め寄せたのです。
勝頼が織田・徳川の勢力圏へ牽制の出陣
足助は、現在の豊田市足助町。
当時は明知城(恵那市)や高天神城(掛川市)などが武田氏の勢力下にありましたので、浜松城を本拠とする徳川家康にとっては、じりじりと追い詰められている形になります。
足助方面から徐々に南下されると、織田氏と徳川氏の連携が絶たれかねません。
地図で確認しておきますと……。
【武田方=赤色の拠点】
山梨県内の躑躅ヶ崎と新府城(右2つ)
静岡県の高天神城(下)
明知城(左)
【徳川方=黄色の拠点】
足助(左)
浜松城(下)
むろん放置するわけにはいきませんが、あいにく信長は留守。
そのため信長の嫡男である織田信忠が尾張の兵を率いて出陣しました。
-

織田信忠の生涯|なぜ信長の嫡男は本能寺の変で自害せざるを得なかったのか
続きを見る
すぐに動ける信忠がまず出陣!
信忠が正式に織田家の家督を継ぐのはもう少し後の話です。
ただし、それ以前から、東美濃や尾張については部分的に権限を認められていたようで、信忠の名でいくつかの寺院へ禁制を発行したり、地侍への知行を安堵していたことがわかっています。
【小谷城の戦い】や【長島一向一揆】では、信忠は信長に同行していましたし、指揮官としての振る舞いも学んだのではないでしょうか。
おそらくはこのときの上洛にあたり、信長は信忠に留守中のあれこれを言い含めていたことでしょう。
そうなると、信長の帰りを待つより、すぐに動ける信忠がまず出陣する――というのは理にかなっています。
ただし、このときは武田勝頼とは派手なぶつかり合いには発展せず、すぐに帰還したようです。
当時、信忠が18歳の若者であったことを考えると、”迅速に出陣しながらも、深追いせず、トラブルも起こさず、無事に帰ってきた”というのは、武将として優れた素質を有していたからではないでしょうか。
しかし……信忠の心中を考えると、少々切ない面も。
※続きは【次のページへ】をclick!