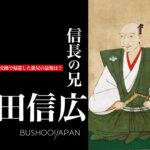大河ドラマ『麒麟がくる』で話題になった徳川家康の幼少期。
竹千代という名の少年家康が人質として屋敷に囚われ、明智光秀の籠に隠れるシーンは、見ていて辛いものがあった。
後の天下人になるとはいえ、当時はまだまだ幼い少年が、なぜ、あのような過酷な目に遭わねばならなかったのか。
残念ながら2023年大河ドラマ『どうする家康』では人形遊びに興じる、才気に乏しい少年像だったが、史実の家康はおそらく常人には得難い感性を己の中に醸成させ、それが征夷大将軍へと繋がったのであろう。
本稿では家康という大人物の土台となった、苦難の「竹千代」時代にスポットを当ててみたい。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
竹千代が生まれたとき鳳来寺の真達羅大将が消えた!?
徳川家康は岡崎城(愛知県岡崎市)で生まれた。
幼名は前述の通り「竹千代」。
父は岡崎城主の松平広忠(安祥松平家第5代宗主・後に松平宗家8代宗主)で、母は水野忠政の娘・於大の方(伝通院)である。
2人はなかなか子宝に恵まれず、鳳来寺へ子授けの祈願に行くと、「寅年、寅月、寅日、寅の刻」に竹千代が生まれ、同寺の「真達羅大将(しんだらたいしょう)」が消えたという。
真達羅大将とは、本尊・薬師如来(峯之薬師)を守る十二守護神の一人(寅神)。
家康の死後、境内には「鳳来山東照宮」が建てられ、参道に阿吽の狛犬ならぬ狛虎が置かれた。
ちなみに鳳来寺は、徳川四天王の一人・井伊直政が虎松と呼ばれ、今川家に命を狙われていたときに匿われていた寺でもある。

参道の阿吽の虎(鳳来山東照宮)
竹千代という名は、連歌の会「夢想之連歌」で詠まれた
「めぐりはひろき園のちよ竹」
に由来する。
稱名寺(碧南市築山町)で行われた催しであり、「徳川家祖廟」(松平初代親氏らの廟所)、渡宋天満宮、三州大浜東照宮がある、いずれも同家にとって縁の深い場所だ。

「竹千代」命名の寺・稱名寺(碧南市)
武家の長男として、期待と不安が予期されたであろう竹千代は、6歳にして最初の試練が始まった。
三河国の西から攻め入ってきた織田信秀(信長の父)に対抗するため、宗主・松平広忠が援軍を求めた相手は遠江駿河の支配者・今川義元であった。
※以下は今川義元の関連記事です
-

戦国大名・今川義元 “海道一の弓取り”と呼ばれる名門 武士の実力とは?
続きを見る
人質をよこせば、援軍を送る──。
そんな義元の要求に応じた松平広忠と竹千代は、ここで予期せぬ不幸に遭遇する。
駿府に送り届ける途中、田原城主・戸田康光によって奪還され、そのまま敵方の織田信秀へ売られてしまったのだ。
竹千代は、熱田の豪商・加藤図書助順盛の屋敷「羽城」に幽閉された。現在の名古屋市熱田区伝馬である。
それにしても……なぜ戸田氏は竹千代を奪ったのか。
原因は、過去に今川義元に攻められたことだともいうが、真相は今なお不明である。
-

今川の人質となる家康を裏切って織田へ送った戸田康光 その後はどうなった?
続きを見る
雪斎が信広を生け捕りにして、竹千代と人質交換
天文18年(1549)年3月6日、松平広忠が死んだ。
このとき8歳になっていた竹千代は、織田家での人質生活が続いており、父の死に目に会うことは出来ていない。
にわかに事態が動き出したのは、今川義元の軍師・太原雪斎がキッカケであった。
僧侶(臨済寺二世住職)でありながら、織田方の安祥城を陥落させた雪斎は、織田信広(織田信秀の側室の子・織田信長の庶兄)を生け捕りしにし、笠覆寺(名古屋市南区笠寺上新町)で【竹千代との人質交換】を成し遂げたのである。

安祥城跡(安城市)
-

信長の兄・織田信広は家督を継げずに謀反を画策?それでも信長に重用された理由
続きを見る
居城の岡崎城には、今川家臣が城代として入城し、三河国は実質的に今川氏の属領となった。
まだ8歳の竹千代は、駿府の松平屋敷(通称:竹千代屋敷or人質屋敷)で暮らすことになる。
竹千代は、駿府の松平屋敷に入るとすぐに礼服に着替え、少将宮で武運長久の祈願をしてから、今川義元と対面したと伝えられている。
後の天下人らしく、字面からも幼き頃から利発そうな雰囲気が伝わってくる。
あるいはこれが武家の子息の覚悟だろうか。
※続きは【次のページへ】をclick!