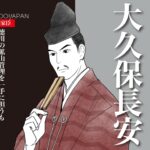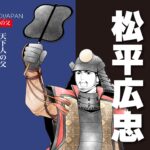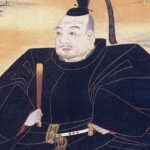こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【大久保忠世の生涯】
をクリックお願いします。
忠世の人柄が見える直政や数正
家臣団で緩衝材の役目も果たした大久保忠世――最も著名なエピソードが、天正壬午の乱の際に、井伊直政をたしなめた話でしょう。
このとき、陣中で食事を共にしようと、忠世は直政を自分の陣幕へ招きました。

井伊直政/wikipediaより引用
戦の最中ですので、食事は極めて質素なもの。芋の葉や茎を煮て、味噌で味をつけた芋汁だったそうです。
他の武将が食べる中、直政があまり箸を進めないので、忠世が不思議に思って尋ねると、直政は
「醤油はありませんか」
と言ったのだとか。
陣中で調味料の選り好みをするのか――他の武将たちが、そう直政を非難する中、忠世はこのように訓戒したと伝わります。
「このようなものですら、兵や農民の口には入らないこともある。この芋汁の味を忘れてはならないぞ」
慈愛の心がうかがえる言葉ですが、直政は部下に厳しいことで有名な人ですので、そのままの意味では伝わらなかったのかもしれませんね。
石川数正が秀吉のもとへ
また、小諸城を預かっていた期間には、こんなこともありました。
天正十三年(1585年)に上田城を攻めていた頃のこと。
幼き頃から家康と共にしていた石川数正が出奔して豊臣秀吉のもとに向かうという、徳川家を揺るがすような大事件があり、その対応のため、忠世が家康に呼び出されました。

豊臣秀吉(右)のもとへ走った石川数正/wikipediaより引用
しかし、最前線に等しい小諸城の守将を空席にしておくわけにはいきません。
そこで忠世は弟の忠教を呼び、こう言い残したとされます。
「私はこの地にやってきて以来、家康様に命を捧げた。この命をお前に与えるので、代わりにこの城を守ってくれ」
「お前も同じように命を差し出せ」と言わないあたりに、忠世の人柄がうかがえますね。
幸い、忠教が命を懸けるような事態は発生しませんでした。
小田原に石高4万5000石を得るが……
家康も、大久保忠世の忠義や仕事ぶりには一目置いていました。
天正18年(1590年)の小田原征伐後に家康が関東へ移った後、秀吉の意向もあって、忠世は後北条氏が去った後の小田原城を与えられました。

小田原城
石高は4万5000石――徳川家臣の中で井伊直政・本多忠勝・榊原康政に継ぐ四番目の大きさです。
“徳川四天王”という看板ブランドがないため、知名度では落ちる忠世ですが、その活躍や重要度では引けを取らなかったと言えるでしょう。
その後は大きな事件に巻き込まれることなく、文禄3年(1594年)9月15日に天寿を全うしました。
享年63。
家督は嫡子・大久保忠隣(ただちか)に受け継がれ、幕府でも重い立場になりました。
忠隣は小姓として家康の側近く仕えていたため、家柄や父の実績、そして本人も主君の覚えがめでたい状態でしたので、納得の出世です。
しかし、彼が京都へキリシタンの取り調べに行っている間、与力である大久保長安の不正が発覚し、連座する形で改易になってしまいます。
通称【大久保長安事件】とされているものです。
※以下は「大久保長安と事件」の関連記事となります
-

大久保長安の生涯|武田滅亡後に徳川で重用されるも不正蓄財で息子は全員切腹
続きを見る
長安が亡くなった後に不正に貯めたと思しき財産が見つかったというもので、実態は謎多き事件ですが、長安の息子たちは全員切腹を命じられ、断絶するという厳しい処分が下されています。
忠隣の権勢を削ぐための陰謀だったのでしょうか。
忠隣は井伊直孝の下に預けられるも、将軍家から許されることはなく、出家したといいます。
しかし、その孫であり、忠世にとっての曾孫である大久保忠職が存続を許されたので、忠世も草葉の陰で泣いても、号泣するまでには至らなかったことでしょう。
あわせて読みたい関連記事
-

松平広忠の生涯|織田と今川に挟まれた苦悩の24年 最後は謎の死を遂げる
続きを見る
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
-

石川数正の生涯|なぜ秀吉の下へ出奔したのか 豊臣政権の崩壊後はどうなった?
続きを見る
-

本多忠勝の生涯|家康を天下人にした“戦国最強武将”注目エピソード5選とは?
続きを見る
-

榊原康政の生涯|秀吉に10万石の賞金首とされた“徳川四天王”の生き様とは?
続きを見る
【参考】
日本人名大辞典
煎本増夫『徳川家康家臣団の辞典』(→amazon)
『家康の家臣団 天下を取った戦国最強軍団』(→amazon)