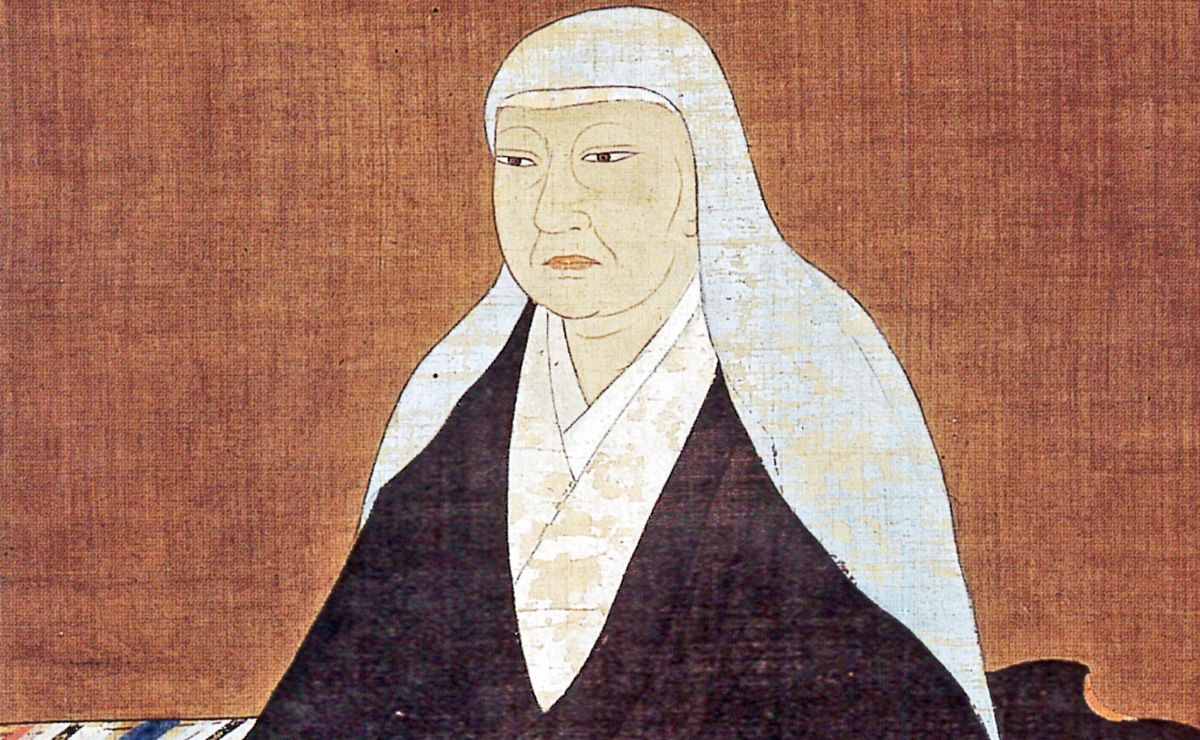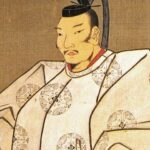天正二十年(1592年)7月22日は大政所の命日です(※21日説もあり)。
豊臣秀吉や豊臣秀長の母“なか”といった方がわかりやすいかもしれませんね。
実はこの名前も本当かどうか不明なのですが、他に候補となる名称もないので本記事ではそのまま使わせていただきます。
果たして日本史上最も出世した男の母親とは、一体どんな女性だったのか。

大政所なか/wikipediaより引用
大政所・なかの生涯を振り返ってみましょう。
👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅
秀吉を産んだ後に再婚
なかの出生地は尾張国愛知郡御器所村(ごきそむら)、現在の名古屋市昭和区だとされます。
生まれは永正十三年(1516年)ともされ、身分の低い出自で、家族関係などははっきりしていません。
なかの妹もしくは従妹が加藤清正の母とされていますので、清正が豊臣政権で重宝されたのも頷けますね。

加藤清正/wikipediaより引用
なかは織田家の兵だった木下弥右衛門に嫁ぎ、日秀尼(とも・豊臣秀次の母)と秀吉を出産。
秀吉と正室・ねねが恋愛結婚で結ばれたことは広く知られていますが、なかと弥右衛門は結婚すらしていなかったのでは……という指摘もあります。
身分の低い人々の間ではままある話で、その後、織田家に仕えていた竹阿弥と再婚したとされます。
では、豊臣兄弟で注目される、弟・豊臣秀長の父親は誰なのか?
弥右衛門なのか、竹阿弥か? というと、これがハッキリしていません。
もう一人いる妹の朝日姫も同様に父親は不明。

『絵本太閤記』に弥助昌吉として登場する木下弥右衛門/wikipediaより引用
なかは「とも・秀吉・秀長・朝日姫の他にも子供を産んだ」とする説すらあります。
後に秀吉が大出世を果たしたとき、なかの子供を自称する人々を処刑したという話があるからです。
しかも、処刑した理由が「なかが恥ずかしがったから」というもので……なんともモヤモヤしますが、この話が事実であれば、彼女が多くの男性との間に多くの子供を産んだ可能性は高くなりましょう。
よほどモテたか、確実に子供を産んでくれると見込まれたのか。
当時、子供は労働力であり、かつ幼少期の死亡率が高いため、「体が丈夫で出産経験がある女性との間に子を作りたい」と考える男性が多かったであろうことは想像に難くありません。
徳川家康の側室も、そういう傾向がありますしね。
いずれにせよ、母については厚遇した秀吉が、父や父方の親類について全く触れていないところからすると、関係は希薄でどうでもよい存在だったのでしょう。
秀吉は、父親に対して供養や官位の遺贈もしていません。
彼女が竹阿弥と死別した頃には、すでに秀吉も織田家に仕え始めていたため、その後は息子を頼るようになっています。
ねねとも実の親子のように仲が良かったそうです。

秀吉の妻・ねね(寧々 北政所 高台院)/wikipediaより引用
二人は、ずっと尾張弁で話していたそうですから、親近感も湧きますし、互いに落ち着く相手だったのでしょう。
本能寺の事件直後は長浜城から大吉寺へ
天正十年(1582年)6月2日に本能寺の変が勃発。
秀吉が天下人へ向かう契機ともなった事件ですが、直後にそんな未来が待っているとわかるはずもなく、全国の戦国武将と同様、なかの生活も激変します。
まず変が起きた直後、長浜城が明智軍に落とされると、彼女とねねは大吉寺というお寺へ逃れました。

明智光秀/wikipediaより引用
大吉寺は源頼朝が平治の乱後、一時匿われたという伝説のある古いお寺であり、天下人やその家族に縁があるんですかね。
一時はかなり大規模な勢力を誇りましたが、何らかの理由で織田信長に破却されたため、当時はかなり寂れていました。
だからこそ逃げこむには適していると考えたのかもしれません。
長浜城から大吉寺までの距離は約16km。
舗装された現代の道路でも徒歩なら4時間弱かかりますので、よくこの距離を女性の足で逃げられたものです。
輿に乗っていたとしても、相当な恐怖だったでしょう。
なんせ息子の秀吉と、秀吉をサポートする弟の秀長は、中国地方で毛利軍と対陣しているわけで、女性二人が絶望的な気持ちになっても不思議ではありません。
この逸話自体が創作の可能性もありますが、二人が危険な状態にあったのは間違いないでしょう。
琵琶湖対岸にある坂本城は明智軍の最重要拠点です。
その距離、約76~80kmであり、いわば目と鼻の先に潜んでいなければならず、また何時助けが来るかもわからない状態でした。
と、そこへ颯爽と現れたのが他ならぬ秀吉でした。
毛利と素早く和睦を結んだ秀吉は、その後、中国大返しと呼ばれる行軍で畿内へ戻り、信長の弔い合戦である【山崎の戦い】で光秀に完勝するのです。
中国大返しは、神のごとき速さの進軍――ではなく、最近は「普通の行軍だよね」とする考え方が主流のようですが、そもそも毛利と和睦を結び京都までやってきた秀吉の行動力が光秀を驚かせたのは間違いないでしょう。
その後、清洲会議を経て、天正十一年(1583年)に賤ヶ岳で柴田勝家を撃ち破ると、秀吉は織田家の権力掌握に成功します。
そして、なかとねねを大坂城に呼び寄せると、次の敵と対峙する準備に取り掛かるのでした。
敵とは他でもありません、徳川家康です。
小牧・長久手の戦い
織田家のトップに立った秀吉にとって実に厄介だったのが、尾張や近江に程近いエリアで精強な将兵を抱える徳川軍でした。
信長存命の頃は、織田と堅い同盟で結ばれていた徳川。
信長亡き今、家康が秀吉に従う筋はありません。
むろん秀吉とて百も承知で、だからこそ両者は激突します。
天正十二年(1583年)3月に始まった【小牧・長久手の戦い】ですね。
これが非常に複雑な決着となりました。
両軍が、非常に広大なエリアで城に入ったり、砦などを築いたりして、睨み合いの時間ばかりが過ぎてゆき、なかなか大きな戦闘には至りません。
例外と言えるのが、秀吉軍の森長可と池田恒興ぐらい。

池田恒興(左)と森長可/wikipediaより引用
彼らは、徳川軍不在の三河を攻撃するため【中入り】という戦術を実行したのですが、その作戦が家康に読まれて完膚なきまで叩かれ、結局、森長可と池田恒興は討死してしまうのです。
しかし、その激戦はあくまで例外的な戦闘です。
他のエリアではジリジリと睨み合いが続き、結局、天正十二年(1583年)11月、徳川軍が担ぎ上げていた織田信雄が勝手に秀吉と和睦をしてしまい、合戦は終了と相成りました。
要は武力で明確にカタをつけられたなかったわけで。
ここからは秀吉による政治外交手腕の見せ所であり、そこで最終的なキーマンとなったのが“なか”でした。
いったい彼女は何をしたのか?
妹の朝日姫が家康に嫁ぎ
小牧・長久手の戦いが終わった後、秀吉の目標は徳川家康を臣従させ、傘下に収めることでした。
石高も配下の勢力数も「秀吉>家康」なのは明白。
あらためて事を構えるとなると勝ち目は薄く得策じゃないと踏んだ家康は、ついに秀吉への臣従を決意します。
しかし、です。
家康がなかなか上洛に応じません。
いざ秀吉の前に出たりすれば殺されてしまうのではないか――そんな懸念を徳川家臣たちが抱いていたというのは、ごもっともな話であります。
そこで秀吉が大技を繰り出します。
妹の朝日姫を嫁がせ、さらには母のなかも一緒に徳川方へ送り込むことにしたのです。

朝日姫(旭姫)/wikipediaより引用
実は天正十三年(1585年)7月、秀吉は関白となり、その就任と同時になかは”大政所”の号と女性の最高位階【従一位】を与えられていました。
秀吉の母というだけで、突然仰々しい位階を貰い、彼女は何を思ったか。
当時は、大和郡山城の豊臣秀長を訪ねたり、寺社に参詣したり、割とアクティブに過ごしていたようですが、合間に体調を崩すことも珍しくなかったようです。
それでもとにかく、秀吉は母と娘を徳川方へ送り、一刻も早く家康を上洛させたい。
すると家康は、ようやくのことで上洛を決意。
引き換えに娘と共に岡崎へ送られた“なか”に対しては、三河武士の強烈なエピソードが残されることとなりました。
それは一体なんだったのか?
家康の忠臣に殺されかけた?
強烈なエピソードを残した三河武士とは本多重次のことです。
気性が荒いことから通称”鬼作左”としても知られる武将であり、

本多重次/wikipediaより引用
なかが滞在する館の周りに火を放つ用意を整えていたというのです。
「ウチの殿に何かしやがったら、お前の母親を焼き殺してやる!」
というわけですが、これって予め秀吉に伝えておかないと意味がないですよね。
それに、仮に家康が殺された後でなかを殺しても、その後、家康のいない徳川軍が強大な豊臣軍を相手に勝てるのか? 下手すりゃ丸ごと潰されてしまいそうで……。
本多重次については、他にも短気すぎるエピソードがいくつも伝わっているので、後のことを全く考えていなかった可能性が大かもしれません。
そしてこうした動きに対し、秀吉の反応は二つ伝わっています。
「激怒して家康に”重次を追い出せ!”と命じた」
「”家康殿はさすがに良い家臣をお持ちだ”と笑って許した」
事が事ですし、秀吉の性格からしてどちらもありえそうな気がしますね。
秀吉の渡海を止める
朝日姫と共に輿入れして、徳川での生活が約一ヶ月続いた“なか”。
無事に大坂城へ戻ると、その後、一時は聚楽第に住んだこともありましたが、大坂城のほうが落ち着くのか、すぐに戻っています。
京より大坂の雰囲気のほうが性に合ったのかもしれませんね。
天正十八年(1590年)辺りからは、加齢のためと思われる体調不良に悩まされ、さらには朝日姫や豊臣秀長に先立たれるなど、不運が続きます。

豊臣秀長/wikipediaより引用
なかは永正十三年(1516年)生まれとされているので、年齢的には死を意識してもおかしくない年齢です。
本人もそれを自覚していたらしく
「私が生きているうちに、墓の支度をしてほしい」
と秀吉に頼んでいます。
秀吉はさっそく母のために土地を探し、お寺の建立を始めさせると、落成した頃にはすっかり元気になっていたそうです。
心配事がなくなって安心したんですかね。
そんな最中、秀吉が文禄・慶長の役における出兵を決め、再び老いた母親の心身に負担をかけます。
秀吉は当初、渡海する気満々でした。
しかし「せめて大陸に渡るなんて危ないことはしないでおくれ」と懇願する老母に逆らえなかったことも、渡海を取りやめた一因だったといわれています。
もちろん、浅野長政など家臣たちの反対もありました。
母の死に目に会えなかった秀吉
文禄・慶長の役において日本側の最前線基地だった名護屋城。
秀吉が名護屋に対陣している間、京を預かっていたのは、秀吉の甥で養子となっていた豊臣秀次(なかにとっては孫)です。
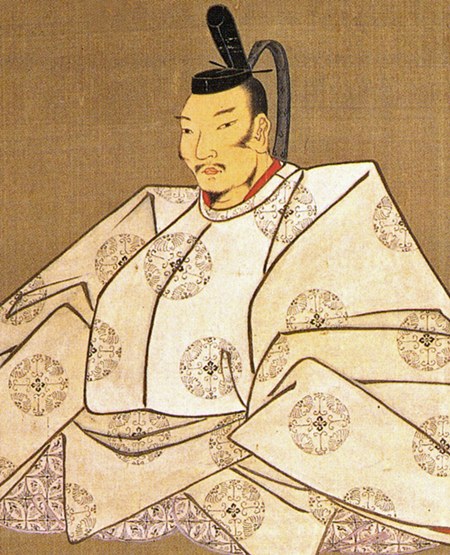
豊臣秀次/wikipediaより引用
当然なかの経過についても知っていたはずですが、秀吉に心配をかけまいと、なかの病状をギリギリまで知らせなかったとされています。
しかし、なかの命が尽きるほうへ向かっていることは日に日に明らかになっていきます。
それまでは、なかが体調を崩しても、祈祷をすれば早く治ったのに、このときはその兆しがみられなかったのです。
「いよいよか……」
そう考えた秀次は、急いで秀吉になかの危篤を知らせます。
秀吉は仰天し、大急ぎで名護屋を出立しましたが、なかはその当日である天正二十年(1592年)7月22日に亡くなってしまっていました。
大坂に到着してから母の死を聞かされた秀吉は、その場で卒倒するほどの衝撃を受けたといいます。
秀吉は誰に何を言われても、病死者や餓死者の報告が届けられても、朝鮮半島への出兵を諦めませんでした。
それは、母の死に目に会えなかったことを後悔した分、意固地になっていたからなのかもしれません。
なかが秀吉より長生きする可能性は極めて低いにしても、朝鮮出兵をしなければ、ほぼ確実に看取ることができたでしょうし。
もしかすると、なかの命日は秀吉が生涯で一番後悔した日なのかもしれません。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
一方でなかとしても、息子が出世して孝行してくれたことは嬉しかったにしても、朝鮮出兵のゴリ押しを止められなかったことは悔やんだでしょう。
しかもこの三年後に秀次事件と、それに続く秀次の妻子処刑が起きています。
「もしも」の話になってしまいますが、秀次事件までなかが健在であれば、彼女が妻子の助命嘆願に動いたのではないかとも思えます。
秀次の子供は、なかにとってひ孫ですからね。
秀吉の養子や実子の多くが若くして亡くなっていることも含めて、何者かが豊臣家の滅亡に向けて着々と進めていたようにすら見えてきます。
👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅
あわせて読みたい関連記事
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】
続きを見る
-

豊臣秀次の生涯|殺生関白と呼ばれた秀吉の甥はなぜ自害に追い込まれたか
続きを見る
-

豊臣秀頼の生涯|大坂城に居続けた秀吉の跡取りは淀殿と共に滅ぶ運命だった?
続きを見る
-

秀吉の妻ねね(寧々/北政所/高台院)の生涯|天下人を支えた女性の素顔
続きを見る
参考文献
- 菊地浩之『豊臣家臣団の系図』(KADOKAWA, 2019年11月, ISBN-13: 978-4800318014)
出版社: KADOKAWA 公式書籍情報 |
Amazon: 商品ページ - 堀 新・井上泰『秀吉の虚像と実像』(笠間書院, 2016年7月, ISBN-13: 978-4305708144)
出版社: 笠間書院 公式書籍情報 |
Amazon: 商品ページ - 歴史読本編集部 編『物語 戦国を生きた女101人』(新人物文庫, KADOKAWA, 2014年6月, ISBN-13: 978-4046000606)
出版社: KADOKAWA 公式書籍情報 |
Amazon: 商品ページ - 国史大辞典(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979–1997年刊)
出版社: 吉川弘文館(ジャパンナレッジ公式紹介ページ)